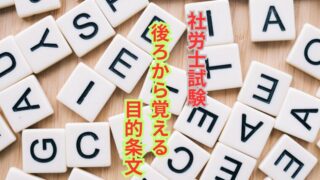社労士試験 いよいよ試験直前。7月からの過ごし方【経験談】

もうすぐ社労士試験の本番ですね。
そろそろ発狂したくなってきたという方も多いのではないでしょうか。
私は家族曰く、「結構ピリついていた」そうです💦
それはそうですよね、何か月も、何年も時間をかけてきたことの成果が問われるわけですから。
はじめに
現在、7月上旬です。
社会保険労務士試験まで約2か月を切るという時期になりました。
この時期になると焦りも出てきて、「今年は厳しいかも・・・」と考えてしまう期間でもあります。
私は残りの期間でひたすら「問題を解く、〇×の記録だけ書き込む、問題を解く」の繰り返しを行うという選択をしました。
自らの反省も含め「今なら直前期をこう過ごす!」という思いをお伝えできればと思います。
やりきれそうな目標を立てる。
もう試験まで「時間が無い」
一方でこの約2か月が勝負です。
ここでグッと実力が高められます。
何か不思議ですよね、試験の時期が近づくにつれ気合も入りますし、これまで頭に入らなかったものも詰め込むことが出来る。
直前期という不思議な期間をフル活用しない手はありません。
まずは残りの期間で何をするべきか計画を練りましょう!
残りの期間で勉強したいこと、勉強しなければならないことは何個も思いつきます。
しかし、とても全てはやっていられない・・という状況です。
最初から無理な計画を立ててしまっては「あぁ、結局終わらなかった」「やっぱり無理だったか」とマイナスな気持ちで試験を迎えることになってしまいます。
確実にこなしていける、または多少無理すればこなせるであろう分量を割り切って決めてしまいましょう。
決めた分量以外はポイっと部屋の隅に積み上げてしまってOK!
それらの教材をやっている時間はありません(笑)
決めた分量をこなすことが出来たというのは、自信にもつながりますよ!
決めたことをひたすら行う!やり切る!
メインは問題集
私の場合は「ひたすら問題を解く」という計画を立てました。
使用したのは学校で配布された「基本問題集」とTACから販売されている「過去10年問題集」です。
この2つを選択したのはこれまで解いてきたというのが1番の理由ですが、加えて見開き問題種(左ページに問題、右ページに解答が記載されているもの)であるためです。
この時期になると1分1秒が惜しいですし、時間が無い中で目標をこなしていくためには高速回転させることが大切です。
見開き問題集であれば、左・右・左・右とサクサク進めることが可能です。直前期は問題を解きまくるという目標を立てた方にはぜひ見開き問題集をお勧めします。
スピードはもちろん大切ですがただ〇・×を当てるだけでは意味がありません。
何故正解したのか、間違えてしまったのかをしっかりと説明できるかを迅速かつ丁寧に確認しましょう。
また見開きの問題集を進めるなら、机に向かっているときだけでなく電車、トイレ、お風呂などでも進めることが可能ですが、私は机に向かって集中できるときだけに限定していました。
スキマ時間を活用するのも有用ですが、しっかりと考えて問題をこなしていくため、机に向かっている時は問題集に全力投球です。
スキマ時間の活用
机に向かっている時は問題集のみをやっていましたが、それ以外のいわゆるスキマ時間では
・目的条文の暗唱
・テキストの確認
をしていました。目的条文の暗唱についてはこちらの記事で紹介していますので、ぜひ試してみてください。
テキストの確認ですが、全てを読むことは不可能ですので、問題を解いている中でもう一度確認しておきたい、何度も間違えてしまいうまく説明できない点に絞って確認するだけにしていました。
一方であとから聞いた話になりますが、直前期にテキスト全てをじっくり読み込んだという人も私の周りには何人かいらっしゃいました。
これまでアウトプット主体で7月を迎えたという方は、ここで1度インプットを行うというのもアリかもしれませんね!
注意点(私の反省点)
直前期を過ごした中で、今思えば不要なことを行って時間を無駄にしてしまったと思う点も多々ありましたので、そうした点も共有したいと思います。
人それぞれの勉強方法がありますので一概には言えませんが、もし同じようなことをされている方がいるようでしたら、その比重を軽くしてみてもいいかもしれません。
模試の理解に時間を掛けすぎない
直前期には模試を受験している方も多いと思いますが、成績はいかがだったでしょうか?
私は合格した年の模試でもD判定を取っていましたので、最後まで諦めずに突き進みましょう。
模試の結果を受け復習するのは非常に大切ですが、私は模試の理解にかなりの時間を掛けてしまっていたのが反省点の1つです。
本番と同じ問題数かつ初見の問題ばかりですので、それなりに時間が掛かるのは当然です。
私は「たくさんの人が受けている模試だから、一言一句逃さず、どんな難易度の問題でも取りこぼしてはいけない」という思いに脳みそを支配された結果、隅々まで調べ尽くしていました。
テキストに載っていないような細かい点については「そんなことどこに書いてあるんだ?」というのが気になってしまい、条文や通達などを検索して、探すといったことまでしていたのですが、これは時間の無駄だったと思います。
模試終了後に配布される解答には難易度や重要度などの記載もあると思いますので、それを有効活用して、絶対に落とせない問題を優先的にやりましょう。
試験当日も大事なのはとりこぼさないことで、満点を取ることではありません。細かい点や興味のある点は合格後でもいくらでも勉強することが出来ます!!
しないと思いますが(笑)
インターネットの情報に翻弄されない
インターネットや体験記にも直前期にはこれをやるべし!今年はコレが出るらしい!といった情報が溢れ返っています。
私も様々な情報収集を行いました。
最後はテキストを読み込むべき、本番と同じように五肢択一の問題をやらないといけない、選択式に注力するべきなどなど。
そういう意味では私のブログもその中の1つになってしまいますが、やり方も効果も人それぞれだと思います。
調べるのは非常にいいことだと思いますが、そこに踊らされることなく、これまでの勉強で行ってきた方法を軸に、有用だと思う情報だけ取捨選択していきましょう。
そしてコレと決めたら即実行です。
ちょっと試してみて、何か違うなと感じたらすぐに別の方法へ切り替えましょう。
やっぱり基本が大事
最終的に重要となってくるのは基本的な問題です。
原理原則が分かっていなければ、それ以外の論点についても理解が追いついていきません。
私の場合は社会保険の知識がどうしても断片的だなと感じていたので、問題を解くのと共にスキマ時間には社会保険のテキストを読んでいました。ただ読むだけではなく、普段は読み流してしまうような基本的な記載、例えば
「何のための制度なのか」
「どうしてこの制度が必要なのか」
といった点を気にしながら読むようにしていました。
また、問題集を周回しているときも、前に解けたからといって、今回も解けるとは限りませんので、何度も正解している問題も飛ばすことなく全ての問題に取り組むようにしていました。
本当のことをお話すると、「基本が大事」なんて偉そうに書いていますが、実はそれを真剣に感じたのは合格後です。
同じ年に合格した主婦さんが「テキスト」、「基本問題集」、「5年分の過去問」のみをやり込み、1発合格したというのです。
この話を聞いたときの衝撃は今でも忘れられません。
そして、結局は「基本が大事」なんだなというのを痛感しました。
なかなか実践するのは大変ですが「基本が基本」です(笑)
選択式は思考力も磨きましょう
選択式は本当に厄介ですよね。
取るべき問題を落としてしまったら、それこそ致命傷になりかねません。
そして、本試験では必ず知らない問題が出てきます。
特に二つまでは答えの候補を絞ることができますが、そこからはどのように選択したらいいのか分からず、最後は運任せ!!という場面にも出くわす可能性大です。
しかーし、そこで立ち止まり運任せにするのか、しっかりと考えられるのかで、大きな違いが生まれる可能性もあります。
何か知っている情報、関連する情報を頭の中で駆け巡らせれば「この手続きは毎月だと手間がかかりすぎるから毎年が妥当じゃない?」といった発想が出てくるかも!
本番でも「どっちが正解だろう・・・」と悩む場面が必ずありますので、普段からそうしたときにどのような思考でどの解答を選択するかといった練習をし、本番でも同じようにするのがオススメです。
息抜きしましょう
最後の2か月はあっという間です。
時間が無い!余裕も無い!やることたくさんありすぎる!という状況です。
大丈夫です、みんな同じです。
ですから、たまには息抜きしてください。
本番へ向けて突っ走った結果、当日に体調を崩しては意味がありません。
当時、学校の先生が言っていたのですが、毎年、当日に体調不良となってしまい受験できなかった、受験はしたが全く実力が出せなかったという方がいるそうです。
そうならないよう、自分なりの息抜き方法を決めて、たまにはリラックス。
私の場合は、「今週も仕事と勉強を頑張ったなー」という金曜日の深夜と、「土日も徹底的に勉強したなー」という日曜日の夜だけ、ビール1本を飲みながら海外ドラマ1本を見るようにしていました。
息抜き方法が決まっているとそこに向けて頑張ろうという気持ちにもなれますよ!
最後に
直前期は実力が一番つく時期とよく言われています。
どのような根拠があるのかは分かりません。でも、私の体感としてもそれは事実だと思います。
だからこそ、嫌でも気合の入る直前期を有効活用して、どんどん実力をつけていきましょう。
作戦を立てて、あとはそれをひたすら遂行するのみです。
完遂できる目標を立てるのを忘れないでくださいね。遂行できなかったら、やり切ることが出来なかったという気持ちで試験に臨むことになってしまいますから。
やることはやったぜ!という姿勢で本番を迎えられるよう、淡々とやるべきことをやる!