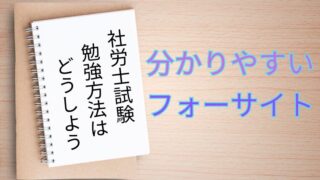社労士試験 目的条文の覚え方
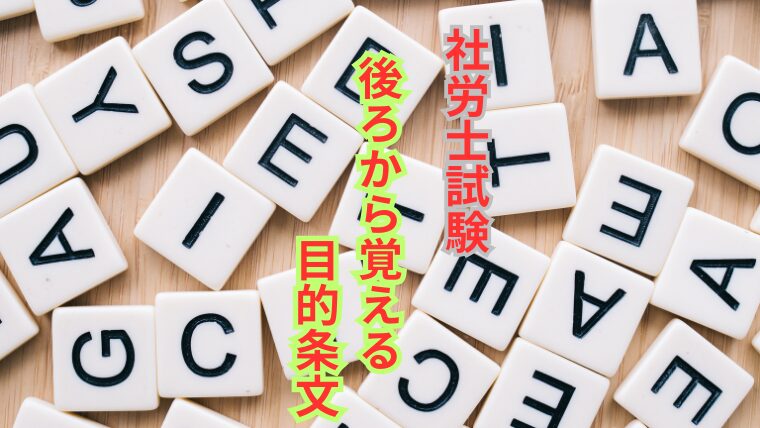
目的条文が全く頭に入ってこない。覚えられない。つまらない。
その気持ち本当によく分かります!
やらなきゃ、やらなきゃと思いながらついつい後回し。
気分転換にもなるかもしれませんし、たまには目的条文を後ろから読んでみませんか??
出たら落としたくない目的条文
社労士試験では基本的な問題を取りこぼしてはいけないと言われますが、毎年のように要注意と言われているものの1つに「目的条文」があります。
出るかもしれないと思いつつ、出ないでくれと願い、いざ出てしまったら「あー、やっぱりちゃんと勉強しておけばよかった・・・」と激しい後悔に襲われてしまうのが目的条文の厄介なところです。
なかなか頭に入ってこないから、意外と勉強が疎かになってしまっているのではないでしょうか。
もしくは、丸暗記したいから直前期に一気に頭に詰め込んでしまおう!という作戦を立てている方もいらっしゃるかもしれません。
作戦としてはアリかもしれませんが、かなり計画的に、緻密に、綿密に勉強スケジュールに則って勉強しているという方以外、直前期にそんな余裕はありません!!
思い立ったら今すぐ、毎日少しずつでも目的条文の勉強に取り掛かりましょう。
目的条文の暗唱
私がオススメする目的条文攻略は以下の5つの工程になります。
簡単に覚えられるような魔法の方法ではありません。書いていることはごく普通のことです。しかし、私が読む、書く、聞くなど色々と試した中で最も効果的だった方法ですので、普通に勉強していても何かしっくりこないなぁという方はぜひ試してみてください。
1.目的条文集を手に入れる(または作る)
2.まずは一読してみる
3.構造を把握する
4.暗唱に挑戦
5.ひたすら繰り返す
1.目的条文集を手に入れる(または作る)
目的条文を見るためにテキストをめくるのは大変です。
通っている学校や受講している講座で何か目的条文に適した教材があればそれを活用しましょう。
または、ひととおり基本講義が終了した時期などですと、資格学校で「横断セミナー」が開講されます。そうした講義を受講される方は、テキストに目的条文だけがまとまったページなどがあると思います。ぜひそのページを活用しましょう。
手元にそんなテキストが無いという方はインターネットで「社労士 目的条文」と検索すればまとめて掲載してくれているページなどが多数見つかりますので、自分の好みに合うサイトを印刷してしまいましょう。
目的条文攻略への第一歩として、多少は時間が掛かりますが自ら書く、入力することで作成してもよいかもしれません。
私はこちらの書籍を活用していました。
目的条文だけを掲載しているページがあり、しかも読みやすいように「意味のかたまり」、「切れ目となる用語(よって、もって etc)」を意識した記載になっているので、目的条文を集めるのが手間だという方は、買ってしまった方が早いですね!
2.まずは一読
目的条文を一読してみましょう。
法律の名称と目的条文を読んだ上で、その法律のイメージは沸いてきたでしょうか!?
イメージが全くわかないものについては、テキストに戻って、その法律に定められている施策やキーワードを軽く復習しておきましょう!
その法律のイメージとは例えば「次世代育成支援対策措置法」と聞いて、「一般事業主行動計画の策定」といったことが思いつくかどうかです。
記憶に焼き付けるにはイメージも大切!!
3.構造を把握する
目的条文を一読していると似たような構造になっているものも多いなということを感じることありませんか??
具体的には
「~~するため●●し、××を講ずることで、■■を図り、もって○○に資することを目的とする。」
といったパターンなどです。
構造を把握しておくことで文章の流れ、つながりを感じることが出来るため、目的条文の意味を噛みしめて理解しながら暗唱することが出来ます。
4.言葉づかいを気にする
法律には決まった言葉のルールがいくつもあります。
代表的なのは「及び・並びに」、「又は・若しくは」の使い分けなどです。これらの用語、しっかり使い分けていますか!?
日常では必要のない知識かなと思いますが、条文を読む時に意識してみると結構役に立ったりしちゃいます。
ちなみに、普段の仕事の中で文書、レポート、報告などに触れる機会は多々ありますが、たまーーーにこれらの用語をガッツリ・しっかり使い分けている方に出会うこともあります。
そうした文書を読んだときは「この作成者、タダ者ではござらぬな・・・」と私は警戒してしまいます(笑)
他にも有名な言葉づかいとしては「その他」と「その他の」の使い分けなどもありますね。
言葉の使い分けを知っておくことで、目的条文がどのような作りになっているのかといったことや、「この単語とこの単語は並列の関係なのか!」といった読み方が可能になります。
こうした法律、条文、言葉遣いに関するルールなんて全く知らないよ!
そんなのどこに書いてあるんじゃーという方にオススメの本がありますので、ぜひ手に取ってみてください。
書いてある内容が参考になるのはもちろんですが、掲載されているコラム(最も条文数の多い法律、少ない法律は?)なども非常に面白いです。
値段も比較的お安く、薄くて読みやすいので、合格後は士業で活躍していくんだという方は今から勉強しておきましょう。
5.暗唱方法
では、実際にやってみましょう!!
短めの目的条文として、ここでは派遣法をサンプルとして使用します。
派遣法の目的条文は
「この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」
です。
まずは前準備として、条文集に「/」を書き込み、以下のとおり分解します。
「この法律は、/職業安定法と相まって/労働力の需給の適正な調整を図るため/労働者派遣事業の適正な運営の確保/に関する措置を講ずるとともに、/派遣労働者の保護等を図り、/もつて派遣労働者の雇用の安定/その他福祉の増進/に資することを目的とする。」
全部で9つのパートに分解しました。
文の切れ目かな、意味の切れ目かなという所で、あまり長くなりすぎない範囲で分解していればOKです。特に細かいルールはありません。
ここからがポイントです!!
それでは、
一番最後から、覚えていくつもりで、読みましょう!!
まずは「に資することを目的とする。」が言えるようになるまで声に出します。
このフレーズだけ読んでいると「何に資するのだろう?」と疑問に思います。派遣法に関連する言葉が来るのかな!?など、想像してしまいます。
次は分解したパートを1つ付け足します。「その他福祉の増進に資することを目的とする。」とつなげて読んでみます。
ここで「福祉の増進」に「資する」ことが目的だったのか!と判明しました。
そして、まだ疑問がわいてきます。
「誰の福祉の増進」なのだろうか?「その他」って書いてあるからには、その前には何かつながってくるのだろうか?と。
では、もう1パート追加です。「もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」。
法律の名前どおり、「派遣労働者」のためを思って作られた法律なのか!ということがここで分かりましたね。
このあたりから少しずつ苦しくなってきますが、冒頭から覚えるより頭に残りませんか?
それに段々と文章の意味が分かってくる感じがしませんか?
あとはこれをひたすら繰り返すだけです。
もちろん全てを言えるようになるためには時間もかかりますし苦しいですが、1日で全てを言えるようになる必要はありません。
しかし、考えながら声に出していけば、ただただ読んでいるだけよりイメージも沸きやすくなり、記憶の定着につながります。
頭から読んでいるとスラスラ読めますが、何も考えずに「ふむふむ、なるほど」としか思わないですし、キレイに文章がまとまっているなーと思うだけで、頭に引っかかるものが何もありません。
お尻から読んで、大いに疑問を持ちながら、目的条文を噛みしめていきましょう!
おわりに
目的条文は重要語句を覚えておけば、穴埋め対策としては十分かもしれません。
しかし、各条文とも似たような語句が使われていますし、試験問題はいかにも当てはまりそうな語句ばかりが語群に並んでいます。
そこで、私は目的条文はなるべく暗唱するという決断をしました。
全てをスラスラ言えればベストでしたが、そこまでには至りませんでした。しかし、この練習を何度も行ったおかげで、違う語句を当てはめて読んでみた場合に違和感を感じる程度にはなることができました。
年齢を重ねるにつれて覚える力も衰えているよなぁと感じる機会もあります。でも、何度も出会えばまだまだ十分頭の中に刻み込んでいくことが出来ます!
悩んでいる時間がもったいないです!
自分に自信を持たせる意味でも、丸ごと暗唱するという意気込みで愚直に取り組んでいくのが最も近道だと思いませんか??
目的条文は法律の要!法律を学ぶならアガルート