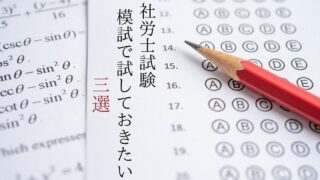社労士試験 前日・当日の過ごし方

あっという間に社労士試験の季節となりました。
8月に入ってもまだまだ実力を伸ばすことは可能です!
無我夢中で勉強しつつ、体調管理を最優先でお願いします。
そして前日・当日は心穏やかにがオススメです。
はじめに
現在は8月1日。
あと20数日で社労士試験の本番となります。
勉強に追い込みをかけるのはもちろんですが、本番に向けての準備、心穏やかに試験を受けるための準備も必要です。
勉強の合間にでもぜひ前日・当日のシミュレーションを行っておくのがオススメ!
「さぁ、いよいよだ!」とテンションも徐々に上がってきますよ。
私が前日、当日に心がけていたこと、体験したことなどを共有させていただきます。
少しでも参考になれば幸いです!
試験前日
受験生であった当時、試験前日に他の受験生は何をしているのだろうと思って検索してみたことがあったのですが、あまりそうした情報はありませんでした。
そのため、私個人の記録にはなってしまいますが、ここに記しておきます。
当時、SNSなどを駆使すれば簡単に知ることが出来たのかもしれませんが、その時は使い方が分かりませんでしたので・・・。
SNSを見る間もなく勉強していたということにしておきましょう(笑)
前日の勉強
3度目の受験ともなりますと「今年受かったらいいな」「当日は精一杯の努力をしよう」などという前向きな気持ちはありませんでした。
「もうイヤじゃ!」「今年こそ終わらせてやる」という狂喜に満ちた気持ち。
「とにかく試験終わってくれ」「とりあえず今年度の勉強から解放されたい」「結果はどうであれ、とにかく休みたい」という目先の幸せしか見ていない気持ち。
こうした気持ちが強かったことを今でも覚えています。
とにかく合格したい!という気持ちの表れでもあります。
そのためなら最後の1分1秒まで勉強してやる、いや、やらねばならないという使命感はありましたが、翌日の本番に備えた休憩も必要です。
そこで、前日の勉強に制限を設けないとキリが無いので、勉強していいのは試験前日の18時までと事前に自分の中で決めていました。
実際は計画していた問題集を16時ころにやり終えたので、16時で勉強終了となりました。
前日には横断的に全科目をザーっと復習したいという思いもありましたが、そんな余裕も無く、計画していた問題集の周回を無事に終わらせfinishです。
その後は、一切勉強を断ち切り、翌日の試験に向けた準備をして、テレビを見たり、インターネットで試験が終わった後にやりたいことなどを検索していました。
最後の1秒まで無駄にしないで勉強するという選択肢もあったのですが、終わりが見えなくなってしまいますので、ある程度のところで踏ん切りをつけるという選択をしてよかったと感じています。
前日の食事
社労士試験は全部で3回受験しましたが、毎回、前日の夕食は何故かデパートで購入してきた「ウナギ弁当」を食べていました。
自分へのご褒美&翌日に向けてのパワー注入です。
過去2回それで失敗してきているので、3年目はさすがにメニューを変えた方がいいかなとも思いましたが、決めていたルーティンを崩す勇気もなく、ウナギ弁当を満喫しました。
こんなこと聞いても何も参考にならないかもしれませんが、お伝えしたいのはここまで勉強を頑張ってきたのですから、前日には少しリラックスして、自分にプチご褒美をしてあげるのもオススメですということであります。
人にもよると思いますが、翌日のおトイレに影響するようなものは避けた方がいいですよ。
私は辛いもの、ニンニク系の食べ物も好きなのですが、すぐにお腹をくだしてしまうため、試験前日はNGです。
試験前日の夜に何を食べようかな?って考えるのも意外と楽しくないですか?
ここまで来たら何でもポジティブに楽しく考えてしまうしかない!!
前日の睡眠
試験当日に眠くなってしまうということはまずないと思います。
それだけ必死に集中していますから。
それでも睡眠は侮れません。
決して夜更かし、徹夜などはしないようにしてくださいね!
私は10時か11時には布団に入り、たっぷりと睡眠をとりました。
ここで大切にしていたのは「昼寝」をしないことです。
勉強しているときに集中力が途切れたなと感じた時は10分~30分ほどの睡眠を小刻みにすることもありました。
しかし、試験前日は「No昼寝」です。
もちろん夜にサッサと眠りにつくために。
緊張や興奮で眠れないといったことがないよう、適度に自分を疲れさせてあげてください。
そして、前日は気持ちよく寝落ちしましょう!
試験当日
いよいよ試験当日です。
前日は早めに就寝し、6時頃に起床しました。起きてから3、4時間後は脳が寝ている、活性化していないみたいな話を聞いたことがあったので、それを信じての起床です。
会場へ向かう
よく言われていることですが、会場の周りは一度チェックしておくことをお勧めします。
行き方を把握しておくことはもちろんですが、昼食をどこで購入するのか、周りにカフェやコンビニはあるのか、そして私は喫煙者ですので、どこでニコチン補給できるのかも重要なポイントです。
幸い、私の受験場所の近くには通っていた資格学校がありましたので、当日の朝もその校舎の自習室に朝一で向かいました。もちろん勉強するのが目的ではなく、電車の遅延などに巻き込まれるのが嫌だったので、とにかく試験会場近くまで辿り着いて、落ち着いて座っていられる場所を確保したかったのです。
会場のすぐ近くにホテルがある場合などは、前日から試験翌日までの2泊分をあらかじめ予約しておくのもいいかもしれませんね。そうすれば、試験開始前、午前と午後の合間にも部屋に戻ることでリラックスすることができます。
試験後にはホテルでゆーーーっくり自由時間を楽しむというご褒美つきです。
翌日の仕事を休めるのであれば、ですが。
当日、会場へ行くこと自体に余計な体力の消費、心労を防ぐためにも対策は十分に考えておきましょう。
入室
試験会場の部屋へ入ったら、自分の席を確認するのはもちろんですが前後左右に座っている人をよーく観察しておきましょう。
試験会場には色々な人がいます。
随分と身体が揺れる人、せき・くしゃみをしている人、筆記用具をまわす・カチカチ音を立てる人、暑さでシャツがビショビショになっている人、貧乏ゆすりしている人、「あー、うー」と声?呼吸?か分からん音波の出ている人などなどなどなど。
近くの人を中心に観察してください。
そして気になりそうなことは事前に察知しておきましょう。
それは試験開始後に気になることが出てきてしまうと、一気に集中力が削がれるからです。
あらかじめ観察・把握しておけばそんなことに気を取られる心配もありません。
実際に私の前に座っている男性は非常に大柄で、汗をカキカキしている黒色のTシャツを着ている方でした。
大変失礼ながらも私は「試験中に汗のにおいがしてきても気にしない」「もちろんこの人が悪いわけでもない」と試験開始前に覚悟を決めることが出来ました。
実際にはそんなこともなく必要ない不安だったわけですが、その覚悟を試験前にすることができるのと、試験中に気になってしまうのでは非常に大きな差が出てくると思います。
試験官は誰なんだ?
私が毎回疑問に思っていたのが「この試験官は何者なのだろうか?」ということです。
後日知ったのですが、試験官の方たちは「開業されている社労士」の方とのこと。
開業されている社労士に「試験官やらない?」とお声が掛かったりするそうです。
もちろんお仕事としてやられています。
社労士の方が試験官なのであれば、解答を聞きたくなっちゃいますね(笑)
そんなことが言いたいわけではありませんで、試験官の方も「試験官としてのプロではない」ということです。
社労士試験の試験官は今回が初めてという方もいるわけです。
ですから試験官の方の段取りがぎこちないなといったことを感じる可能性もあります。
年に1度の大切な試験なんだからしっかりしてくれよ!と思いたくなってしまう気持ちも本当によく分かりますが、穏やかにいきましょう!
試験開始!選択式
選択式で「時間が足りない」ということにはならないと思いますが、各科目3点を必ず獲得しなければいけません。
しかも選択式が午前中に行われますので、ここで出鼻をくじかれると午後の気合い・体力が全て削り取られてしまいます。時間を掛けてじっくりと戦うために、私は以下の2点をお勧めします。
選択肢を見る前に解く
空欄には数字、言葉、文章が入る場合など様々なパターンがありますが、選択肢を見る前に文章の内容、文脈、自分の知識をフル活用して、自分なりの答えを問題用紙に必ず書くようにしましょう。
答えそのものではなくても選択肢の中に入っているであろうキーワードや数字だけでもいいです。
全く分からない場合でも、数字が入りそうだなとか、日数だろうなとかその程度でもいいので当たりをつけておくことをお勧めします。
必ずやってほしい理由ですが、選択肢欄に並んでいる言葉が全て「魅力的」に見えてしまい、どれも正解に見えてくるからです。
社労士の各科目は似たような用語や数字がただでさえたくさん出てきますので、あらかじめ答えの目星をつけておかないと悩みに悩むことになります。
直感を信じる。答えは変えない。
私は救済処置によって合格しました。
その原因となったのが選択式の答えを1問書き換えてしまったことです。
それによって1科目だけ5問中2問の正解となってしまい、この科目が救済されるか否かだけを気にしながら合格発表を待つという、落ち着かない期間を過ごしました。書き換えなければ正解していたので、本当に後悔しました。
よっぽど自信が無い限り答えは変えるなと言われていると思いますが、一方では「あー、あそこで答えを修正しておけば・・・」という場合もあると思います。
ですから、日ごろから問題などを解いている中でも自分の直感が合っていたのか、それとも直感で答えたものよりも、改めて考えなおした答えの方が合っているのかを確認しておくことをお勧めしたいです。
その上で、本番で悩んでしまった場合にはどちらの回答を記入するのかを決めておくようにしましょう。
自分で決めたルールに従っていれば、どのような結果になっても受け入れやすいと思います。私はそのルールも決めておらず、何か違うかもと感じたままに行動して、結果、後悔することになりましたので「直感を信じる」のがベストだと決めています。
午後は択一式
択一式は選択式とはガラっと雰囲気も変わりまして、時間との戦いでもあります。
急いで読んで、考えて、選んで、記入しなければなりません。事前の準備とも言えますが、択一式を解く上で以下の点は決めておくべきでしょう。
問題を解く順番
私は社会保険科目があまり好きではありませんでした。また、美味しい食べ物は最後に食べるタイプです。
以上のことから、問題を解く順番は健保→厚年→国年→労基→労災→雇用→一般常識と決めていました。
本当であれば苦手科目から好きな科目へと細かく設定したいところではありますが、問題冊子を行ったり来たりするのは時間がもったいないですし、混乱してしまいますので健康保険から始めるというシンプルなルールだけにしました。
問題を解く順番は模試などでも試してみて、ぜひ自分にとって一番しっくり来るものを見つけ、しっかりとプランを立てておくべきです。特に気にならない、こだわりが無いという場合は最初から解いていくのが良いでしょう。
マークシートに記入するタイミング
問題を解く順番を決めたら、マークシートに記入するタイミングも決めておきましょう。
ちなみに私は一科目が終わるたびに記入していました。1問ずつ記入するのは何往復もするのが面倒ですし、最後にまとめて行うのも時間が無くなったり、記入がずれてしまうとパニックになりそうです。
また、科目ごとにすれば頭の切り替えにもなるかと思って、科目別の記入と決めていました。
加えて、答えに悩んでしまった問題でも必ず「これかなぁ・・・」と思う回答にマークをしておきました。塗り忘れて取りこぼすのはもったいないですし、とりあえずマークせずに空欄にしておこうとしても、そのこと自体を忘れてしまうと解答がズレてきてしまいます。
マークミスは最も避けたい事態ですし、自分なりの解答ルールも決めておきましょう。
見直すべき問題の把握方法
正解候補の2肢までは絞れたけれど、どちらかに絞るためにはもっと時間を要するなというときは、とりあえず後で考えるという決断も必要です。1問に掛けられる時間は限られていますし、のんびりしている時間はありません。
でも、後で解こうと思ってもその問題はどこだっけ?と探すのに時間を使うのももったいないですね。
そこで私が実践していたのが、自分用の解答欄を作成することです。これはどこかの学校の講師が言っていたものをそのまま実践しただけなのですが、非常に有用だと思います。
実際にどのようにしていたのか、こちらの記事もよかったらご参照ください。
具体的に何をするかといいますと、試験開始後すぐに問題用紙の一番前や一番後ろの何も書いていないページに縦を科目、横を問題番号にした7×10の表を手書きで作成します。そしてそこに解いた問題の答えを書き込んでいくのです。解いていく中で、迷った問題には?マークや、第二候補となる選択肢も併せて記載しておき、見直しの時間ではマークがついている問題を優先的に確認していきます。
また最後にマークミスが無いかなども容易に確認できますので、非常におすすめです。
ただし、択一式の試験開始後すぐに鉛筆を使う人は滅多にいませんので、室内に鉛筆を使用する音が響き渡ります。実際に、コイツは何をしているのだという感じで周りの受験生数名がこちらをチラチラと見ていました(笑)
でも、人の目線なんて気にしていられません!本当にお勧めの方法ですので、ぜひ模試などで試してみてください。
答え合わせはいつする?
試験終了後の大きな悩みですよね(笑)
私の場合ですが、試験終了後2~3日間は採点せずに終わった解放感を思いっきり満喫しようと思っていました。
しかし、あまりにも気になりすぎて結局は試験当日の午後9時頃には採点していました。
その結果、選択式で1科目、基準点割れしていることが判明し、失意のどん底へ。
あーやっぱり採点するのはやめておけばよかったとも思いましたが、やはり気になるものは気になる。
答え合わせをいつするか?は人それぞれですが、サッサと答え合わせをして、良くも悪くもまずは全力で自分自身をねぎらって、いたわってあげるのがお勧めです!
おわりに
試験前日・当日のことはあまり考えずに後回しになることも多いと思います。
実際にどうしていたかという情報もあまり多くありません。
こちらの記事が少しでも参考になれば非常に嬉しいです。
もちろん、資格学校や通信教育の先生方のアドバイスもあるかと思いますので、そちらをしっかりと守りつつ、前日・当日の準備を進めていけたらいいですね。
勉強自体に気合を入れるのはもちろんのこと、試験を見据えた対策も万全に行い、全力で試験に臨めるよう準備していきましょう!