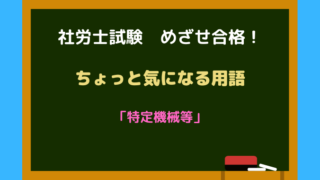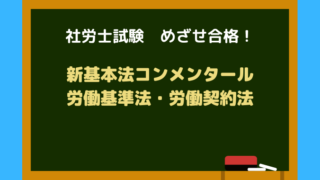特定社労士になるため 合格点ピタリ賞・ギリギリ通過した男の受験記録
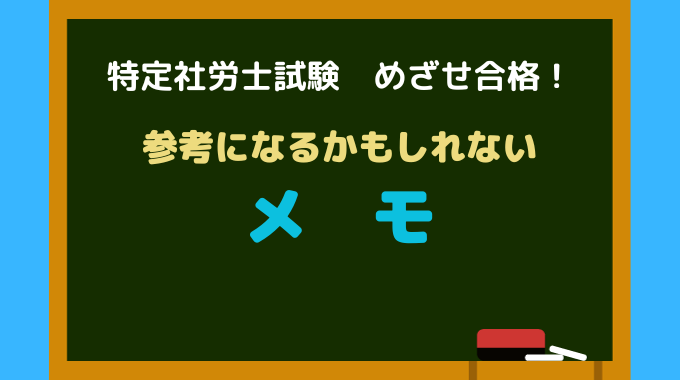
「転職に役立つかも」という不純な動機で始めた特定社労士の受験記録です。
特定社労士の試験を受けてみようかなという方の参考になれば嬉しいです。
序章
私は「転職に役立つかもしれない」、「アピールポイントが増えるかもしれない」という不純な動機で特定社労士への挑戦を始めた、どうしようもないタイプです。
その経緯は以下にまとめてあります。よかったら読んでみてください、かわいそうにと笑ってあげてください(笑)
社労士事務所はブラック!? 社労士事務所への転職前に知っておいてほしいコト
特定社労士の試験、正確な名前は「紛争解決手続代理業務試験」と言います。
これを取得すると、労働紛争解決のための手続きを代理して行うことができるのです!(そのままじゃん!)
社労士として登録していないと受験すら出来ないため、マニアックな試験とも言えますね。私も当初は全く興味なく、受験したのは社労士試験に合格してから4~5年後です。
幸いにも1回目の受験において合格点ピッタリでなんとか通過したものの、相変わらず無駄の多いことを色々とやっていましたので、これから受験を考えている方のお役に立てれば幸いでございます。
そもそも受験する人があまりいないとは思いますが(笑)
ちなみに私が受験したのはR3年なので、その時点での経験談であり、今はもう仕組みも変わっているかもしれないので、ご注意ください!
ではでは、紛争解決ナントカ試験へレッツらゴー!
第1章 e-ラーニング
特定社労士への道のりは毎年9月から始まり、11・12月までの約4か月の中で大きく4段階に分かれています。
- e-ラーニングによる研修受講
- グループ研修
- 弁護士によるゼミナール
- 試験
の4段階。
この最初に行われる「e-ラーニング」がなかなかのクセ者です。
約1か月弱の期間で30時間ほどの講義を全て見なければいけません。スピード調整などもできないため、土日がメインになってしまうと週末は結構なボリュームをこなさなければいけない💦
憲法、民法の講義もあれば、メインとなってくる労働関係の講義も盛り沢山で、あとで見ようなどと先送りにしてしまうと9月下旬には悲惨な生活を送ることになります(笑)
もちろん全ての講義を視聴したかはしっかりとチェックされているから、「はい、全部見ました~」などと口頭報告をすれば済むという話でもなく、地道に視聴するしかありません。
このe-ラーニング、後々に気づいたことだけれど講師として登場してくる弁護士、学者先生はかなり著名な方ばかりでビックらポンでございます。
しかーし、そんな著名な先生方の講義も受ける側のレベルが低ければ宝の持ち腐れ、豚に真珠状態となる。ハイ、もちろん私は豚ちゃんサイドでございます。
私にとっては、いくぶん?かなり?相当?レベルが高すぎる講義であったため、「やべぇ、研修に手を出してしまったのでは・・」、「この後に実施されるグループ研修とかついていけないっしょ」という思いを抱きつつ、講義動画を視聴していました。いや、講義動画を再生していた・・・。
こんな状態で受講したので講義動画がどれだけ勉強になったか、有意義であったかを語ることは私には出来ません。今思えばもったいないことをしたなぁと思う所もありますが、残念ながら講義内容はほとんど頭に残っていない。
第2章 グループ研修
e-ラーニングが終われば、いよいよグループ研修です。
私が受講した時は10月の中盤から後半にかけて、3週連続で土曜日に実施されました。
そもそも昔からグループを作っての研修があまり得意じゃない。これまでも会社の研修などで色々なセミナーを受けさせられたけれど、最近はグループ討議みたいのを必ずやらされるから本当にイヤでございます。
「近くにいる人でグループ作る」→「軽く自己紹介して、意見交換」→「発表」というお決まりのパターン。
これが、ホント苦手。
何だか研修によっては、無理やりこのグループ発表を入れてきているなぁと感じることありません??この研修には必要ないだろ!と。これをやることこそが「ザ・研修」みたいな風潮を感じているぜいぃ。
そもそも特定社労士にずっと手を出さなかった理由の1つがこのグループ研修でもあったから、本当に受けたくないなぁと。
さて、実際にどんなグループだったのか。
私のグループは受講者が9人。そこに既に特定社労士の資格を取得している先輩がリーダーとして加わり、合計10名のグループでした。
10人のうち開業社労士が5人。勤務社労士が3人。オレと残りの1名は登録しているのみ。意外と開業している人って多いのだなと実感。どれくらい稼いでいるのかなというのが気になりますが、それは最後まで分からなかったです(笑)
このグループ研修では労働問題の事例が幾つか与えられ、それについてココが良い悪い、こんな判例があるなどの議論を行います。ひたすら議論するのがメインの研修。そして、最終的にはレポート作成のために課題用として準備された事案についての「あっせん申請書」と「答弁書」という2つのレポートをグループとして提出しなければいけない。
「あっせん申請書」とは【会社にこんな扱いされたので、その対価を要求します!】という労働者側の怒りのレポート。「答弁書」というのは、【従業員がこんなこと言ってますけれど、そんなことありません。私たちはちゃんと対応しています!】という会社側のレポート。
非常に簡単に言うとそういう内容です。
これらを3週間でこなしていくので、結構忙しい。
だからこそ、リーダーとして加わっている先輩社労士の仕切りも大切です。
しかし、、、私のグループに割り当てられたリーダーはなかなかのクセ者でした。「俺はオブザーバーみたいなもんだから」、「俺に聞くなよー、ちゃんと調べて!」、「議論はどうやって進めていくの?」、「それでいいのかなぁ」といった発言を連発してきます。
研修会場ではいくつかのグループが同時に議論をしているけれど、他のグループのリーダーは「こういう判例がありますから、参考になりますよね!」、「ちょっとここの条文を読んでみてください」、「こういう考え方もありますよ」といったアドバイスをしているのが聞こえてきます。
はぁ、ハズレだ。完全に。この思いは今でも変わりません。最後までハズレでした。
でも、グループ内の研修受講者は本当にいい人ばかり。グループ研修はイヤだなと思っていたけれど、このメンバーと学習できたことは本当に良かったと思っています。
これくらい時間を共にして、仲を深められるのであればグループ研修も意義があるよなーと感じました。
一般的によく行われている、たった1回の研修で、何度もグループ変えて、意見交換・発表するというあの儀式はやはり必要ないのでは?という思いは変わりません。
第3章 課題レポートの進め方
グループ研修の集大成としては「あっせん申請書」と「答弁書」の提出が求められます。
記憶が定かではありませんが、この2つのレポートをグループ研修最終日には提出しないといけなかったはずです。つまり、約2週間で作り上げないといけないということ。
この2つのレポートは11月下旬に実施される弁護士を交えたゼミナールと呼ばれる講義で使用されます。そこで配布もされるし、弁護士先生の目にも入るため、いい加減なものを出すわけにもいかない!!
でも、時間もない!だから結構タイヘンです。
ちなみにこの「あっせん申請書」と「答弁書」はそれぞれ全く違う案件について作成されるので、1つの事案の中でそれぞれの立場から作成するというわけではありません。
この課題をどのように進めていくのかもグループで異なるようです。
ちなみに私のグループでは、クセ者リーダーからありがたいアドバイス。「課題の進め方も話し合って決めてなー」と一言。自分はこうだったとか、こうした方がいいよというアドバイスなどは一切ナシ。アドバイスがありがたすぎて、泣けてきます。
まさかこれで社労士会連合会から報酬とか貰っているんですか??こっちも会費やら受講料を払っているんですけど・・・。と今更ながらグチっておく!!
結局、私のグループは「あっせん申請書」と「答弁書」をつくるグループの2つに完全に分かれて作業することに。だから、自分が作成する文書ではない方の課題にはほぼ関わらず。
本当は両方の課題に関わらないといけないというのは感じつつ、みんなで話し合い、そんな時間はナイ!!という結論になりました。
具体的には担当することになった課題について、各自が申請書あるいは答弁書を書き、それを合体させた後で、「これも入れよう」「あそこは削ろう」など、議論をして仕上げていきました。
グループ研修の中では課題の文書を書く時間も、議論をしている時間もないから、それは全て宿題。自宅での作業。この期間はメールで何度もやり取りしたり、オンラインでの話し合いもしたものです。懐かしい。
他のグループがどうやって進めていたのかは全く分からなくて、もっと効率的・効果的な方法もあったのかもしれませんが、とにかくこの作業は大変でした。
でも、とりまとめをしてくれたメンバーや議論の中心になってくれたメンバーの皆さんに本当に感謝。グループのメンバーには恵まれたことに改めて感謝。
第4章 空白の1か月
グループ研修は10月で終わり、課題も無事に提出すると、次は弁護士先生による「ゼミナール」と呼ばれる研修が11月下旬に行われることとなります。
そのゼミナールが行われるまで約1か月間は空白期間。
そしてゼミナールの終了後には即、試験となるため、この1か月間は試験に向けた勉強を行うための超重要期間です。
受験生以外は目にしたこともないと思いますが、特定社労士の試験にも過去問集が販売されています。
それがコチラ↓
コチラというか、これしかないのです!(笑)
だから、特定社労士の受験生はほとんどの人が購入しているのかなぁと推測。
もちろん私も1か月はこの書籍をメインに勉強です。ひたすら回す。
合格率が50%前後とはいえども、勉強をすればするほど厄介な試験だということをヒシヒシと感じます。
色々と覚えなければいけないことが多いのはもちろんだけれど、正解があるような無いような試験。
いかに説得力のある主張が出来るか、そうした文章を書けるかが問われる試験。
と感じたのは試験が終了した後💦
この空白の勉強期間も「暗記に偏りすぎてしまった。」と今は反省しています。
正直なところ何をどう勉強していいのか悩ましかった。
過去問題集をやっていても「え!?この事例で労働者側に立つべきなの?」、「えぇー、この問題は社労士として引き受けることが可能なの!?」というように、そもそも自分の知識・感情から導いた答えとは異なる模範解答も多いわけで・・・・。
ところで、この特定社労士の試験にも様々な講座が開講されています。
数は多くないですけどね。
LECの講座、著名な特定社労士先生の講座、社労士協同組合が提供している講座などなど。
受ける・受けない、どの講座を選ぶかなどは様々だったけれど、私は社労士協同組合が提供している講座を受講した。
そのために一時的に協同組合にも加入しました(笑)
講座の感想としては、勉強になる点は多かったけれど、受講したから頭もスッキリ!というわけにはいかなかったかなと。
とにかく何だか頭がモヤモヤしたまま、過去問題集に書いてあることが書けるようになるかという勉強に終始していました。
第4章外伝 書籍あれこれ
そもそも書籍を買うのが好きな私は、特定社労士試験でも無駄に書籍を買いまくりです。
参考になるかは分かりませんが、せっかくなのでご紹介!
何でこんなに買ったの!?!?
今から思うと本当に謎です。
たぶん何をどう勉強したらよいのか分からなすぎて、何かにすがりたかったのかもしれない・・・。
本当にそんなに買ったんかい!?と言われてしまいそうな量。

激しく後悔しています(笑)
全ての書籍をしっかりと読んだわけもなく、ところどころをつまんで読んだだけ。
研修の開始時にお勧め書籍として紹介されたものもあるけれど、結果的にはほぼ必要なかった。
そんな中でもこれは良かったなと思うのは、菅野先生の労働法くらいかもしれない。
緑色のぶ厚い本です。
ちなみにこの研修でグループの人に聞いたところによると、この本は社労士として活躍していくなら必読の本と言われているそうです。
確かに試験勉強中もかなり役に立ちました。
でも、個人的には、荒木先生の労働法の方が読みやすかったです。
読んだのは試験終了後でしたが。
そのほかの書籍は参考になる点ももちろんありましたが、さすがに買う必要はないかなーというのが正直な感想。
あっ、でも、特定社労士試験の勉強をしている当時は読んでおらず、その後に読んだ本の中で「実は読んでおいた方がよかったんじゃない!?」と思う書籍が1冊あるのですよ!
それがコチラ
11月に受講することになる、弁護士先生によるゼミナールという講義で、法的三段論法、要件事実、あてはめ、射程といった用語がポンポンと出てきます。
法律を勉強している人にとっては当たり前の言葉なのかもしれないけれど、私にとっては何のことを言っているのかサッパリ分からず。
講義の中で説明されるにしても、私の頭では残念ながら理解が追いつかない。
そういった基本的な用語、考え方を解説してくれているのが、この「キヨミズ准教授の方学入門」という書籍。
もし、特定社労士の勉強をしている中で「スッキリしないなー」と感じている方がいたら、この1冊を読んでみるのもいいと思います。
そんなに分量もないから、すぐに読み終わりますよ。
第5章 ゼミナール開始
11月下旬の2日間+12月上旬の半日、弁護士によるゼミナールが開催されます。
ゼミナールのメンバーは、弁護士1名に対して受講者は6個くらいのグループ研修メンバー総勢約60名~70名です。
座席はグループで固まって座るように指示されます。
それから、事前に提出している課題文書が他のグループの分も含めて配布されます。
ゼミナールは全3回で、講師の弁護士は毎回変わります。ただ、私の場合は1回目と3回目の講師は同じ人でした。
このゼミナール、受講する前から噂には聞いていたのですが、噂通りに1人1人あてられます。60人も参加していて、そんなに当てられるの!?と思っていたけど、それが本当にあてられるんですよ・・・。
マイクがまわされてくるから、適当にモゴモゴ言っておこうという作戦も通用しないんですよ・・・。
この事案で問題となる点は?参考になる判例は?他に勘案しないといけない点は?などなど、様々な質問が飛んでくるから、マジで課題となった案件はしっかりと勉強しておくことをオススメします!
他にはこんな噂もありました。「弁護士先生の追及が厳しくて、ピリピリした講義である」「答えられないことを厳しく指摘され、泣いてしまう受講生がいた」など。
そんなゼミナール勘弁してくれーと思っていたけれど、幸い私が受けたゼミナールの先生は本当にいい先生でした!
私が当てられた時の質問も何て答えたらいいか分からなくて、「〇〇だと思うのですが、すみません、全く分かりません」と答えても普通に受け止めてもらえました!
しかーし、これも噂レベルですが、私が受けていた時期の別のゼミナールでは非常に厳しい先生もいたらしい。泣かされてしまった人もいたらしい。。。
ちなみにゼミナールでは1回当たったら終わりではないというのもポイント。
色々な質問がポンポン、席順にあてられていくので1コマで2回くらいあてられることもある!!
それから、これも今思えばっていう話なんですが、ゼミナールでの弁護士先生の話はしっかりと聞くべきです。
弁護士はどういう点を気にして、何を大切にしているのかということを勉強するためにも非常に貴重な機会ですよ!
なぜなら、試験を採点してくれるのは弁護士先生ですから。
だから、弁護士先生の話をよりよく理解するためにも課題の内容はもちろんのこと、先ほども記載した法的三段論法、あてはめといった用語?手法?については少しだけでも調べておくといいと思います!
いや、調べておくべし!!
第6章 試験当日
試験はゼミナール最終日の午後、つまりゼミナール終了後に昼食を経て受験します。
午後に開催っていうのがスゴイ。ゼミナールで学んだことを噛みしめて、復習して、試験に挑むという時間ナシです。
私がいた東京の会場ではお昼休みに建物の会議室が解放されるのですが、人、ひと、ヒトで溢れかえってカオスな状態。
こんなに受験者がいるのかと改めてビックリ。
それも想定して慌てずに試験開始を迎えるべしです!可能であれば、解放される会議室の座席は急いで確保!!
試験時間は2時間。
慣れないボールペンでひたすら書く書く書く!
私が受けているとき、何を書こう、どうやって攻めていこうと考えていたら時間はあっという間に過ぎていき、最後に慌てて書きなぐった記憶しかありません。
ボールペンだから一度書いてしまったら、なかなか書き直せないのは非常に厄介だけれど、恐れずに書いていかないと、どんどん時間が無くなります。
もう1つ、試験前に私のグループで盛り上がっていたのは「どのボールペン使うか問題」。
解答用紙の行間が結構狭いらしいからペン先が細い方が良い、たくさん書いてあるように見せるためには太めの方が良いのではないか、などなど。
でも、実際に受けてみたら行間が細いといったことは全くなく、わざわざペン先が細いものを用意する必要はないと感じました。細い方が書きやすいという人もいるかと思いますが、そうでない場合はそこそこの太さがあってもOK!
私、実は行間が細いという噂を警戒して0.28mmのボールペンで臨んだのです。でも、書きやすさで言えば0.5~0.7mmが好み。この太さのボールペンでも全く問題ないっす。
無理せずにお好みのボールペンでチャレンジOK!!
おわりに
特定社労士の試験は合格率50%前後で、比較的合格しやすい試験ではあります。
でも、そこまでの勉強は結構しんどい!
それはどんな資格でも、どんなテストでも同じですね。
いつかは特定社労士への道を!と考えている方へ少しでも参考になれば幸いです。
合格基準点ピッタリで合格したワタルでした。てへっ。