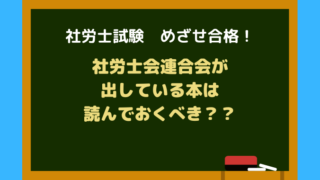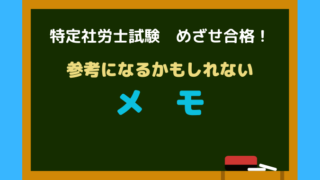社労士試験 ちょっと気になる用語「特定機械等」
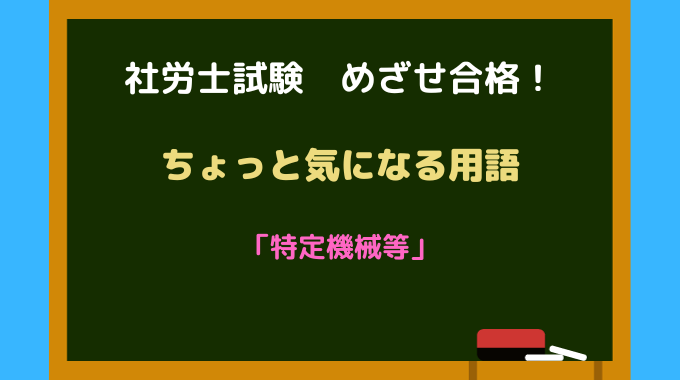
試験に出るから覚えるけど、そもそも何なのかなぁ?と思うモノありますよね。
はじめに
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社労士試験の勉強をしていると、テキストには出てくるから覚えるけど、深追いはしないっていう用語・単語がありますよね。
とりあえず覚えたけれど「いったい何なんだろう?」と一瞬は気になってしまいます。
とはいっても、改めて自分で調べるほどのものではありません。
そこであえて調べてみました(笑)
今回のお題ですが、労働安全衛生法(以下、安衛法という)より「特定機械等」です。
特定機械等 とは?
「特定機械等」は安衛法の第37条に登場します。
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制
(製造の許可)
第三十七条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
製造する時に「都道府県労働局長の許可」が必要になるのが特定機械等です。
特定機械等はまず「別表第一」に掲げるものとされていますので、安衛法の別表を確認すると、以下の記載があります。
安衛法 別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
さらに安衛法第37条では、別表第一に掲げるもので「政令で定めるもの」という要件も記載されています。
そこで安衛法の政令(施行令)を確認してみます。
労働安全衛生法施行令
(特定機械等)
第十二条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
三 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク
六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)
八 ゴンドラ
2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容器は、第一種圧力容器とする。
別表第一に掲げれている特定機械等について、荷重などさらに細かく記載がされていますね。
それでは1つずつ見ていきます。
ボイラー
ボイラーとはboil「~を沸かす」という英単語にも表れているとおり、液体を温めていくことで温水や水蒸気を作る装置のことです。
より具体的には、電気、高温ガスまたは火気により、水や液体で水蒸気を作り、そこで発生した温水や蒸気を外部へ供給するという機械になります。
逆に非常に簡単な表現をすれば、お湯を沸かすことで発生する熱せられた水、発生した蒸気を有効利用するための装置と言えます。
第一種圧力容器
圧力容器とは、内部や外部からの圧力に耐えられるように設計された密封容器、つまり容器内に圧力をかけるための容器です。
第一種があるということは、第二種圧力容器というのもあり、その違いは
・圧力により、容器内で新たに気体を発生させることが出来る「第一種圧力容器」
・圧力により、容器内で気体を発生させることは出来ないのが「第二種圧力容器」
という違いがあります。
当然、第一種圧力容器の方が危険度が大きく、規制も厳しくなります。
圧力をかけることで何が出来るのかについてですが、例えば、蒸気を閉じ込めることで通常100℃にまでしか上がらないお湯の温度を120℃まで上昇させたりすることができます。
ちなみに、ボイラーと圧力容器はどちらも水・蒸気を扱いますが違いとしては、
・ボイラー:蒸気や温水を他へ供給するためのもの
・圧力容器:他から蒸気等を受け入れ可能。また、自ら蒸気を発生させ加熱等を行い、高温の流体を蓄積するためのもの
という違いがあります。ボイラーは他へ発出させるもの、圧力容器は受け入れるためのものという見方もできそうですね!
クレーン
クレーンとは、荷物を動力を用いてつり上げ、つり上げたものを水平に運搬することを目的とした機械です。
クレーンには様々な種類がありますが、イメージしやすいのは「天井クレーン」でしょうか。工場の天井両側に設置されたレールのようなものに沿って物をつりあげ、移動させることが可能な装置です。
もっと分かりやすいのは「クレーンゲーム」ですかね。非常に簡単に言えば、クレーンゲームが巨大化したものとイメージしておけば分かりやすいと思います。
スタッカークレーン
安衛法施行令のクレーンの定義には「スタッカークレーン」という名称も出てきます。
スタッカークレーンは天井クレーンの一種で、自動倉庫などで重宝されています。具体的には、
・各ラック(棚)間を移動することができる走行機能
・各ラックの上下方へアクセスする昇降機能
・荷物をラックへ格納,搬出するフォーク機能
の各機能を備えたものになります。
私の個人的なイメージですが、自動販売機でも番号を押すとその商品の前まで受け皿が移動して、商品を受け取ってくれる機械ありますよね。それと似ているのかなと思います。
移動式クレーン
厚生労働省のHPをさまよっていたところ、移動式クレーンとは、「動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの」という定義がありました。
クレーンには大きく3タイプあります。
●トラッククレーン
トラックにクレーン装置がつけられているもので、トラックの運転席とクレーンの運転席が分かれているもの
●ホイールクレーン
トラックの運転席とクレーンの運転席が同じもの。(分かれていない)
●クローラクレーン
戦車のタイヤのような走行機能にクレーン機能がついているもの
デリック
デリックはクレーンと同じで荷物を「つり上げる」ことを目的とした機械です。
クレーンとデリックの大きな違いは、
・クレーン:荷物を吊り上げ、水平移動させることが目的
・デリック:荷物を吊り上げることが目的(水平移動は出来なくてもよい)
そのため、デリックによって積み上げを行う際には、荷物を積んでいるトラックなどがデリックの可動範囲まで移動しなければなりません。
そうした特徴もあり、現在はクレーン、移動式クレーンが主流になってきていますが、港湾などではいまもデリックが活用されています。
エレベーター
積載量1トン以上のエレベーターが特定機械等に含まれます。
これについてはあまり詳しい解説が見つけられなかったのですが、1トン以上となると業務用エレベーターが対象になると思われます。
ちなみに積載量1トン以上のエレベーターには性能検査と、少なくとも月1回の「定期自主検査」が必要です。検査してくれる人は以下のとおりです。
性能検査:労働基準監督署長、または厚生労働大臣の登録を受けた「登録性能検査機関」
定期自主検査:厚生労働大臣の登録を受けた「登録性能検査機関」※製造会社を含む
建設用リフト
工事資材を運ぶために、工事現場に設置されるのが建設用リフトです。工事期間だけ使用する仮設の機械なので、数ヶ月から1年以上続くよう現場で重宝されます。
建設用リフトの最大積載荷重は1トンほどですが、何度も往復させる必要がある場合にはクレーンを使うよりも効率がよくなります。
またクレーンと比べて天候に左右されづらい、操作が簡単といった利点もあります。
ゴンドラ
ゴンドラは、使用目的や設置場所によって様々なタイプがありますが、私のイメージとしては「屋上から吊るされて窓の清掃をしてくださっている方」たちが使用しているアレです。
こちらも詳しい説明がはっきりと見つけられませんでしたが、比較的イメージしやすい機械かなと思います。
おわりに
今回は特定機械等について調べてみました。
ボイラー、圧力容器、デリックなどは名前だけ覚えて一体何なんだろうか?とずっと思っていたのですが、少しスッキリです。
試験には出ない内容ですが、少しでも暗記のお供になってくれたら嬉しいです。