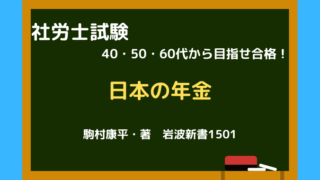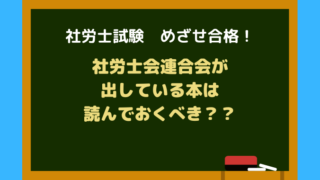社労士試験 ちょっと気になる用語「曲馬又は軽業」
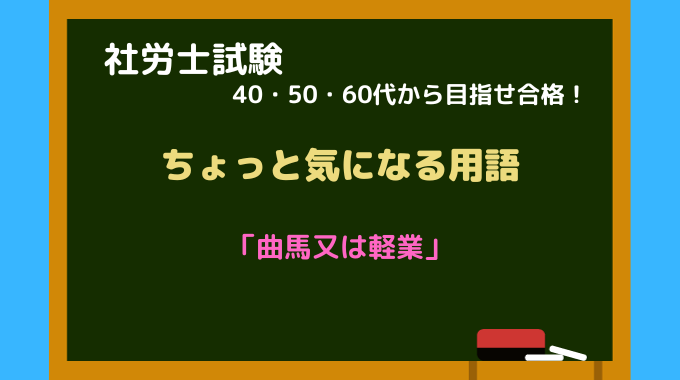
試験にはほぼほぼ出ないけれど、テキストには出てくる単語・用語ありますよね。
今回は「曲馬又は軽業」です。どこに出てくる用語か分かりますか?
はじめに
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社労士試験の勉強をしていると、テキストには出てくるけれど深追いする必要のない単語などが出てきますよね!
でも、そうした単語は「いったい何なんだろう?」と一瞬は気になってしまいます。
とはいっても、改めて自分で調べるほどのものではありません。
そこであえて調べてみました(笑)
今回もTACの市販テキストをペラペラと捲っておりましたら、気になる用語がありました。
今回のお題ですが、労基法より「曲馬又は軽業」です。
年少者の業務制限 労基法56条
「曲馬又は軽業」という単語ですが、年少者に就かせてはいけない業務として規定されているものの1つになります。
この単語に出会うために、労基法の第6章「年少者」の内容から順に追っていきます。
まずは労基法第56条を確認してみましょう!
第六章 年少者
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
ここで「児童」という単語が出てきました!
労基法では「年少者」と「児童」が以下のように使い分けられています。
- 年少者:満18歳に満たない者
- 児童 :満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者
そして、56条1項では児童を使用してはならないとされています。
しかしながら、56条2項では【児童を修学時間外なら使用してもいい場合があります。でも「別表1の1~5号」の業務に就かせてはいけない】とされています。
別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
てっきりここに「曲馬又は軽業」が出てくるのかと思ったら、そうではないようです。
労基法62条
さらに労基法を読み進めてみますと、第62条には年少者の就業制限について規制があります。
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
細かいことは厚生労働省令で定めるとなっています。
この厚生労働省令が「年少者労働基準規則」というものになります。
最初に気になった「曲馬又は軽業」という単語もこの規則に登場します!
年少者労働基準規則
まずはこの規則の第8条を確認します。
第8条は、労基法62条で「厚生労働省令で定める」とされている「危険有害業務」が具体的に書かれています。
ちょっと量がありますが、滅多に見ることもありませんのでドドーンと記載します。
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
二 ボイラーの溶接の業務
三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
五 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
七 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
八 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
九 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
十 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
十三 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十四 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十五 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
十六 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
十七 軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
十八 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十九 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
二十 削除
二十一 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
二十二 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
二十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
二十五 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
二十六 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
二十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
二十八 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
二十九 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
三十 削除
三十一 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
三十二 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
三十三 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
三十五 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八 異常気圧下における業務
三十九 さく岩機、鋲びよう打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
四十二 焼却、清掃又はと殺の業務
四十三 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
四十四 酒席に侍する業務
四十五 特殊の遊興的接客業における業務
四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
ここにも危険そうな業務がズラっと記載されていますが、やはりよくよく見てみると「曲馬又は軽業」というのは記載がありませんね。
つづけて年少者労働基準規則の第9条を確認します!
(児童の就業禁止の業務の範囲)
第九条 所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第五十六条第二項の規定による許可をしてはならない。
一 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
二 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
三 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
四 エレベーターの運転の業務
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
やっと「曲馬又は軽業」という文言にたどり着くことが出来ました!!
第9条の本文に「前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務」とあるように、先ほどズラっと記載した業務(前条1~46まで)に加えて、児童に対しては「曲馬又は軽業」など1~5号の業務もダメですよ!という規定になっています。
公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
さて、やっと目的の単語が登場したわけですが、曲馬・軽業については、インターネットで検索した内容を見てみますと、
曲馬:馬の曲乗りや、馬に曲芸をさせる見世物。もともとは馬術の余興として行われたものをいうが、武術としての乗馬技術が芸能化したものともいえる。興行の始まりは享保(きょうほう)(1716~1736)以後のことといわれており、日本では昭和初期までサーカスを曲馬団とよんでいた。
軽業:綱渡り・はしご乗り・玉乗りなどの曲芸。また、その見世物。アクロバット。
とされています。
加えて、「令和3年版 労働基準法 下 厚生労働省労働基準局編」によると、【公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務】について、以下の記載があります。
公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務について、労働省労働基準局長と厚生省児童局長との打合わせの結果、撞木上における曲芸、演技者の肩を利用する技芸、両脚を利用する曲芸、自転車曲乗り、曲馬に関する技芸、アクロバット、オートバイ又は自転車の特殊な曲乗り等はその範囲に入るものとし、綱渡りのうち、高さ2メートル未満で、特殊の器具を使用せず、かつ、普通の姿勢で綱渡りする場合及び集団をもって表現するピラミッド曲芸のうち、高さ2メートル未満で、かつ、他人を自分の肩にのせず他人の肩の上に立つ場合は、これを一の業務の範囲に入らないものとする方針を定めている。
令和3年版 労働基準法 下 厚生労働省労働基準局編
結構細かく決められていますね!
前半の「その範囲に入るもの」が禁止事項、後半の「業務の範囲に入らないもの」が児童の業務として認められているということになります。
なお、こちらの書籍によりますと、「ゴルフ場におけるキャディの業務」は年少者労働基準規則第9条第3号の「娯楽上における業務」に該当しない(児童がやってもよい)という解釈も示されていました。
おわりに
今回も社労士試験の中で、気になる・聞いたことある・でも深追いはしない用語について簡単にではありますが調べてみました。
さっと読んだら、さっさと次に進みましょう!
他にも気になる用語などありましたら、ぜひ教えてください。喜んで調べさせていただきます。