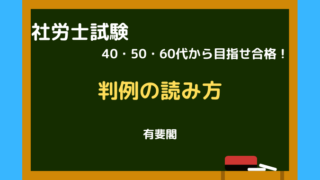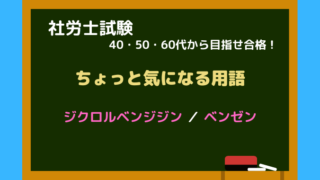社労士試験 ちょっと気になる用語「黄りんマッチ」と「ベンジジン」
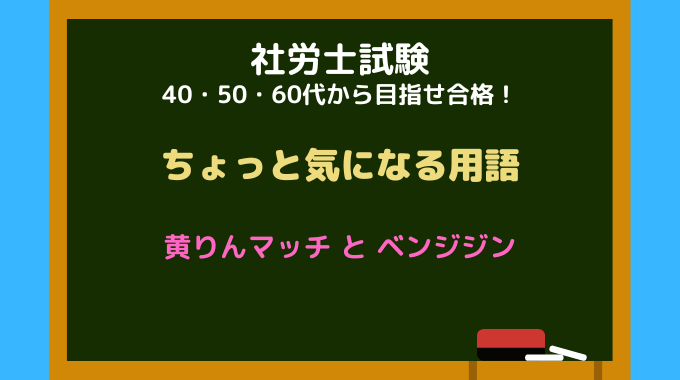
試験には出ないけれど、テキストには出てくる単語・用語ありますよね。
はじめに
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社労士試験の勉強をしていると、テキストには出てくるけれど深追いする必要のない単語などが出てきますよね!
でも、そうした単語は「いったい何なんだろう?」と一瞬は気になってしまいます。
とはいっても、改めて自分で調べるほどのものではありません。
そこであえて調べてみました(笑)
今回のお題は「みんなが欲しかった!社労士の教科書」をパラパラとめくっていたら目にとまりました「黄りんマッチ」と「ベンジジン」です。
黄りんマッチ
この「黄りんマッチ」という単語、どの試験科目に出てくる単語でしょうか?
正解は「労働安全衛生法」の第55条になります。
(製造等の禁止)
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
危険有害物として、製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。
では、この「黄りんマッチ」とは一体何なのでしょうか?
火をつけるためのマッチではありますが、わざわざ法律で使用等が禁止されているくらいですので、ヤバい奴なのは間違いなさそうです。
黄りんマッチとは
1830年代にフランス人のシャルル・ソーリアという人によって発明されたマッチです。
それまで使用されていたマッチは、火をつけようとしても発火性が悪かったのですが、マッチの先端部分(火が付く部分)に「黄りん」を使用して、発火性を高めたものが「黄りんマッチ」です。
これだけ聞くと使い勝手の良いマッチに思えますが、大きな問題が2つありました。
黄りんマッチの問題点
1:発火性が良すぎる
黄りんマッチはどこにこすりつけても発火するほど発火性の良いものでした。そのため、室温がちょっと上がると発火してしまったり、ちょっとどこかに擦ってしまっても発火してしまうという、便利だけれども危険なものでした。
そもそも、この「黄りん」というものはロウ状の固体らしいのですが、直接空気に触れるだけでも発火するらしく、水に入れて保存しているそうです。
2:毒性が強い
人体にとっては有害な物質で吸引してしまうと、鼻、喉、肺が激しく刺激され、最悪の場合は死にいたることもあるようです。
また、黄りんは皮膚に触れてしまっただけでも激しい火傷を起こすほど刺激が強いそうです。
黄りんマッチのその後
こうした危険性、人体への悪影響が認識され、便利さはあったものの黄りんマッチは次第に使用されなくなり、使用を禁止する国が増えていきました。
日本では1921年に製造が禁止されました。
ベンジジン
ベンジジンも先ほどの黄りんマッチと同じく、労働安全衛生法の第55条に登場します。
ベンジジンの化学式は皆さんご存じのとおり「C12H12N2」ですよね!(笑)
このベンジジンですが、灰色っぽい粉末(砂や砂糖のような形状)で、革製品の染料に使用されていたそうです。
しかし、発がん性が高いことが判明し(特に膀胱癌)、皮膚からも簡単に吸収されてしまうため、日本では1972年に製造等が禁止されました。
おわりに
今回は社労士試験の中で、気になる・聞いたことある・でも深追いはしない用語について調べてみました。
そういうものなのかと思ったら、さっさと次に進みましょう!
他にも気になる用語などありましたら、ぜひ教えてください。喜んで調べさせていただきます。