社労士試験 独学・サブテキストは「みんなが欲しかった!社労士の教科書」
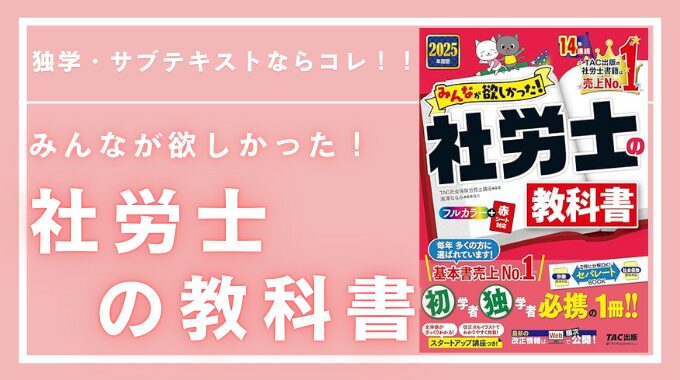
来年度の社労士試験に向けたテキストが販売され始めましたね。
独学でチャレンジしようとしている方にとっては貴重なテキストです。
学校に通っている方、通信教育を受講されている方にとってはサブテキストとして手元に1冊はあってもいいのかなと。
基本テキストも何種類か販売されていますが、その中でもオススメの1冊を紹介します。
はじめに
勉強するにあたって、テキストや問題集を何種類も手広くやるのは、基本的にはNGだと思っています。
それならば1冊を徹底的に、何回も何回もボロボロになるまでやりましょう!!
という話をよく聞きますよね。
もちろん正しいことだと思います。
私も過去には色々なテキスト、問題集を無駄に買い漁っていた時期がありました。
そしてほとんど使いこなせず💦
しかし、私の経験を踏まえてお話しするならば、社労士試験については市販のテキストを1冊は持っていても良いのではないかと思っています。
その理由などを含めて、お勧めの1冊を紹介しちゃいます!
書籍の概要
今回ご紹介する書籍はこちらです。
みんなが欲しかった!社労士の教科書
こちらは毎年10月にTAC出版さんから発売される、社労士試験のためのテキストです。
まぁ、書籍の名前のとおりなのですが(笑)
ちなみに同じタイミングで発売される問題集が↓です。
この2冊がセットになって、社労士試験の基礎学習と位置付けられています。
独学の方の場合はこちらをセットで購入して、何度も何度もテキスト読む→問題を解くを繰り返していくのがオススメです。
今回は「社労士の教科書」の紹介になりますので、その概要・特徴を紹介します。
おすすめポイント
オールカラーで見やすい
市販されている社労士のテキストは最近でこそオールカラーのものが増えてきていますが、私の記憶ではこちらのテキストがかなり早い時期からオールカラーを導入されていたかなと思います。
資格学校のテキストや通信教育で使用されているテキストも2色刷りなどが主流になってきていますが、オールカラーはまだあまりないですよね。
オールカラーでありがたいのは「図や表などの色分け」がハッキリしていて、理解しやすいことにあります。
社労士試験は暗記しなければならないことが山のようにありますが、その根底にあるのは「理解」です。
そのためにも見やすさ・分かりやすさというのは非常に重要ですよね!
コンパクトで持ち運びやすい
市販されているテキストの多くがいわゆる「A5判」(タテ210mm×ヨコ148mm)となっており、非常に持ち運びやすいです。
コチラのテキストは「労働保険」と「社会保険」の2分冊になっているのもありがたい。
これが1冊だと持ち歩くのはかなり大変ですからね💦
最新の情報をいちはやく
通学や通信教育ですと、科目ごとにテキストを貰えるスケジュールなどが決まっているので、その配布された順番に進めていくことになります。
しかし、こちらのテキストでは購入時点で全ての科目のテキストを入手したことになりますので、スケジュールの立て方が思いのままです。
始めて学習する方は順番に前から進めていくことにはなると思いますが、既に学習経験のある方にとっては、苦手な科目からやろう、社会保険からやろう、というように自由にアプローチすることが可能になります。
もちろんテキストが発売された後の追補等にも対応していますので安心です。
2分冊だからこそのメリット
「労働保険」と「社会保険」の2分冊になっているということは先ほど紹介したとおりですが、そのメリットにお気づきでしょうか。
それは「あれ?××の場合はどうだっけ??」という疑問解消に非常に有用だからです。
何を言っているんだと思っている方も多いかと思いますので説明します。
例えば「平均賃金」と「賃金日額」と言われると「あれ?なんだっけ?何が違うんだっけ?」と思ってしまう人も多いのではないでしょうか。
もしこの疑問を解消しようとしたら、労基法のテキストと雇用保険のテキストが必要になります。
学校や通信教育で配布されているテキストは科目別になっていますので、こうした疑問が沸いたときに片方のテキストしか持っていないと「家に帰ってから調べよう」→「結局、忘れてしまい調べない」という流れになることが容易に想像できます。
しかし、こちらの「社労士の教科書」では強制的に2分冊になっていますので、こうした疑問が沸き起こったときには確実にしらべることが可能です。
社会保険でも同じような場面がこれからもたくさん出てきます。
国民年金と厚生年金保険、健康保険と厚生年金保険はそれぞれつながりが強いですから、この3科目についてはテキストを行ったり来たりすることが容易に想像できます。
「社労士の教科書」ではこの3科目も強制的に1冊になっていますので、ページをめくり放題です(笑)
ちょっと重たいという点はありますが、せっかく1冊になっていますのでそのメリットを最大限に活用していきましょう!!
ちょっと気になる点
こちらのテキストは本当にコンパクトかつ分かりやすいのですが、ここが残念だなーと感じる点もすこしあります。
余白はほとんどナシ
基本となるテキストですので、自分が気になった点、勘違いしていた点などあれこれとメモをしたいと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、こちらのテキストは内容の充実とコンパクトさを両立させようという思いが強すぎたのでしょうか、書き込みを行うスペースはほとんどありません。
ガシガシ書き込みたいという方は付箋を使うなど、工夫が必要になります。
紙質は好みが分かれるかも
書き込むスペースがあまり無いということを紹介したばかりですが、それでも細かい余白に書き込みたいときがあります。
しかし、その際もちょっと注意を。
私は紙質のことに詳しくないので正確なことが言えませんが、本テキストの紙質は純粋な紙というよりは、ちょっとツルツルした感じがします。
純粋な紙9割+ビニール1割というのでしょうか、より良い紙質として作られているのかもしれませんが、書き込みを行う際にはほんの少しだけ違和感を感じてしまいます。
もちろん書き込み自体はできるのですが、普通の紙に書く漢字とはちょっと異なりますので、ご注意ください。
オールカラーが故に・・
オールカラーで見やすさ抜群!という紹介をしておりますが、これもちょっとだけ気になる点があります。
勉強しているとどうしても蛍光ペンで線を引きたくなりますよね!
しかし、オールカラーのために線を引いても白黒テキスト、2色刷りのテキストを使用しているときほどは目立ちません。
まぁ、気にならない程度ですが、線を引きまくるって方は要注意です。
実際に使用してみて
私が実際に使用していたときの感想、特にサブテキストとしての利点を幾つかご紹介します。
理解が深まる時がある
通学または通信教育をメインとしている場合、説明を聞き、テキストを読んでも「いまいち意味が分からない」、「説明された内容とテキストの内容が合っていない気がする」といったことありませんか?
そうした時に違うテキストを読んでみると、書いてある内容は大体同じなのになぜかスッと頭の中に入ってくる、理解が深まるという時があります。
私が勉強している時はちょっとした書きぶりの違いであったり、読む順序の違いなど些細なことがキッカケで理解が深まる場合が少なからずありました。
そうした経験もあり、テキストは1冊を集中的に!!というのが王道なのは分かっているものの、サブテキストを用意しておくというのもアリかなと思っています。
気兼ねなく使える
メインのテキストが別にある場合、サブテキストはどのように使っても全く気になりません。
お風呂で読んでいて水没させてしまおうが、持ち歩いてどこかで万が一なくしてしまってもそこまで気になりません。
なぜならサブテキストだからです。
また買えるからです。(もったいないけど)
メインテキストは魂を込めて書き込みをしていく、大切なパートナーです。
メインテキストはボロボロになるまで使い込むべきですが、水没させたり無くしてしまうといったことがあってはなりません。
サブテキスト、あってもいいかも!って思いませんか??
おわりに
今回は「みんなが欲しかった!社労士の教科書」を紹介させていただきました。
記事の内容がサブテキストとして使用する場合を想定したものとなっていますが、もちろん独学メインテキストとしてもお勧めです。
資格学校に通っていた当時も配られたテキストと遜色ないなーと思いながら眺めていましたし、そもそも全ての内容が載っているテキストなどありません!
もし独学でこちらの書籍をメインで使われる場合などは、サブテキストとしてユーキャンから発売されているテキストなどもお勧めです。
私は受験生当時にあまりにも手を広げすぎて反省しているのですが、こちらのユーキャンのテキストを読んで理解が深まった、納得できたということもありました。
いずれにしても「サブテキスト」を眺める、分からない時にめくってみる、スキマ時間用に持ち歩く、などなど気軽に使って少しでも知識の定着に役立てていくのはオススメですよ!











