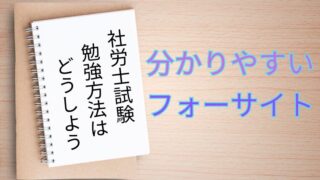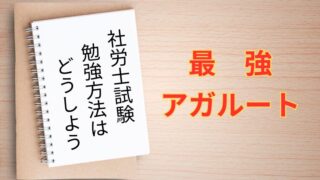忙しくて社労士試験の勉強をする時間が確保しづらい。迷わずスタディングへどうぞ!
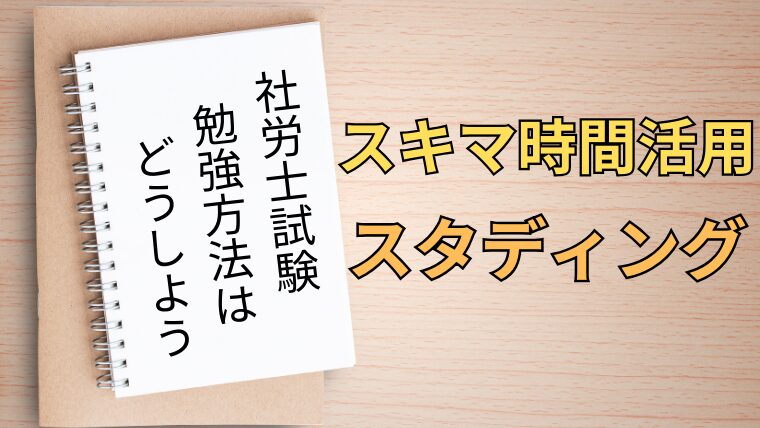
便利な世の中になりました。
携帯だけで資格試験の勉強が出来てしまうのですから。
忙しい中でも社労士試験に合格したい!スキマ時間を徹底活用したい!という方はスタディングでの勉強、いかがでしょう。
費用も抑えられているのは、本当にありがたいですね!
はじめに
社労士試験へのチャレンジを決意した後には勉強方法を決めなければなりません。
お金のかからないのは独学。
でも、理解するのには時間を要する。続ける根性も必要。
通学は強制的に行くことになるから持続力はある。
でも高い。
そうなると、講座を受けられるし、通学ほど高くない通信教育が無難かな。
はい、そう思います!!
私は通信教育をオススメしますが、しかし、その通信教育も種類が豊富にあります。
今回はスキマ時間を有効活用、お財布にもすこぶる優しいスタディングの社会保険労務士講座を紹介します。
忙しくてなかなか勉強の時間が取れない方には本当にオススメです。
おすすめポイント
スタディングのおすすめポイントを一言で表すなら、私は「3K」とお伝えします。
Kakaku Kouritu Katate です。
分かりづらくて、すみません(笑)
価格 効率 片手 です!!
一言で表していないじゃないかというごもっともな批判を浴びつつ、スタディングの良さをお伝えしていきます。
入門講座と合格戦略講座
社労士試験はとにかく範囲が膨大です。
そのためにも「どのように勉強していくか」という作戦を立てることは非常に重要です。
その作戦を立てるためには、社労士試験では何を学ぶのかを知らなければなりません。
スタディングの「入門講座」はそれを把握するのに最適です。
これから学ぶ法律、知識などが日常生活とどのように結びついているのか、これから学ぶ知識がどのように活かされていくのかを学ぶことが出来ます。
私は人事の経験・知識もゼロの段階から社労士の勉強を始めたので、始めたばかりの時は本当に何を言われているのか分かりませんでした。
こうした入門講座を受けておけば、その時の「分からなさすぎるショック」が緩和されただろうなぁと、今では思います。
社労士試験で大事なことの1つは「繰り返すこと」
入門講座で大局を把握して、より細かい点を更に学んでいくという方法は理にかなっていますね!
そしてもう1つ、本格的な勉強を始めていくにあたって活用していきたいのが「合格戦略講座」です。
各科目で何を重点的に勉強していくべきなのか、あまり注力しなくてよい分野はどこなのか、勉強を進めていくうえでの注意点などを把握することができます。
勉強を進めていると「これは出そうだな」、「これは覚えないとな」、「この数字は丸覚えした方がよさそう」、「ここは紛らわしいから狙われそう」と感じることが非常に多いです。
その結果、どうなるかといいますと「結局、全部覚えないとダメそうだ!!!」という結論に至ります。
何でもかんでもすべて覚えることができれば、それに越したことはないのですが、恐らく無理でしょう。
たまに見たこと、読んだことをそのまま絵のように覚えてしまう、一度読んだら忘れないといった能力があると聞きますが、もし本当にそんなことが可能な方がいらっしゃるのであれば、うらやましい限りです。
残念ながら、大抵の方はそうした能力とは無縁ですよね💦
だからこそ取捨選択が必要です。
合格戦略講座では「適切な勉強方法」を分かりやすく指導してくださいますので、忠実に守りながら、効率よく勉強していきましょう。
非常に簡潔で分かりやすいスライド講義
スタディングの講義はスライドとお呼びしてよいのか分かりませんが、分かりやすく簡潔に作成された板書を中心に行われます。
講義を聞く→問題を解くという勉強の流れが構築されているので、受講している方はその流れに従い「聞く」「解く」を繰り返していくだけで、グングンと実力を向上させることが可能です。
使用されるスライドもテキストを映して講義が行われる場合と異なり、かなり動きのあるものになっていますので、見ていて飽きません。
仕事でプレゼンテーションを行う、プレゼンテーションを聞く場合にはパワーポイントが使用されることも多いですが、ただただ画面を見ながら聞いているよりも、動きのあるパワーポイントの方が印象に残りますよね!
それと同じでスタディングの講義は動きのある内容ですので、見て、聴いているだけでも理解しやすい、頭に入ってきやすい、記憶に残りやすいモノになっています。
もちろん講義の視聴も片手のスマホでOK!
スライドは大きめの文字で作成されていますし、細かく分割されて作成されていますので、スキマ時間を見つけては少しずつ進めていくことが可能です。
講義は一気に見た方がよいのでは!?
講義をスキマ時間に少しずつ見るのってどうなんでしょう?
資格学校などの講義は2時間~2時間半くらいが1コマとされていることもありますし、ある程度の量をインプットして、講義終了後にアウトプット(問題を解く)していくというのが一般的ですよね。
だから、講義映像はある程度まとまって見ないといけないのでは?と思ってしまいます。
私もそう思っていました。
でも、今は私の体験から申し上げますと、スキマ時間に少しずつ見ることでも十分に価値があります。
その利点はズバリ「どこまで見たっけ?」「前に見た内容は何だった?」と必ず考えるからです。
考えるのはほんの数秒、一瞬かもしれません。
でも、それは立派な「復習」になります!!
試験勉強で大切なのは「繰り返し」、つまりは「復習」です。
「復習しなくちゃ!」と焦って行うよりも、スキマ時間を活用しようとすれば、脳が勝手に復習モードになってくれるので、ある意味お得ですよね。
ですから、時間の長短を気にせずどんどん進めていきましょう。
あっ、もちろん時間のあるときは一気に見るのもアリですよ。スキマ時間じゃないとダメ!!という話ではありませんので、よろしくお願いします。
WEBテキストなので常に持ち歩き可能
「今日はどのテキストを持っていこうかな」という悩みはありません。
スタディングはWEBテキストが基本
スタディングの講義は、非常に分かりやすいスライドを用いて行われます。
そこに講師の方が説明を加えてくださるので、受講生はそれを見て、聴いて知識を得ていくことになります。
そしてスタディングでテキストとなるのは、この「スライド」です。
「スライド」がテキスト!?
そう思われるかもしれませんが、ご安心ください。
そして、ぜひ1度、登録するだけで無料講義を見ることが出来ますので、試してみてください。
「このスライド、そのまま欲しい」と思わずにはいられないでしょう。
良くまとまっていますし、講義用としても作られていますから、とても見やすいのです。
この見やすいスライドが「WEBテキスト」として、いつでも何回でもどこでも見られるというのは嬉しい限り。
重い思いをせずに脳裏に焼き付くまでWEBテキストを見ることが可能です!
もちろん印刷可能です
こちらのWEBテキストはもちろん印刷することも可能です。
この図表は手元に持っておきたい、何回も繰り返し見ることになりそうと思ったものが出てきたときは、迷わず印刷!
でも、ちょっと待ってください。
せっかくスマホなどで「いつでもどこでも勉強」をいうスタイルを貫くのであれば、覚えておきたい図表はスクショもありですよ!
私も受験生時代には覚えておきたいことをまとめた表、覚えられない文言などは写真を撮って、いつでも見返せるようにしていました。
その時に使用していたスマホのアルバムは「謎のメモ」ばかりが保存されている、非常に奇妙なものでした。
スタディングのWEBテキストは非常にキレイに作られていますので、スクショして後で見返すのにも最適です。
勉強といえば「紙こそ神」という方へ
英和辞典は紙と電子のどちらを選べばよいのか!?!?
という議論はもう何年も聞く話ですね。
私は英語の勉強も好きなので、この議論にも非常に興味を持っています。
最近は「電子」というか「スマホ」のアプリを用いて英単語を調べるというのが主流になっているのかなという印象を受けます。
一方で辞書といえば「紙」でしょ!!という方もたくさんいらっしゃいます。
そして、勉強するにしても「紙」が基本でしょ!!という方もたくさんいらっしゃいます。
すみません、実は私もスタディングをオススメしておきながら、実は「紙・派閥」の人間であったりします。
英和辞典にしても勉強テキストにしても、WEBを活用していくことには全く抵抗はないのですが、どうしても手元に紙媒体のものが欲しいと思ってしまうのです。
昨今は「書いて覚えるのは時間の無駄」という風潮もありますし、実際にそうなのかもしれません。
でも、自分の勉強には「紙」がないとダメなのだという思いを持っている方も多いのではないでしょうか。
ご安心ください。
ちょっと費用が掛かりますが、スタディングでWEBを主体に勉強する際にも、紙ベースのテキストを購入することが可能です。
先ほどよりお勧めしている、スタディングのスライドつまりWEBテキストが冊子になったものを購入することもできるのです。
書き込みしたい、マーカーを引きたい、ペラペラとページをめくりたい、テキストの汚れ具合が勉強のバロメーターという方もいるはずです。
全てWEBで勉強っていうのも抵抗あるなぁ・・と不安に感じている方も、これで安心ですね!
WEBを最大限に活用するならスタディングの社会保険労務士講座がおすすめ!
勉強の流れもスタディングにお任せ
スタディングの講座は講義映像の視聴、その後に問題を解くという流れがあらかじめ構築されています。
基本的には講義を受けて、すぐに問題演習という勉強方法になるのですが、講義が続くこともあれば、問題のボリュームが多いこともあります。
それらが全て決定されているのって実はありがたいですよね。
「講義を視聴する」のと「問題演習を行う」のはどちらが好きですか?
言い方を変えれば、どちらが苦しいでしょうか??
多くの方が「講義を視聴する」のが好きで、「問題演習」が苦しいと感じるのではないでしょうか。
問題演習はどうしても「できない自分」を肌で感じることになります。
そのため、自分で好きなように勉強のプランを組もうとすると、必然的に「講義の視聴」に傾いてしまうのではないでしょうか。
そんな受験生の気持ちが汲まれている、いや、見透かされている!?
スタディングの学習はすぐに問題演習を行うことができるように順番が組まれていますので、それを信じて愚直に1つずつこなしていきましょう。
※ただし、選択するコースによって構成も異なりますので、ご注意ください。記事の後半に掲載している「講座の種類とオススメ」を参照してくださいね。
「講義だけを先に全部見てしまおう!!」という気持ちは私もよく分かりますが、お勧めしません。
なぜなら、後に残った問題演習をひたすらこなしていくというのが苦しいからです。
そして、「あとでやろう!」はやらない確率がとてつもなく高いということを私は知っています(笑)
質問可能なプログラムもあります
通信教育で学ぶと決めた時、気になる点の1つは「質問が可能か?」ではないでしょうか。
私の経験からしますと「質問の可否」はそこまで気にすることはありません。
学んでいけば次第に理解は深まりますし、ネットで調べれば大抵のことは解決するためです。
私は資格学校に3年間通い、いつでも質問できる環境にあったわけですが、質問したことはほぼゼロです。
とはいえ、初めて勉強する場合は「質問できるのか、できないのか」は自分の不安を取り除くためにも大切なポイントですよね。
スタディングは受講する講座によって、質問が可能なものもあります。
次の「講座の種類」のところで紹介しておりますので、確認してみてくださいね!
講座の種類とオススメ
スタディングの社労士合格コースは3種類あります。
- 社労士合格コース ミニマム
- 社労士合格コース レギュラー
- 社労士合格コース フル
社労士合格コース ミニマム
各科目の概要を知ることが出来る「入門講座」と勉強のコツを学ぶことができる「合格戦略講座」に加えて、各科目のメイン講義となる「基本講座」のセットになっているものです。
ミニマムという名前のとおり、インプット講義だけがセットになっているものですので、こちらのコースを選択した場合は、アウトプットは自分で行う必要があります。
スタディングを軸に社労士試験にチャレンジする場合ですと、ミニマムコースはちょっと厳しいですかね。
やはりアウトプットは非常に大切ですので。
他の通信教育も受けている、資格学校に通っている、でも理解が追いつかない、知識を補充したいといった場合に利用するというのはアリかもしれません。
社労士合格コース レギュラー
レギュラーコースは、ミニマムコースに「スマート問題集」、「セレクト過去問集」、「総まとめ講座」を追加したものになります。
私はこちらのコースをオススメします。
やはり知識の定着にはアウトプットが欠かせません。
「スマート問題集」は一問一答形式の問題が出題されるので、それに〇・×で回答していくものになります。
勉強の流れはスタディングにお任せしてしまえばOK!ということを既に紹介していますが、それはインプット講義の後に、このスマート問題集を活用して演習するという流れが構築されているからです。
ですから、分かりやすいスライドでインプット、学んだ知識を即アウトプットしていくためにも「スマート問題集」は欠かすことの出来ないプログラムなのです。
社労士試験に挑むためには過去問演習も欠かせません。
過去に出題された論点は繰り返し問われる可能性も高いですし、過去問は他の受験生も必ず取り組んでいますので、もし過去問で問われた内容が出題された場合、取りこぼしは致命的です。
そこで「セレクト過去問集」の出番です。
過去に出題された問題で重要なものを、本番と同じように五肢択一形式で取り組むものです。
普段、〇×形式の一問一答を行っている場合には気づきにくいのですが、五肢択一形式の問題を解いている時に必ず起こることがあります。
「2つまでは絞れるのだけれど・・・」という現象です。
5つの選択肢(問題)のうち、3つは容易にその〇×が分かるのですが、残りの2つについて判断を下すのが非常に困難だと感じる場面に必ず出くわします。
そうした場面になっても慌てず、落ち着いて対処するために「五肢択一形式」の問題にも慣れておくべきでしょう。
単なる知識の有無だけに限らず「問題文を読み飛ばすクセがある」、「五肢択一形式になった途端に焦ってしまう」など、思いもよらない発見もありますよ!
レギュラーコースにはさらに「総まとめ講座」も含まれています。
こちらも社労士試験にチャレンジしていく上では絶対に外せない内容がてんこ盛りの講座ですので、受講は必須です。
具体的な内容ですが、白書・統計対策、横断整理、法改正、計算事例、判例などに関する講座が含まれているのです。
多くの受験生が苦しめられる一般常識対策にもなりますし、理解を深めるためには横断整理もどこかでやらなければなりません。
法改正もいつ出題されてもおかしくないですし、近年は実務に近い問題が出されることを考えますと計算問題の対応もしておいた方がよいでしょう。
やっておいた方がいいと思われる内容がこれでもか!!というくらいに押し寄せてきますので、必ず押さえておくべき講座です。
インプット、アウトプット、押さえておくべき論点の全てが含まれているレギュラーコース、間違いなくオススメです!!
社労士合格コース フル
社労士合格コース「フル」は「レギュラー」コースに直前対策答練と合格模試を加えたものになります。
試験が近づいてくるにつれて、大切なのは問題演習です。
直前対策や模試では直近の法改正や白書に関する問題も出題されるはずですので、なるべくなら受講しておきたいですね!
とはいえ、直前期はこれまでに勉強してきたことすら定着していないと焦る時期でもあります。
そして、社労士試験の模試と言えばTACとLECの規模が依然として大きく、受験する人もかなり多いのが実情です。
他の人が押さえている知識は自分も押さえておきたいですよね。
もし本番で多くの人が受験した模試の問題が出ようものなら、それだけで不利に感じてしまいます。
もし他校の模試を受けるつもり、直前期の大変さなど想像も出来ないという場合には、とりあえず「レギュラー」コースを受講しておくというのもアリかもしれません。
結局オススメはどれ?
私は「レギュラー」コースをオススメします。
その理由は「紙のテキストが欲しい」からです。
ガッツリ勉強するなら「フル」コースで決まり!なのですが、フルコースを断念する代わりに、浮いたお金で「紙のテキスト」を購入するという選択肢はいかがでしょうか。
紙のテキストはWEBテキスト、つまり講義内で使用されたスライド等が印刷された冊子を購入することができるというオプションです。
先ほども紹介しましたが、スタディングの講義内で用いられるスライドは、簡潔かつ分かりやすいものが多いです。
講義を視聴している中でも「今のスライドは何回も見たい」「今回学んだスライドはそのまま覚えてしまおう」と感じさせてくれるものが多々あります。
手元にテキストがあるとパッと開いて確認したり、お風呂、トイレ、歯磨き中にパラパラとめくってみたり、スマホで確認するよりも気楽に触れることが出来ます。
私自身が全てを電子デバイスで済ませるよりは紙の教材を取り入れていきたいタイプということもありますが、ぜひオプションのテキストも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
講義時間
スタディングのHPではインプットの講座に関する講義時間が掲載されているので、しっかりと確認しておきましょう。
インプット講義をとりあえず1周させるというのが勉強の大きな指針の1つになります。
スキを見つけてコツコツ取り組んでいきましょう!
スタディングのインプットにかかる時間は概ね以下のとおりです。
| 講座名 | 講義時間 |
|---|---|
| 入門講座 | 6時間 |
| 合格戦略講座 | 5時間 |
| 基本講座 | 124時間 |
合計すると大体135時間程度になります。
入門講座と合格戦略講座はサクっと終わらせつつ、必要に応じて何度も見て、戦略をもって勉強していくのも大切ですよ!
レギュラーコース、フルコースを選択した方は「講義」→「問題演習」という流れの繰り返しになりますから、講義と問題演習はなるべくセットで、近い時間の中で取り組めるのが理想ですね。
白書や法改正について学ぶことのできる「総まとめ講座」の時間は残念ながら掲載されていませんでしたが、取り組むのは勉強の中盤~後半にかけてになります。
その頃はただでさえ覚えなければいけないことがあふれ返り、厳しい状況の中での視聴となりますが、慌てることなく少しずつこなしていくことを心がけましょう!
価格
フォーサイトのの各講座は比較的安価でありがたい限りです。
| カリキュラム名 | 価格(税込) |
|---|---|
| 社労士合格コース ミニマム | 46,800円 |
| 社労士合格コース レギュラー | 59,800円 |
| 社労士合格コース フル | 74,800円 |
※こちらの価格は私が2024年2月時点で調べたものになります。
安いですね!!!!
普段のランチの値段や居酒屋での支払いに比べたら高額ではありますが、他社の社労士講座と比べれば、破格のお値段となっております。
私のオススメはレギュラーコース+紙テキストです。
ちなみに紙テキスト(冊子)は全20冊でお値段なんと、29,800円です。
レギュラーコース+紙テキストは89,600円となります。
テキストを含めるとちょっと高く感じてしまうなぁという方もいるかと思いますが、「このスライドいいな!」と思った時に個々に印刷するよりは、最初から手元にあった方が圧倒的にラクですよ!
あくまで、テキストは「紙」媒体のものがないとイヤ、紙の方が落ち着くという方へのお勧めです。
いずれにしても一問一答、過去問など問題演習は欠かせないコンテンツなので「レギュラー」か「フル」を選ぶようにしましょう!
その他のポイント
スタディングの勉強サイトには、同じようにスタディングを活用して勉強している人とのコミュニケーションが可能なコンテンツもあります。
他の人がいま何を勉強しているのかな、どんな悩みを抱えているのかなといったことを知ることが出来ますし、逆に自分から勉強に関する発信をすることも可能です。
通信教育はどうしても孤独な勉強環境の下で行いますので、交流の場があるというのは非常にありがたいですね!
とはいえ、お互いに励ましあうのが楽しくなってしまって、交流サイトに入り浸ることがないように注意してください(笑)
大手資格学校の模試は受けましょう
他の記事でも同じことを記載していますが、通信教育で学習している場合でも大手資格学校が開催している模試は受験することをお勧めします。
模試の受験は「自分の実力」がどれくらいかを確認するため、今年の合格を占うためだと思っていませんか?
もちろんそれも模試を受験する大きな意義の1つです。
が、しかーし、私はそれ以上に本番を想定した細かい確認をするべきだと断言します。
時間配分、雰囲気、問題を解く順番、試験開始前に何をするのか、お昼の休憩には何をするのか、当日の服装、持ち物、当日の朝の過ごし方、前日夜の過ごし方など。
本試験まではひたすら勉強となってしまいますが、勉強以外の試験準備がおろそかになってしまっては、本番前日、当日に慌てふためくことになります。
例えば腕時計は準備していますか?
普段はスマートウォッチを使用している方も、本番では使用できません。
腕時計は持っていると思っていても、電池が切れてしまっていたりしませんか?
私はTOEICテストの当日に腕時計が止まっていることに気づき、散々な目にあいました。
本番で自分の力をいかんなく発揮するには、余計なことでストレスを抱えたくありません。
そのためにも、入念な準備が必要です。
ぜひ会場受験できる大手資格学校の模試を受講するようにしましょう!
おわりに
社労士試験のオススメ通信教育として、スタディングの社労士講座を紹介しました。
・スキマ時間の活用ならスタディング
・オススメはレギュラーコース+紙テキスト
・携帯片手に簡単に勉強が進められる
勉強はどっしりと机に座って、ハチマキ巻いて、気合を入れて行うだけが全てではありません。
そんな環境が作れないことはよくあること。
スキマ時間の活用が十分に考慮されて作成されているスタディング。
忙しいあなたにお勧めします。