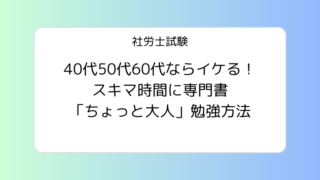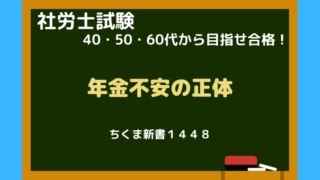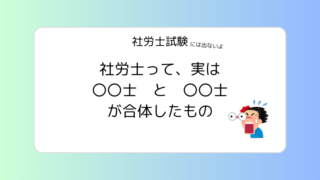社労士試験 「よくわかる社会保障法 第2版」
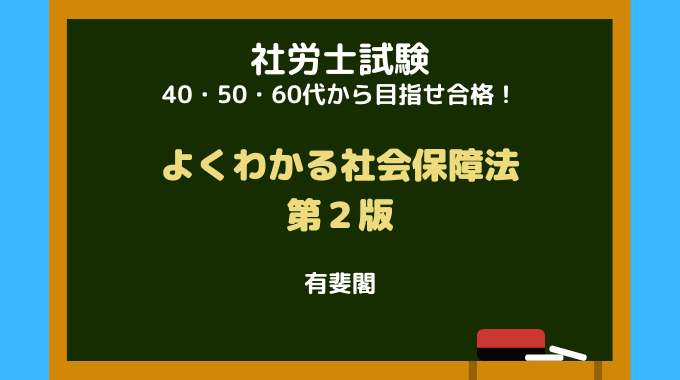
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
今回は社労士試験の試験科目についての記載も多い書籍を1冊紹介します。
はじめに
社労士試験では社会保険科目で得点を稼ごうというのはよく言われる話ですが、社会保険科目はなかなか分かりづらいというのも事実です。
何か概要を掴める書籍がないかな?とお探しの方にオススメの1冊を紹介いたします。
書籍の概要
今回紹介する書籍はコチラです。
よくわかる社会保障法 第2版
有斐閣 2019年3月発行
総ページ数は314ページ。書籍のサイズはA5判(横148×縦210mm)と教科書サイズになっています。
執筆者は以下のとおり6名おり、そのうち稲森氏、西村氏、水島氏の3名が編者(論文集や教科書などの複数の人が執筆する書籍において中心となってとりまとめの役割を果たす人)です。
- 稲盛 公嘉 :京都大学大学院法学研究科教授
- 西村 健一郎:京都大学名誉教授
- 津田 小百合:北九州市立大学法学部准教授
- 福島 豪 :関西大学法学部教授
- 水島 郁子 :大阪大学大学院高等司法研究科教授
- 倉田 賀世 :熊本大学法学部教授 ※いずれも書籍に記載されている時点のもの
社会保障関係の専門家によって書かれている専門書となります。
以前にこちらの記事でも簡単に紹介している書籍なのですが、専門書でありながら非常に読みやすく、社会保障に関する概要を学ぶのに適した1冊です。
本書は2019年に発行されていますので、法改正の多い社労士試験からすると情報が古くなってしまっている部分もあるのではないかという懸念もあるかと思います。
もちろん最新の改正内容が反映されているわけではありませんが、各種制度の幹の部分を学ぶことは出来ますし、この書籍を読んだあとにテキストを読めば、テキストの内容がより頭にスーッと入ってきます!
こちらの書籍は以下の構成になっています。
- 社会保障の世界へ
- 公的医療保険・高齢者医療
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
- 社会福祉
- 生活保護
- 社会保障の権利と財政
社会保障と言われると健康保険や年金がメインかなと思ってしまいますが、労災保険や雇用保険についても記載があります。
社会保障=社会的保護という意味合いもあるためだと思われますが、いずれにしても社労士試験の科目が多く入っていれば、読んでおいて損はないですよね!
また、こちらの書籍の大きな特徴として全ての記載が対話方式になっているという点にあります。
大学のゼミを舞台として4人の学生と先生が議論を交わしているという形式になっており、それが「より読みやすい専門書」の要因の1つとなっています。
それでは、各章についてもう少し詳しく見てみます。
第1章 社会保障の世界へ
「社会保障とは何か?」について書かれており、しっかりと読んでおきたいパートの1つです。社労士試験のテキストではあまり触れられていない点だと思いますので、ここで全体像をつかんでおくことは今後の学習にも役立つこと間違いございません!
第2章 公的医療保険・高齢者医療
健康保険法がメインになりますが、国民健康保険、医療供給体制(医師の登録や診療報酬に関すること等)については試験勉強においてあまり深くは触れられませんので、本書でその概要を知ることが出来ます。
第3章 介護保険
介護保険もその言葉自体はよく聞くものの、その割にはフワフワとした知識になってしまっていることが多いのかなと思います。実際に自分もそうでした。
提供されるサービスの種類なども細かくて、勉強内容としてはあまり関わりたくないと思っていました。本書ではかなり丁寧に詳しく説明されています。
第4章 年金保険
年金についてはそのまま試験範囲ですので、制度の中身などの細かい点は試験用のテキストの方がより詳しく記載されています。本章では年金制度の全体像、財源など大きい視点について書かれている箇所を中心に読むことをお勧めします。
第5章 労災保険
こちらも給付内容などは試験用テキストの方が圧倒的に詳しいです。本書の所々に問題提起とその考え方(例えば、業務による災害によって小指を失ってしまった場合、ピアニストとサラリーマンではその重みが異なるのに同じ扱いでよいのか?など)についての記載があります。そうした点に重きを置いて読むのがよいと思います。
第6章 雇用保険
雇用保険については、社労士試験という観点からしますと「あまり読まなくてもいいのかな」という章です。概ねテキストや受講されている講義の中で説明される事項ですので、復習、知識の整理及び全体像の把握に活用するのが良いでしょう。
第7章 社会福祉
社労士試験では労働という観点から育児介護休業法や障害者雇用促進法などが勉強対象のメインとして注目されていますが、児童や障害者に対する支援はそれだけではありません。他にはどのようなサービスがあるのかを知っておくことは今後の勉強により深みを与えてくれます。
第8章 生活保護
生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行うこととされている生活保護法は、救貧制度として古くから運用されているものです。
他の社会保障制度等を補完するという位置にあり、最後のセーフティネットとも呼ばれている制度は、試験科目ではないにしても知っておくべきものです。
第9章 社会保障の権利と財政
受給権の消滅、併給調整や社会保険の財政について学ぶことができる章です。社労士試験の勉強は制度の内容等を把握するのがメインになってしまい、財政がどうなっているのかといった点にはなかなか手が付けられないですよね。第9章を読んでその概要を掴んでおくと今後の勉強においても「いまいちよく分からない」という場面が減少すると思います。
本書を読むにあたっての注意点
2019年の発行です
先ほども記載しておりますが、2019年の発行ですのでその後の法改正事項などはフォローされていません。
そのため社労士試験という観点からすると多少古い情報となってしまっている点もあります。
本書を読んで「ここは押さえておきたい!」「理解が深まった!」と感じる点があったら、ぜひ線を引くなり、メモに残しておくなど行い、あとでテキストに書き込むようするのが良いと思います。
試験に関係ないと思われる所も読みましょう(時間があれば)
大前提として本試験までに時間の余裕がある場合の話になります。
試験が近づくにつれどんどん余裕が無くなっていき、あれも覚えてない、これも終わってない、それは理解すら怪しいという状態になっていきます。
しかし、試験までにまだ時間があるようでしたら読み飛ばさずに、一度でもいいので全ての章を読んでおくことをお勧めします。
例えば第8章の生活保護などは社労士試験にはほぼほぼ関係のない箇所になります。
しかし、試験に向けて学んだこと以外にもこのような制度があるということを知っておくのは、試験用に学んでいる法律が「何をどこまで保護しているのか・保護していないのか」という理解にも役立ちます。
もちろん一般的な常識・教養としても役に立ちます!
全部は読んでいられない場合
通読する余裕はないけれども、社会保険(社会保障)関連については理解も暗記も何だかモヤモヤしているという方については、必要な箇所をピックアップして読んでいただいても全く問題ございません!
私が改めて読んでみて、特に読んでおいた方がよいと感じたのは「第1章(社会保障の概要)・第4章(年金)。第9章(財政等)」の3か所です。
年金はやはり分かりづらい、頭がゴチャゴチャしてしまうということもありますので、第4章を一気に読んでしまうのがお勧めです。
また、1章と9章で社会保障の土台・軸となる考え方などを学ぶことは各論を学ぶ上での基礎になります。
おわりに
今回は「よくわかる社会保障法 第2版」を紹介させていただきました。
社会保険科目は断片的な暗記も必要ですが、その土台となるのは全体像を見ること・理解をすることです。
社会保険関係が苦手だなぁという方には特におすすめしたい1冊です!