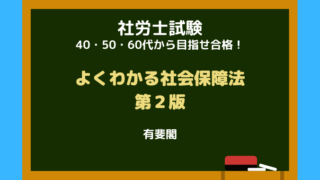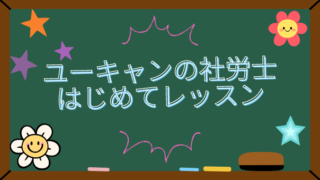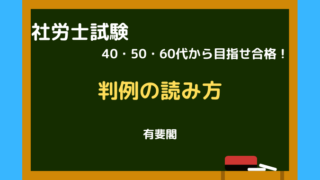社労士試験 「はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第20版」
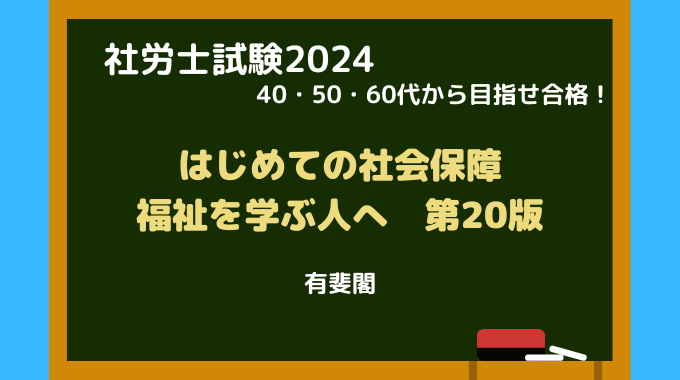
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
今回は社労士試験の学びを深めるための1冊を紹介します。
はじめに
先日、社会保険科目の理解を深めるためということで、書籍を1冊紹介させていただきました。
新たに社会保障に関する書籍を1冊読み終え、知識のアップデートを行いました。非常に勉強になる本でしたので、ご紹介させていただきます。
書籍の概要
今回紹介する書籍はコチラです。
「はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第21版」 有斐閣
総ページ数は約300ページ。書籍のサイズは四六判(横127×縦188mm)で単行本と同じサイズになっています。
著者は椋野美智子先生と田中耕太郎先生です。お二人とも厚生省に入省後、大学の教授になられているという経歴をお持ちです。
以前にご紹介した「よくわかる社会保障法」と同様に社会保障関係の専門家によって書かれている専門書です。
「よくわかる社会保障法」は2019年に発行されていますので、多少古くなってしまっている情報などもありますが、今回ご紹介する「はじめての社会保障」は2001年の初版発行以来、ほぼ毎年「版」を変えて発行され続けています。
つまり、常に内容が最新のものにアップデートされていますので、どうせなら新しい情報を知って勉強に役立てたいという方はこちらの書籍がオススメです。
それでは早速、本書の章立てを確認していきます!
- 序章 :社会保障の見取り図
- 第1章:医療保険
- 第2章:生活保護と社会福祉制度
- 第3章:介護保険
- 第4章:年金
- 第5章:雇用保険
- 第6章:労働者災害補償保険
- 第7章:社会保険と民間保険
- 第8章:社会保障の歴史と構造
本書のサイズは非常にコンパクトですが、内容は盛り沢山です。
各章の内容をもう少し詳しく見ていきます。
序章 社会保障の見取り図
何のために社会保障を学ぶか?社会保障とは何か?についての概要を学ぶことが出来ます。特に印象に残っている記載が「社会保障を丸暗記しようとするのは無駄の多いやり方だ。」というものです。
社労士試験の勉強をしている時にも当てはまる言葉だと思います。
第1章 医療保険
社労士試験対策としては健康保険のことを詳しく知りたいところですが、国民医療費の構造や医療保険制度全体の動向、診療報酬制度の仕組みなどを中心に医療保険全般について学ぶことが出来ます。
第2章 生活保護と社会福祉制度
生活保護に加え障害者支援、子育て支援についての記載があります。社労士試験での学び以外にも子育てについては様々なサービスがあることを知り、知見を広めましょう。
第3章 介護保険
介護保険について要介護認定の仕組み、サービスの種類などを詳細に学ぶことができます。社労士試験では介護保険法を詳しくは勉強しませんので、本書で制度の概要を補完するようにしましょう。
第4章 年金
年金制度の概要はもちろんのこと、財政方式や「基礎年金の税方式化」についての問題点などを学んでおくことは非常に勉強になります。もちろんメインの勉強は試験用テキストになりますので、あくまで補完材料として活用してください。
第5章 雇用保険
雇用保険については、各制度の内容が簡易的に紹介されている程度ですので、こちらもテキストの補完として活用するのがよいと思います。また、本書にはいくつものコラムがありますので、雇用保険についてはそちらをメインに読んでもいいかもしれません。
第6章 労働者災害補償保険
労災保険についても制度についての簡単な紹介がされているのみですので、試験用のテキストや講義をメインとしてください。本章は読み飛ばしてもよいかもしれません。
第7章 社会保険と民間保険
社労士試験にとって全く重要ではない内容ですが、勉強している最中及び資格取得後に「民間保険と社会保険って何が違うの?」と聞かれたときに「よく分かりません」とはなかなか答えづらいものです。
その共通点や異なる点をしっかりと認識することは、今後、社会保険のプロフェッショナルとなるのれあれば必ず知っておかなければならないものです。
第8章 社会保障の歴史と構造
私個人としては、本書の中でも重要な内容の1つだと思っています。
なぜ社会保障が必要なのか、どのような理由でどのような変化を遂げてきたのかを知ることも「丸暗記」を脱却するため、有効な手段になります。
歴史など普段の勉強ではなかなか触れられることもないので、一読の価値アリです!
本書のおすすめポイント
社労士試験チャレンジ中の方にオススメします
社労士試験に関係しない内容もありますので、必ず読んでおくべきですと言うわけにはいきませんが、知識の補完、復習、幅を広げるという意味では非常に勉強になる内容です。
一方で、以前にご紹介した「よくわかる社会保障法」と比べますと、内容が詳細かつ濃くなっています。
そのため、社労士試験の勉強を始める前に概要を学ぶという目的で読まれる場合には本書よりも「よく分かる社会保障法」がよろしいかもしれません。
民間保険との相違、社会保障の歴史はオススメ
各章の概要を紹介した際にもオススメしましたが、第7章の「社会保険と民間保険」、第8章の「社会保障の歴史と構造」はお時間が許す限り読んでおきたい内容です。
私もそうでしたが、社労士試験の勉強を行っているときに「そもそも社会保険って何?」ということを考え、答えられる人はなかなかいないのではないでしょうか。
そうした根底を知るということは、それによって作られた法律のことを知ることにもつながります。
どうしても暗記することに注力してしまいがちな社労士試験ではありますが、何だかうまく理解できない、記憶に残らないといった時には本章の歴史などを再読することで、社会保障の必要性や問題点を認識するというのも有効だと思います。
おわりに
今回は「はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ 第21版」を紹介させていただきました。
社労士試験に合格した後の勉強としてもお勧めされることがある書籍ですので、お時間があればということにはなってしまいますが、勉強の合間の息抜きも兼ねて一読する価値のある本です。
私が受験していたときは社会保険・社会保障の全体像などは全く見えていませんでした。今思えば、こうした背景知識があるだけでもだいぶ違っただろうなと感じていますので、よかったら手に取ってみてください!