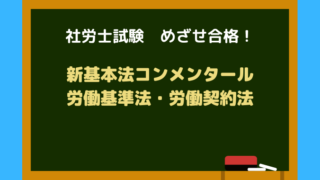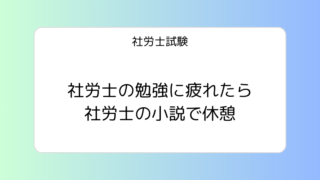社労士試験 詳解労働法 第3版
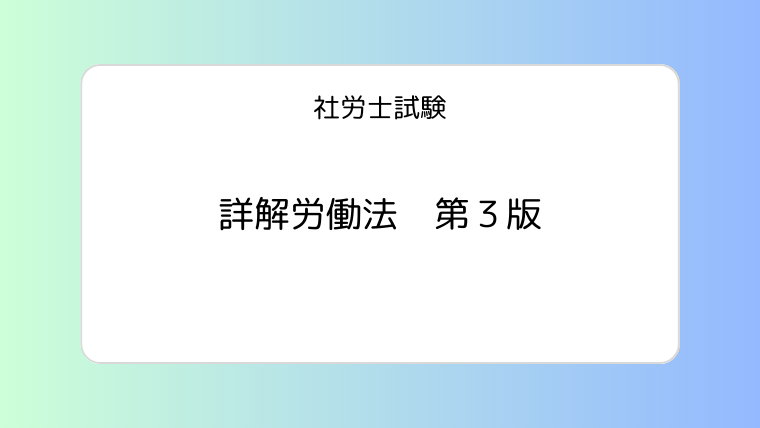
読んで学べる!持ち歩けば鍛えられる!学びと筋トレの玉手箱や~。総ページ数1454ページ。ふぅぅ~、とりあえず読み切った!頑張った(笑)
はじめに
今年(2023年)の9月下旬に「詳解労働法 第3版」が発刊されました。今、発刊されている労働法関係の書籍では、最新・最厚・最詳=最高と言えるんじゃないですかね!
オレの極貧財布から8,580円を捻出して何とか購入。
約2か月かけてひととおり読み終えたから、その感想文になります。
レビューするとか、評価するとか、オレがそんな立場にはないのであくまで感想を。
買おうかな、読んでみようかなと思っている方の参考になれば!
書籍の概要
こちらの書籍は2019年9月に初版が出版され、2021年9月に第2版、2023年9月に第3版が発売されています。
何だか最近は(といっても、昔のことはよう知らないけど)労働法関連も制度改正が多いから、2年おきに改訂してもらえるというのは素直にありがたいですね!
ちなみに初版は1360ページ、第2版は1404ページ、第3版は1454ページとどんどんページ数が増えて、内容が充実しています。お値段は据え置き!笑
第2版については、労働法に関する様々な質問がQ&A形式で掲載されている「公式読本」も発売されている、発売されていたんです。こちらもお勧めですよー。

実際に読んでみて
本書は労働法に関するありとあらゆるテーマについての記載があるから、本当にすごい書籍だなとしみじみ実感。
労働法に関する知識は何とか保っていきたいと思って、それなりに関連する本を読んできたつもりのオレですが、それでも「へぇぇ、そうなのか」「ひえー、知らなかった!」と思う内容が大量にあった。当たり前だけど。
社労士試験のためのテキストや講義では割と軽めに流されてしまう、けれども、もしかしたら今後試験でも狙われてくるのではないかとオレが勝手に思っている「憲法と労働法の規定」などについてもしっかりと書いてある!
個人的に、特にじっくりと読んだ箇所はまず「就業規則」。
オレは今は社労士とは全く関係ない業務をやっているけれど、その一方で現在籍を置く会社の規程は昔からほとんど改善・変更・見直しがされていないような状況。はっきり言って「ナニコレ?」と思う内容が多数アリ。
だから就業規則の効力とか、法的な位置づけなどをもう1度学ぶのに非常に勉強になる。このあたりは労働契約法も絡んでくるから、以前に紹介した「新基本法コンメンタール 労働基準法・労働契約法」でも同じような内容を学ぶことは可能です。
でも、本書は両方の法律、裁判例などを分かりやすくまとめて解説してくれているので、読みやすさという面からも本書がオススメですよ!
それ以外でオレが熱心に読んだページは「賃金」と「年次有給休暇」。
結局、自分に関係のあるところにどうしても目が行ってしまうのは仕方ない(笑)
賃金と言われてパッと頭に浮かんでくるのは「賃金支払いの5原則」とかだけど、本書を読んでいると賃金の請求権がいつ発生するのかといった内容も同じくらいに興味深いものだなと感じる。
年休に関して言えば、最初の付与が勤務を始めてから6か月後となったのが1993年からというのに驚いた。だって、つい最近じゃないの!(オレの中では)
時間単位年休が認められたのは2008年というのにもっと驚き。2008年なんて、つい昨日のことのよう。それは言いすぎかな、でも1週間前くらいの感覚(オレの中では)
それらに加えて欧州との年休の取り方の違い、そもそも年休に対する考え方の違いなどもサラッっとではあるけれども掲載されていて、本当に勉強になりますよー。
実際に読んでみて 2
詳解労働法というタイトルにもあるとおり、労基法・労契法だけでなく安衛法、労災法、雇用保険法などはもちろんのこと、社労士試験の労働一般常識で問われる可能性のある法律はほぼほぼ含まれている!
含まれていないものとしてパッと思いつくのは、社労士法くらいかな。
こうした各法律を個別に学ぶのではなく、横断的に把握することが出来るのも本書を読むメリットの1つとなりますよー。
他の「労働法」という名前のついた書籍でも同様の構成となっているのですが、本書でも女性、育児・介護、外国人雇用、障害者雇用、高齢者といった単位で各項目が整理されています。
法律ごとに学ぶのではなく、各項目に応じて様々な法律を横断的に読むことが出来るのは大変ありがたしですね!!
また、本書は注釈が充実しているとともに、判例の内容、学説の見解などもかなり詳細に書かれています。注釈はかなり小さい字で書かれているので、老眼の症状が出てきたオイラの目では読むのに一苦労という面もありますが、それでもタメになる内容が多いので、頑張って読みました(笑)
判例に関する記載についても、テキストや判例六法などではどうしても結論のみが書かれている場合も多いと思うのだけれど、本書では結論に加えて、その概要も記載されている場合もあるからより印象に残るし、読み応えがあります。
おわりに
すごく分厚くて素晴らしい内容が盛り沢山なのだけれど、それと反比例するようにオレの感想は薄っぺらなものになってしもうた・・・。それでも、少しだけでも本書の良さが伝わっているといいなと祈るばかり。
本書も社労士試験の突破という観点からはオーバースペックで、必須のものではないのだけれど、勉強をしている中で疑問に思っていることがある、モヤモヤしていることがあるなぁというときには悩むより、調べる、専門書を読んでしまった方が近道の場合もある!とオレは思う。
もちろん興味のあるところだけを息抜き程度に読むってのもアリですね!息抜き用にしては重いし、お高いけれども。
社労士業界では労働法の基本書として「菅野グリーン」が有名だけれど、本書も本当にいいと思いました。専門家でもなんでもないですが、両方とも一応読破した者としての意見です。前にツイッターで書いたことあるのですが、オレは本書を読破しようと思ってからはキツイなぁと思いながらも、常に持ち歩いて読んでいました!
だから電車で読んでいる時などは「アイツ、一体何を読んでいるんだ!?」という視線を感じることもたまにありました。
そーゆーの全く気にならないという人はいいのですが、基本的には家でじっくりと読む、分からないことがある時に読む、知りたい箇所だけ読むという使い方がオススメですよ!
(そんなの言われなくても知ってるわい!分かってるわい!という声が聞こえます)