社労士試験 年金科目の勉強をしてもシックリこない人が読むべき書籍「知らないと損する年金の真実」
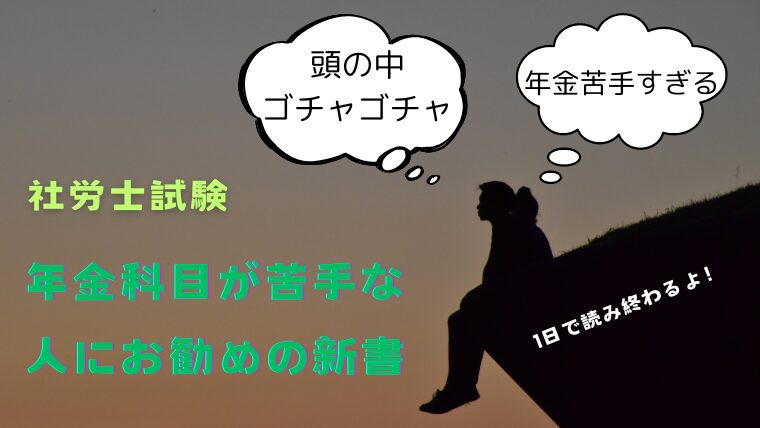
「年金科目を制するものは社労士試験を制する」と言われたりしますが、実際のところはどうなのでしょうか?
私の実体験をもとにするならば、答えは「イエス」です。
たしかに年金科目の点数がとれた年に合格することが出来ました。
でも、なかなか勉強しづらい内容が多いのも事実。まずは全体像を把握するのが大切です。
そこで、年金の問題点や不安をとおして全体像を学ぶことができる1冊を紹介します。
はじめに
社会保障や年金に関する書籍を何冊か読みましたが、本日ご紹介する書籍は、年金についての知識もほとんど無い、社労士試験においてもこれから年金を勉強するといった方も含めて、最もオススメできる1冊です。
書籍の概要
今回ご紹介する書籍はコチラです。
知らないと損する年金の真実
ワニブックスPLUS新書430
2021年10月 発行
総ページ数は269ページです。
著者は大江英樹(おおえひでき)さんです。
書籍に記載されているプロフィールによりますと、大手証券会社で個人資産の運用や企業年金制度のコンサルティングをされた後に独立し、経済コラムニストとしてご活躍されているそうです。
では、まず、本書の章立てを確認していきましょう!
- はじめに
- 第1章 :年金の本質
- 第2章 :年金に対する誤解を解く 初級編
- 第3章 :年金に対する誤解を解く 中・上級編
- 第4章 :知っておくべき年金の歴史
- 第5章 :年金改革で変わること
- 第6章 :公的年金をうまく活用する
- 第7章 :これからの年金との向き合い方
- おわりに
という構成になっています。
発行年が新しい
本書の大きな特徴の1つとして、年金関係の書籍の中では発行年が新しいということが挙げられます。
年金制度自体の手続きや細かい仕組みについては、毎年更新されている専用の書籍があります。社労士試験で問われる内容もそうした書籍に書かれていることの方が多いです。
一方、年金制度の外観を分かりやすく解説されている書籍の中では、本書はかなり新しいものになります。
そのため掲載されている数字や法改正の内容も比較的最近のものまでカバーされています。
法改正事項は試験を見据えるとなると、新しければ新しいほどよく、古い書籍を読んでいると「今はどうなっているのかな?」と常に気を配らないといけません。
発行が新しいというのは「それだけでありがたい」ということになりますよね!
圧倒的に分かりやすい
2つめの特徴として「圧倒的な分かりやすさ」があります。
本書の「はじめに」に次のような記載があります。
誰も教えてくれない年金の本質や勘違いしていることについて、わかりやすく説明をしています。
本書・はじめに より
はい、おっしゃるとおりでした。
非常に分かりよいです。
特に第1章から第3章において、よく言われている年金に対する指摘・非難・不安材料等について、分かりやすくかつ納得のいく記述がされています。
そのため、年金について詳しくないよという方でも安心して読める1冊です。
特に印象に残っている点
私が個人的に特に印象に残っている文章を3つ紹介します。
未経験者は不安だし、経験者は黙っている
これは書籍の序盤に出てくる言葉なのですが、何について語られているか想像がつくでしょうか?
年金について騒ぐ人は「まだもらったことが無い人」が大半だろうという話です。
年金をもらえるのは基本的に65歳になってからですので、まだもらったことが無いという人が大半です。
そして、年金について不安・不満を漏らすのもそうした「年金未経験者」でしょう。
一方でもらえるようになった人も決して「年金には満足している」などとは言いません。
そんな言葉が漏れてしまっては「もう少し減らしても大丈夫なんじゃないか?」といった議論に発展してしまう可能性もゼロではありませんから。
確かにテレビなどで年金のことが取り上げられても、その年金について発言している人はほとんどが「年金は無くても平気だよ!」というくらいに稼いでいそうな人ばかりな気がしてしまいます。
何人の働いている人が、何人の働いていない人を支えているか
私はこの表現に衝撃を受けました。
全くその通り!!!!と、感動してしまいました。大げさですが(笑)
年金の説明でよく見かける図の1つに、若い世代が高齢者を支えている絵を見たことありませんか?
算数でいうところの分母にあたるところに若い世代の絵があり、分子にあたるところに高齢者がいて「高齢者を支えている若い世代の人数はどんどん減っています!」という絵・図です。
よく見るあの絵は、世代別の人口で作成されていることが多く、働いているか働いていないかといった点は考慮されていません。
そして年齢が高くなっても働ける人は収入がありますので、極端なことを言えば年金に依存することもなく、そこまで支える必要が無い人もいるでしょう。
定年年齢も上がっていく一方の世の中で、本書のいうとおり働けない人(働くことから引退した人々)をどれだけ支えていけるかを考えていく必要があると実感しました。
繰り下げて公開するのはあの世、繰り上げて後悔するのはこの世
年金相談の場から出てきた格言らしいのですが、これは本当にウケますね!
私は社労士試験の勉強をとおして、年金受給の繰り上げ、繰り下げという制度があることを初めて知ったのですが、どうしても「何歳からもらうのがベストなのかな?」と考えてしまいますよね!
本書の中でも年金は損得勘定ではないということが学べます。
しかし、この格言のとおり、何歳を選んだとしてもきっと「あーすればよかった」「こうした方がよかった」と思ってしまうのでしょう。
私はギリギリまで繰り下げたいと思っているのですが、75歳まで働くことのできる職場を見つけなければいけません。
そして健康な身体を保たなければなりません。
おわりに
今回は「知らないと損する年金の真実」を紹介させていただきました。
本書は社労士試験の本には載らないような年金の概要、問題点を知るには非常に勉強になる1冊です。
制度の細かい説明などはありませんので、全体像を知りたい、今の年金制度が構築されてきた考え方などを知りたいといった場合には最適な教科書です。
これまで何冊か年金や社会保障の書籍を紹介してきましたが、読みやすさはナンバー1になります。
こちらの書籍を読んで、国年・厚年の勉強をより有意義なものにしてもらえたらと思います。











