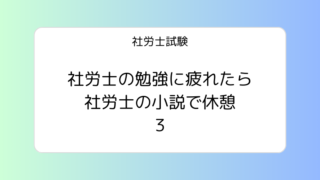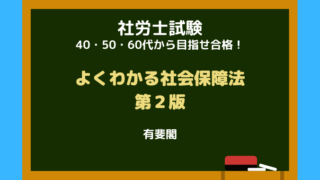社労士試験 「年金不安の正体」ちくま新書
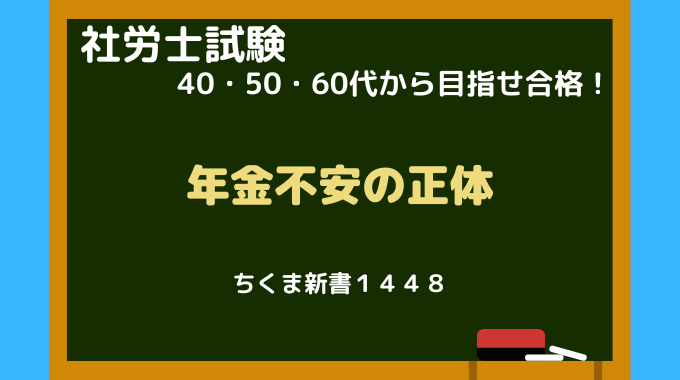
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
今回は年金に関してのモヤモヤを無くすための1冊を紹介します。
はじめに
社労士試験を終えてから社会保険、特に年金についてはあまり触れる機会が無く、必死に覚えた内容もほぼほぼ抜け落ちてしまったことを痛感しています。
年金は全体像から抑えるのも有効な勉強方法の1つであり、丸暗記にならないようその仕組みや歴史を知っておくことも非常に大切です。
そうした年金全体を把握するのにタメになる1冊を紹介いたします。
書籍の概要
今回は紹介する書籍はコチラです。
年金不安の正体
ちくま新書1448
2019年11月 発行
総ページ数は204ページです。
著者は海老原嗣生(えびはらつぐお)先生です。
書籍のプロフィールによると、発行当時のものになってしまいますが「雇用ジャーナリスト、中央大学大学院客員教授」をされているようです。
それでは早速、本書の章立てを確認していきます!
- 序章 :年金制度の本当の問題とは
- 第1章 :積立方式では解決しない
- 第2章 :厚労省が悪い、では解決しない
- 第3章 :「年金は欲しいが高負担はいや」という世論
- 第4章 :ウソや大げさで危機を煽った戦犯たち
- 第5章 :ベーシックインカムの現実度
- 第6章 :昨今繰り広げられた、対立的な政治風景
- 終章 :もっと本気で高負担社会
- おわりに:空気と水と平和と福祉
年金制度の問題点と言われていることについて、データ等を用いながら「何が問題と言われているのか」そして「実際はどうなのか」ということが分かりやすく解説されています。
社労士試験に出てくるような年金制度に関する仕組みの説明などは特にありませんが、その仕組みが構築される背景を知ることが出来ます。
漠然と暗記をするよりは、勉強への効果も高まりますよ!
例えば、試験対策としては押さえておかなければならない「マクロ経済スライド」について、導入するメリットや当時の批判にはどのようなものがあったかなどが描かれています。
また、本書では主に次の2点について深く学ぶことが出来ます。
- なぜ賦課方式なのか。積立方式ではダメなのか。
- なぜ保険料方式なのか。全額税方式ではダメなのか。
試験勉強では当たり前のように理解し、そういうものなのかと受け入れている賦課方式や保険料の徴収についても、様々な議論・攻防がなされていることを詳しく解説されています。
こうした背景知識があると「年金科目はあまり好きじゃないなぁ」という方の助けにもなると思いますので、よかったらぜひ一度手に取ってみてください。
特に面白かった点
私が個人的に特に面白かった・楽しめた点を2つ紹介します。
国会での発言・議論が幾つも掲載してあり、面白い
国会における議員の発言などが紹介されています。
一見普通のことを言っていそうなのですが、本書の解説を含めて読んでみると、結構メチャクチャなこと言っているのだなというのが分かります。
何だか国民ウケ、マスコミへのアピール発言??と思えてしまうようなものもあり、なんでもかんでも鵜呑みにしてはいけないなぁと実感です。
各国との比較・検証に驚き!
本書の終盤に、多くのページは割かれていませんが日本と各国の社会保障に関する比較が行われています。
これだけ議論され、様々な施策が実施されているにも関わらず日本の社会保障・年金はまだまだ不足しているという事実に驚きました。
社労士試験で海外の話題といえば「社会保障協定の締結」に目がいってしまいがちですが、非常に勉強になりました。
おわりに
今回は「年金不安の正体」を紹介させていただきました。
年金について書かれている書籍は、社労士の勉強をしていなかったら手にも取らないですし、読んでもチンプンカンプンな内容が多いと思います。
しかし、1度は年金について学んでから本書を読んでみると「そうなんだ!」と思えることがたくさんあります。
簡単なテキスト感覚で読めてしまいます。
社労士試験の勉強はそれだけ大変なんだということですね!
ぜひ一度手に取ってみてください。楽しめますよ!