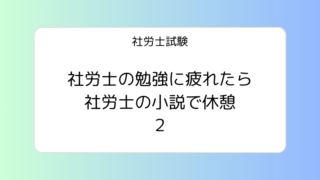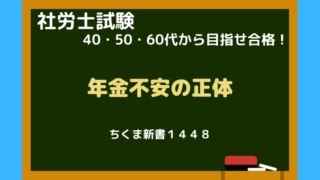社労士試験の休憩時間に読む小説 第3弾「希望のカケラ 社労士のヒナコ」文春文庫
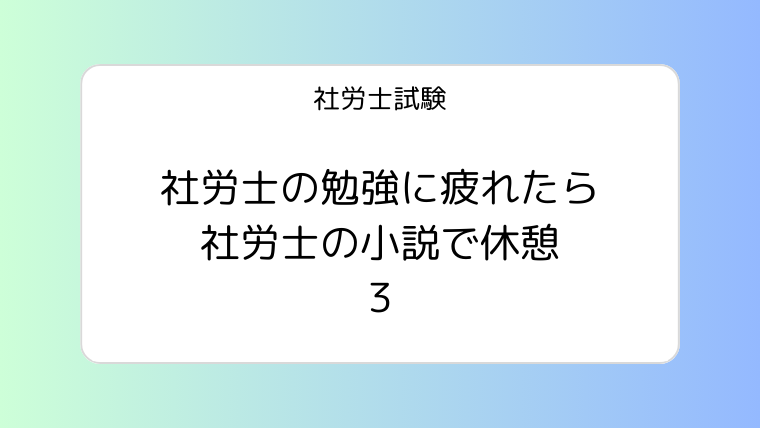
社労士を題材にした小説「ヒナコ・シリーズ」の第3弾の紹介です。
はじめに
社労士試験の勉強の合間に読むべき小説も3冊目になります。
今回も一気に読ませていただきました!
前回から主人公ヒナコは「社労士探偵」と私の中では認識されています。これだけ鋭い人でも社労士試験は3回目で合格のようです。やっぱり社労士試験は大変💦(たしか第一作でそう書いてあったような)
書籍の概要
今回ご紹介する書籍はコチラです。
希望のカケラ 社労士のヒナコ
文春文庫 2023年1月発行
総ページ数は323ページ(解説含む)で、前作より20ページ程減り、第1作目と同程度になっています。
作者は水生大海(みずきひろみ)さんです。
作者のプロフィールなどは以前の紹介記事をご覧ください。
本書はヒナコ・シリーズ第3弾ということで、社労士事務所に勤務している主人公ヒナコが4年目に突入したという設定になっています。(本書にまる3年経過と書いてあるのでおそらく4年目と思っています。)
1作目が1年目の話、2作目が2年目の話となっていましたが、今回は3年目というわけではなく、4年目です。
今回も2作目と同じく短編エピソードが5話掲載されています。
本書の設定はまだコロナが蔓延しているという設定ですので、マスクをつける・外すという記述が何回か出てきます。
最近はマスクをする必要がなくなった(義務ではなくなった)ので、こうした描写も何か懐かしい感じがします。さらに数年後にこの小説を読んだ方は「なんでこんなにマスクのことに触れられているのだろう」なんて思ってしまうかもしれません。
本作で取り扱われている社労士的な題材としては「助成金」「同一労働同一賃金」「労災の特別加入」「副業」「男性の育児休業」と、旬のネタが満載ですね!
第3作目の特徴
本書は取り扱われているネタ、事件?のもとになる制度が比較的新しいため、より親近感を感じるエピソードになっているなと感じました。
それに関連して、これまでのシリーズでも言えることではあるのですが、主人公の顧客として登場する各企業の悩みや対応も非常にリアルであるということが、このヒナコ・シリーズをより面白くしています。
本書においても「なんでもいいから助成金もらえるようにしてよ!」「育児休業は本当にとらせないとダメ?」といった話が出てきますが、これは小説に限った話ではありません。
法律に書いてあることなので守ってもらうしかないわけなのですが、「それでも受け入れられない」「何か抜け道は無いのか」「最終的には会社と社員の問題だろう」といったご相談・ご発言は私が社労士事務所にいた時も普通に聞かれることでした。
ヒナコ・シリーズでは顧客である企業が無理難題を言ってきても、それを主人公がしっかりと対応することで、企業におかしなことはさせないといった展開が多かったように思います。
しかし、実際にはもっとひどい場合もあります。
私が受けた相談でかなりインパクトの強かったものは、例えば「さっきクビを言い渡して、明日から来ないようにしたから、あと必要な手続きとかお願いしまーす!」という相談?というより、依頼もありました。(もちろん「了解でーす」とはなりませんが)
いずれにしましても、ヒナコ・シリーズは顧客の発言・言動にもリアリティがあるなと感じるところも多いので、これから社労士として活動していこうと考えている方にも非常に勉強になるのではないでしょうか。
独り立ちする・開業を考えている方は顧客目線でも読んでみることで、後々の業務にも活かすことが出来る点もあると思います!
本書を読む際の注意点
前回も同じことを書いているのですが、私は第1作目である「ひよっこ社労士のヒナコ」から順番に読むことを強くオススメします!
本書、第3作目の解説にはどこから読んでも大丈夫ですよ!といった記載もあるとおり、短編なのでどの話から読んでも「全く意味が分からない」ということはありません。
しかし、全体のストーリーを楽しむためにも最初から読んだ方がより感情移入して楽しめることも間違いナシです!
おわりに
今回は「希望のカケラ 社労士のヒナコ」を紹介させていただきました。
解説を読んでいると続編もあるのかなと感じさせてくれる記述もあるのですが、それはもう少し先になるかと思われます。
本書が発行されたのも2023年の1月とつい最近ですからね!

第4弾を楽しみに待ちつつ、第4弾にも旬のネタが取り上げられると思うので、ナニコレ?とならないように私も知識の吸収に励みたいと思います。
私が個人的に取り上げてほしいと思うネタは、社会保険関係、最低賃金法、派遣法、社労士法(悪徳社労士の登場)などでしょうか。
楽しみですね!!