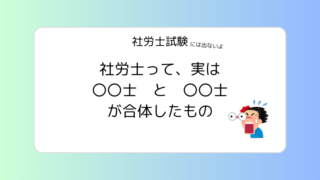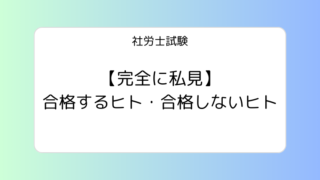社労士試験 あくまで私の経験上の話ですが、記憶定着には問題演習がオススメ!とにかく回転させましょう
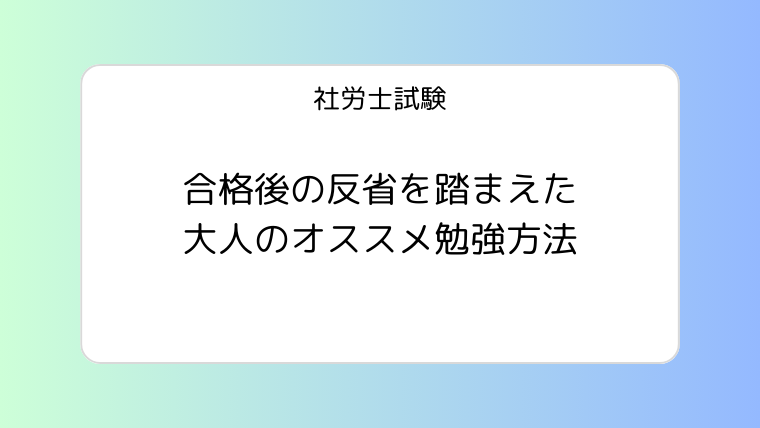
社労士試験で実力をつけるのは「問題演習」が大切だなと感じています。
様々な<こだわり>を捨てて、愚直に問題を解きましょう!!
勉強開始あるある
資格取得を決意した後に必ずやってしまうことってありますよね。例えば部屋の片づけであったり、勉強道具を揃える、参考書を買いあさるなどなど。それに加えて「最適な勉強法を探す・検索する」ってよくやってしまったりしていませんか!?
私も様々なサイト、体験談、書籍を読み漁り、色々と試してきました。でも、なぜかどれも長続きせず、「これは自分に合っているかも!」と思える勉強法に出会うことはありませんでした。
もっと言えば、自分に合っているということが体感できるほど続けることすら出来なかったというのが正直なところです。
結局、私が合格した年に行っていたことは「ひたすら問題を解く」です。あまりにも普通のこと過ぎて申し訳ないです。しかし、これが私にあっている勉強方法でした。
中高年あるある
細かいところが気になりませんか?
どこに書いてあるのだろう?根拠はなに?
これは仕事をする上ではとても大事な視点ですよね。
でも、社労士の勉強に取り込みすぎてはいけません!!
同年代の受験者数名と話したときに「あるある」と盛り上がったので、きっと思い当たる方もいるでしょう。
仕事をする上では「どこに規程されている?」「実際になんて書いてある?」ということを確認するのは大切です。
でも、社労士の勉強でそれを追求すると法律、政令、省令、通達など本当に細かいところまで追っていくことになり、大変です。時間が掛かりすぎます。
仕事をする上では「こうした場合も想定しておこう」「こーゆー場合はどうするんだ?」と様々なパターンを考えておくのは大切です。
でも、社労士の勉強ではそれを考え出すと、書籍を調べ、判例を調べ、インターネットで検索することになりキリがありません。答えが見つかるとも限りません。
社会人経験が長いとそうした気持ちが余計に湧いてくるでしょう。それは悪いことではありません!
しかし、そうした点を追求しすぎることが無いよう注意してくださいね。
探究心を抑えて問題演習です!!
気になる点があっても基本的にはテキストに書いてある範囲内に抑えましょう。
最適な勉強方法とは
最適な勉強方法は人それぞれとも言われますが、避けて通れないのはアウトプットです。
中高年の皆さんであれば、これまで業務に関する小難しい書類をいくつも読んできています。テキストの内容を理解するのであれば若者にもまだまだ負けていません!
でも、問題を解くというのは何年ぶり、何十年ぶりという方も多いのではないでしょうか。
間違えることを恐れず、気にせず、問題演習を取り入れましょう!!
ひたすら問題を解く
先ほどもお伝えしましたが、色々な方法を試した結果、私が取り入れた勉強方法は問題集・過去問等を解きまくるです。
試験まで残り2、3か月となるまではテキストを読み、問題を解き、気になる点は講義を聞きなおすという3点を漠然と進めていました。
しかし、いよいよ本番までの時間が無くなってきたときに、残りの期間で何をするのか、どの問題集を何回解くのかというのを決めました。結果的にこの「残りの期間で何をするか」を決めたことで自分にもエンジンが掛かり、この年の合格へとつながりました。
具体的に何をしたかですが、残り期間約2,3か月で
ということを必ずやりとげると決めました。ひたすら解くことを最優先にするため、補助ルールとして
・基本的にテキストには戻らない(問題集の解説をまるごと吸収するのを目標に)
・細かいことは調べない
・間違えても解説を読んだらどんどん次に行く
も徹底して守るようにしました。
直前期は一問一答ではなく、五肢択一の本番と同じ形式で解くべきという講師からのアドバイスもありましたが、その時は一問一答ができれば結果的に問題は解ける、スピードを稼ぐには一問一答しかないと判断し、過去10問題集を選択しました。
さて、私はこの目標を守ることが出来たかといいますと、結果的に過去10年問題集を10回転するという目標は果たせませんでした。7回転させたところでタイムアップです。
結局、7回転目でも間違える問題はありましたし、全てが身についたわけでもありませんでしたが、試験前日の16時頃に7回転目を全て終えたことはよく覚えています。
問題を解きまくったことで知識の定着度がかなり高くなったことに加えて、本番では嬉しいサプライズがありました。それは、問題を解くスピードが上がっていたということです。
1・2回目の択一試験では、時間ギリギリまで問題を解き、悩んだところを改めて考える、見直しをするといった余裕がほとんどなかったのですが、3回目の受験では、問題を解きまくった成果なのでしょうか、とりあえず全てを解き終わっても30分ほど時間の余裕がありました。それ以外にも本番では自分なりに工夫したことがありましたので、それはまた別の機会にお伝えしたいと思います!
いずれにしましても、私は問題を解きまくるというスタンスが自分に合っているようでしたので、勉強方法に迷っているという方がいらしたら、無心で解きまくるということもぜひ試してみてください。
テキストは間違えた内容の確認がメイン
問題演習を中心にする、テキストには戻らないといっても、テキストがいらないのかというとそういうわけではありません。
問題演習をした結果、全く分からない、何だったかな?と思うことは多々ありますので、パッと思い出せない場合はテキストの該当箇所に戻りましょう!
これは中高年の強みかなと勝手に思っているのですが、働いていて調べ物をする際にネットや書籍で必要なことだけを吸い上げるということはよくあると思います。
調べものをしているときに、該当する項目が出てくるまで最初のページから読み進めるということはあまりありませんよね。必要なことだけを調べて、どんどん次に進むということを仕事では普通にやっていませんか??
これはこれまでの経験や知識を総動員して、考える力、推測する力がより磨かれているからこそできるものです。
勉強も同じだと思っています。勉強初期は特にテキストへの依存が高くなってしまうのは当たり前のことですが、徐々に問題集、アウトプットを重視していくことが大切です!
私がうまく活用できなかった勉強方法
さて、ここからは私にとってはあまりしっくりとこなかった、効果が出なかった、効果の有無を判定する以前に長続きしなかった勉強方法を紹介したいと思います。あくまで私には効果が無かったというだけですので、ご参考まで。
テキスト読み込みだけ
テキストを何度も頭に沁み込んでくるまで読むべし!という本を読んだ影響もあり、ひたすら何度も読むという方法を試したことがあります。
書籍で推奨されている回数までたどり着くことが出来ませんでしたので、本当の効果は分からないのですが、そもそも推奨されている既定回数を達成することが出来ませんでした。まず眠くなります。ひたすら読むだけなので、睡魔との戦いです。内容よりも睡魔とどう戦うべきかということの方が記憶に残っています(笑)
次に、問題を解いている時と比べて、余計なことを色々と考えてしまいます💦
読んでいるだけで大丈夫かなぁ、あれもやらなくちゃなぁ、お腹空いてきた、明日はあの仕事もやらなくちゃ、もうすぐあのゲーム発売されるなぁなどなど。そんなことを思いながら読み進めているので、全く頭に入っている気がしませんでした。
ただただ字を目で追っていることに気が付いたため、このテキストを読むだけという勉強方法は中止させていただきました。
ひたすら書く
いわゆる書きなぐりです。
実は高校受験の時はこれで成功した経験がありましたので、社労士試験もこれで突破しようと思い試したものの、全くうまくいきませんでした。
覚えたいことを何度も書き、脳に刻み込もうとしましたが、結果としては「今日も書きまくったー」という満足感だけでした。
また、青ペン記憶術といったタイトルの本も読み、実践してみましたが残念ながら私には効果がなかったようです。高校受験の時はうまくいったので、これで大丈夫と思ったのですがねぇ。
中学生の時に行っていた手法をそのまま行っても40代の私には通用しませんでした。
ただただ読むというのに比べれば手を動かしていますし、眠たくなってしまうといったことはありませんでしたので、ある程度続けていればもしかしたら効果があったかもしれませんが、とても時間がかかるというのも難点です。
思い返してみれば、中学生の時に書きなぐっていたのは公式とか英単語でしたので、比較的短い内容のものであれば効果はあると思います。社労士試験で言えば、雇用保険の基本手当の所定給付日数、健康保険の高額療養費制度における1か月の限度額算定式などには効果があったかもしれません。
自分の肉声でインプット
目的条文の暗記などに対しては自分の音声で録音し、それを聞き流すといった方法が推奨されていましたので、試してみました。
Youtubeなどでもナレーターの方が読んでくれているものなどがありますが、自分で読むことで、ここは読みづらかったとか、ここはあまりしっくりこない内容だったという感情が加わりますので余計に記憶に定着するといった効果も期待できるようです。
なるほど、言われてみればそうかもしれませんので、私も試してみました。
やると決めたら、まずは形から入るというのが私の悪い癖ですので、買いましたよスマホ用のマイクも。久しぶりに探してみたらSHUREという会社の「MV88」という機種でした。
これを装着して覚えたいことを録音していると、プロ感も加わって、俄然やる気がみなぎってきます!しかし、肉声インプット方式でも思わぬ罠が待っていました。
録音するときの自分の読み方が気になってしまい、その修正にこだわってしまうのです。
もうちょっとスピードを速めよう、抑揚をつけよう、嚙んじゃったからやり直し、声のトーンをもう少し高くしようなどなど。どこにこだわっているのだという感じですが、気になるものは気になります。時間ばかりが経過していくので中止です。
運動しながら勉強
座っているだけじゃダメ!五感をフルに活用しよう!!これもよく言われていることですよね。
私の場合、活用の仕方が間違っていたかもしれませんが、立って勉強してみたり、部屋の中を歩きながら勉強してみたり、筋トレしながら講義を流したりしてみました。
これも眠気防止のためにたまにやるのはいいかもしれませんが、メインの勉強方法としてはあまり適していないと判明しました。
今は昇降できる机などもありますので、それを活用すれば良いかもしれませんが、私はそんな机は持っていませんでしたので、前かがみの体制が続き、手元の教科書の距離も長いので字が読めません。ただただ勉強しづらいだけです。
一方で歩いている時も文字は読みづらいですし、筋トレしていれば「つらい」という感情が最優先ですので、講義内容など全く頭に入ってきません。
通勤時間に耳で講義を聞くくらいが座っているとき以外の勉強方法としては限界でしょう。
カフェで勉強
これは私には合わなかったというだけですので、あくまで私見です。
カフェで勉強している方はたくさんいらっしゃいますし、雑踏の中での勉強はある意味、試験会場に近いとも言えます。私がカフェでの勉強で気になってしまったことは、
・机が狭い
・飲み物の水滴がテキスト等に垂れるのがイヤ
・周りの会話がより聞こえてきてしまう
・お金がかかる
の4点です。
さすがに毎日行くとなるとそれなりの費用もかかりますし、何気なく流れているBGMも気になってしまったり、他の方の飲食中の音が気になったり、集中しているようで集中できていない時間も多かったです。
2,3時間も滞在しているとさすがにそろそろ出ないとダメかなとも思ったりして、次の店に行けばまた出費も増えてしまいます。
自宅のような誘惑が無いのですぐに勉強に取り掛かるというメリットはありますが、カフェでの勉強は金銭的に断念しました。
自分に教える勉強方法
人に教えることが出来てこそ、身についている証拠。
なるほど。
社労士の講義を聞いていても、先生が膨大な知識や細かい数字を間違えることなく話せるのは、毎日のように教えているからなんだろうなーと思うようなってから、自分に教えるという勉強方法が効果的なのではと考えました。
テキストを持ち、立ち上がり、目の前に存在しない生徒を想像して、私の講義が始まります。
これ、ただテキストの朗読を先生風にやっているだけですよね・・・。
ホワイトボートの小さいものもありましたので、それを壁に掛けて「ここ重要だぞー!」という演技も試しましたが、紙に書いているのと一緒です。
自分に教えるというのは、理解しているかを確認する、覚えなくちゃいけないことを空で言えるかを確認するということですね。
社労士試験に長々と丸覚えが必要な内容というのはあまりありません。教えるというよりは、思い出せるかを確認するだけで十分でしょう。教えるスタイルは時間と労力がもったいないと思いました。
赤シート・緑シートの活用
社労士試験の1回目に失敗した私はあまりにも悔しすぎて、壮大なリベンジ計画を立案しました。
テキストに書いてあること全部覚えれば、ほぼすべての問題に正解することが出来るので、それが手っ取り早いし、確実な道であるだろうと思い「よし、全てを覚えよう!」と。
そこで、テキスト全てを赤シート、緑シートを使って塗りつぶしました。
今は昔と違って、暗記用のペンにも赤色、ピンク色、青色、緑色があるんですね。赤やピンクで塗りつぶした場合は緑シートを被せればその部分が見えなくなり、青や緑で塗りつぶした場合は赤シートを被せればその部分が見えなくなります。
重要な単語などは赤、ピンクで塗りつぶし、それ以外の部分は青や緑で塗りつぶしました。単語を覚えているかの確認と単語の意味が説明できるかの確認を、シートの色を変えるだけで可能としたのです。
そのためにチェックペンの箱買いし、ひたすら塗りつぶしました。結果は大失敗です。塗るだけで時間が掛かりますし、シートを被せない状態でのテキストは読みづらくて仕方ないのです。
労基法のテキストだけは見事に全てを塗りつぶしましたが、それだけで止めました。せめて重要単語だけにしておけばよかったのですが、それなら選択式の問題集を活用した方がよっぽど効果的です。
絶対にマネしないでください。しないか。
終わりに
私が試した勉強方法について、思い返せることを記載してみました。
こうしてみると、私は最初のやる気とやり始める行動力は褒めてあげたいですが、長続きもせず、本来の主旨とは違うところでこだわってしまう傾向があるのかもしれないということに、改めて気づかされました。
もしかしたら「問題集をひたすら解きまくる」以外にも続けていれば実を結んだ勉強方法もあったかもしれません。
しかし、続けられることができた勉強方法もそれだけだったということですので、自分には問題を一心不乱に解くというのが正解だったかと思います。
皆さんも勉強方法を取捨選択して、続けられそうなものをぜひ見つけてくださいね。