社労士試験 六法(法令集)は必要か!?
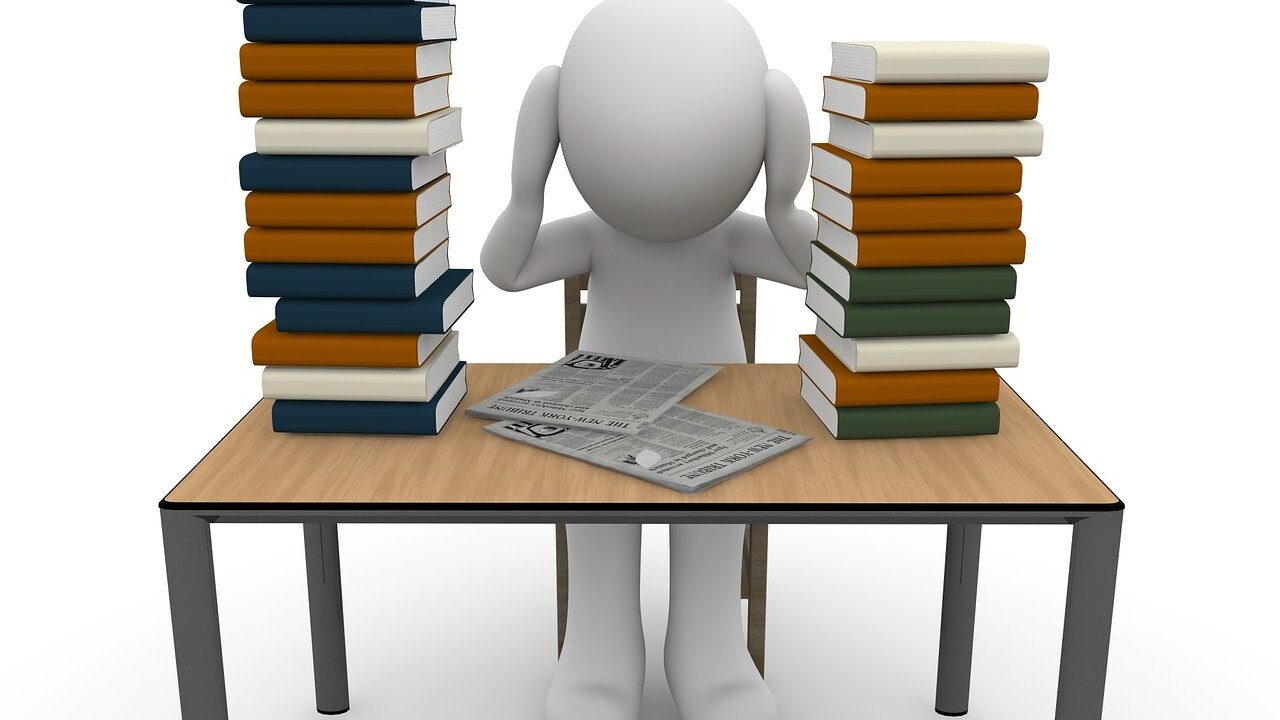
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社労士試験対策として「六法(法令集)は必要か!?」に関する記事となっています。
社労士試験の勉強に六法は必要なの?とお悩みの方はぜひ参考にしてみてください!
六法(法令集)は持っていてもいいと思います!
社労士試験の勉強をしていると、ふと法律の条文を見た方がいいのかなと考えてしまう時ありませんか?
私も1回目の試験で落ちてしまった後、2年目の勉強を始めるにあたり資格学校の先生に相談したことがあります。結論は「必要ない」とのことでした。確かに社労士試験では条文を引用することもありませんし、条文番号が出てくるとすれば問題文に書かれている場合だけですが、「○○法第××条と照らして正しいか?」といった聞かれ方はしません。
そのため基本的に法令集は必要ありません。
しかし、私は講師のアドバイスに従わずに手元に法令集を持っていました。
頻繁に活用したというわけではありませんが、1冊持っておくのもいいかなと思っておりますので、その理由をお伝えします。
とにかく合格あるのみ!合格までには1秒たりとも無駄には出来ないという場合はオススメしませんので、条文を見ている時間があったら1問でも多く問題を解くようにしてください。
法令集の所有をお勧めする理由
私が法令集を持つことをお勧めする理由は以下のとおりです。
直接合格に結び付くかと聞かれてしまうと、寄り道・回り道となってしまうかもしれません。
しかし、大人の勉強方法としては有用だと思います。記憶の定着にも役立つ内容ですので、「それいいかも!」と思った場合にはぜひ導入してみてください。
意外と知らない!?法律の正式名称
法律の名称は結構長いものもありますので、講義などでは大抵省略された名称が使われますよね。もちろんテキストには正式名称がでているでしょうが、あまり気に留めてみることはありません。
省略された名称しか知らなくても試験で困ることはほぼないと思います。しかしながら、名称を知っているだけでイメージが膨らむこともあります。
例えば、有名なところでは「派遣法」でしょうか。
ハケン法、ハケン法と講義の中では呼ばれていると思いますが、実際、派遣社員さんについて何が定められているのでしょうか。
「派遣法」の正式名称は、、、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。
これだけでもイメージできることありますよね!法令集をパラパラっとめくっているだけでも、そんな発見があります。
正式な書きぶりもたまには刺激になります
講義を聞いていてもよく分からない内容があったときに、解説聞いても分からないのに原文は何て書いてあるのだろうかと疑問に思ったことありませんか?
私は結構そう思う時があって、法令集を購入したきっかけでもありました。
実際に法律自体を読んだことでスッキリ分かるという経験は少ないかもしれません。
しかし、テキストではまとめて分かりやすく書いてあることも、原文はこんか書きぶりなっているのか!と思うこともあります。
労基法には賃金支払5原則(4原則)が出てきますが、私は第〇条第1項:通貨で支払え、第2項:直接支払え、第3項:全額支払え~といった書き方がされているものだとずっと思っていました。
でも、実際は同じ条項の中に「通貨で、直接、全額払え!」って書いてあるんですよね。
そうしたことへの気づき・発見も記憶を構築するのに役立つのではないでしょうか。
法律の全体像・構成を知ることで新たな発見があります
一般常識ではかなりの頻度で登場してくる法律に「労働契約法」があります。
単発で講義がある法律でもないのでなかなか印象に残らないですよね。
皆さんが社労士試験に合格後、「特定社労士」に挑戦しようと思った場合には避けては通れない法律なのですが、社労士受験の時には「何なのコレ?」と思っていました。
もし同じように感じている方がいたら、ぜひネットで検索でもしてみてください。
この法律、実は全部で21条しかありません。
何かそれを知るだけでも対策できそうだなって思いませんか。
そんな気持ちで法令集を見ていると、
労災とか雇用保険法って何条まであるの?
一番最初は目的条文って決まっているけれど、一番最後って何が書いてあるの?
なんて興味が沸いてきませんか。
そんなことを思うだけでも、勉強への気持ちが高まってきますので、勉強に疲れてしまった時は軽い気持ちで法令集を見てみるというのもありですよ。何となく勉強している気にもなれます(笑)
用語の意味を知ることが出来る
テキストには用語の説明も詳しく書いてありますので、あえて法令集で調べることはありません。
しかし、法令集は余計な解説など無く、事実だけが淡々と書いてありますので、テキストでどこだっけ?と探す場合よりも早く見つかることもありますし、無味乾燥に書かれた条文の方がしっくりくることもあります。
また、法律によっては「用語の定義」が第2条や第3条あたりにズラズラと書いてあるものもありますので、そうしたところだけを眺めてみるのもたまには有用だと思います。
判例を読むと面白い(読みすぎないように)
もし法令集を買ってみようと思った時に「判例六法」など裁判例がついているものを購入する場合は要注意です。
本来の勉強を忘れて読みふけってしまう場合があるからです。
さらに労働関係や社会保険関係ではない一般的な判例六法ですと、民法や刑法などの判例が大量に掲載されています。理解できない内容も多いですが、たまにそうなんだーと思ってしまう内容があるので、ついペラペラとめくってしまうことがあるんですよね。
これも中高年になり、そうした内容に耐性がついてきたというのもあるかもしれませんが、ハマってしまうと危険です。
社労士試験という観点からしますと、判例の内容が出題される場合もありますし、テキストに記載されている判例の概要を知ることもできますので「これ面白そうな判例だな」と思った場合などは、法令集を眺めてみるのもいいと思います。
長時間読み込んでしまわないようご注意ください。
おススメの法令集
法令集は社労士試験に挑戦している中で必須アイテムではありません。しかしながら、中高年の皆さんはそれなりのご経験もあるため、上手くご活用いただければ知識の定着にも役立つのではないかと思います。私が購入した中で、買ってよかったと思った法令集を2冊ご紹介させていただきます。
1冊目は「労働関係法規集」です。
労基法を始めとした労働関係の法令が掲載されています。社会保険に関するものは掲載されていません。非常にコンパクトで、字も割と大きめですのでパラパラと眺めるのには最適です。なお、こちらの書籍は特定社労士の試験の際に活用されている方が多数いらっしゃいました。
労働関係法規集(2023年版) [ 労働政策研究・研修機構 ]
2冊目は「判例六法」です。
こちらも社労士試験に関連する法律としては労働法関係しか記載されていませんが、テキストに載っているような有名な判例についても記載されています。加えて、一般的な法律もたくさん載っていますので、眺めていても飽きることはありません。
ただし、字が小さいです。私も眼鏡を外して読まないと・・・(笑)
|
|
おわりに
以上、私が法令集を持つことをお勧めする理由となります。
直接、勉強の成果につながるものではないかもしれませんが、行き詰ってしまったときや勉強に飽きてしまった時などに気分転換で開いてみるのもいいと思います。
特に中高年の方でしたら、業務に関係する法律や会社内部の規程などにこれまでも触れた機会があると思いますので、その経験を活かして法律自体を見てみるのもおススメです。
あくまで試験に受かるための勉強に直結しているわけではないことをお忘れなきようお願いいたします。












