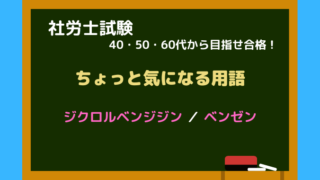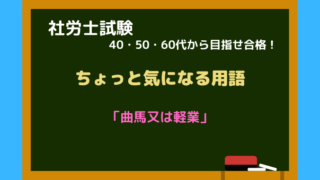社労士試験 「日本の年金」岩波新書
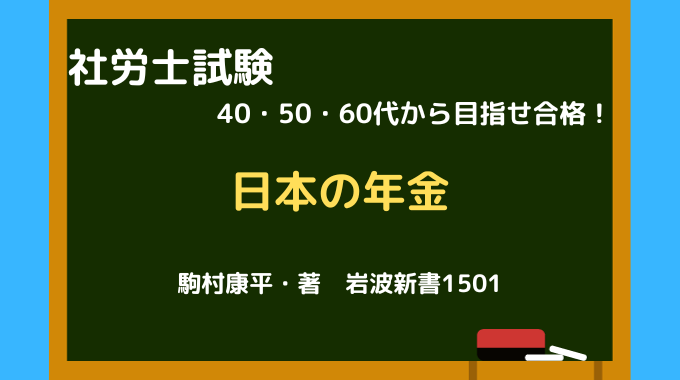
タイトルがそのまま過ぎて、読んでみたくなってしまい、わざわざお取り寄せした本になります。
はじめに
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社会保険関係にもう少し強くならないといかんと思い、最近は様々な書籍から知識の吸収に努めています。
タイトルだけですと、まさしくズバリな本ですが、さてさて中身はいかがでしょうか。
書籍の概要
総ページ数は259ページです。
著者は駒村康平(こまむらこうへい)先生です。
書籍に記載されているプロフィールによりますと、2007年から慶應義塾大学の経済学部教授となっています。(現在は教授をされているのかは分かりません)他にも厚生労働省の顧問をされていたこともあるそうです。
本書は2014年発行ですので、今読むとかなり古い内容になっています。そのため、もし読んでみたいという方(特に社労士受験を視野に入れている方)は、出てくる数字などはほぼほぼ気にすることなく、参考になるところだけ読むようにしなければなりません。
本書の目次は以下のとおりです。
- 序章:年金制度を取り巻く状況
- 1章:年金制度は、いま
- 2章:年金制度が直面していること
- 3章:これからの年金制度
- 終章:今後の社会保障制度を展望する
約10年前に書かれている書籍ということを考えると、答え合わせをしているような感覚にもなりますね!
本書は年金の細かい制度についての記述はほとんどなく、主に年金の歴史、問題点、諸外国の状況等について詳しく学ぶことが出来る内容です。
かなり突っ込んだ内容で、あまり聞いたことのない用語も出てきますので、これまでに読んだ年金に関する新書と比べても難しい内容ですが、そのぶん学ぶことも多かったです。
また今の年金に関する書籍ではあまり触れられることのない内容、例えば厚生年金基金、年金記録問題などについての記載も割と豊富です。
残念ながら社労士試験には縁のない話題が多いですが。
特に面白かった点・勉強になった点
私が個人的に勉強になった・初めて知った・面白かったなという点をいくつか、簡単に紹介させていただきます。
複雑な基礎年金の財政
既に年金の財政を学んでいる方はそんなの知っているよという話なのですが、厚生年金加入者の保険料の中には国民年金保険料も含まれています。
そこから基礎年金の分として「基礎年金拠出金」が拠出されるという仕組みになっています。
こうした仕組みは勉強していないとなかなか知ることのない知識ですよね。このことをうまく例えているなと思う表現がありましたので、紹介します。
山の斜面に立地し、古い建物を残して増築をくりかえした旅館に行くと、自分が1階にいるのか2階にいるのか、わからなくなる。本館の2階が新館の1階だったりする。古い制度をそのままにして建て増しをした年金制度は、同じような複雑な構造になっているのである。
日本の年金・駒村康平
いかがでしょうか?うまいこと例えるなーと思いませんか!(笑)
障害者向けの所得保障制度は各国で異なる
日本の障害給付の受給率は諸外国に比べると低いそうです。
その要因の1つに障害の概念が異なるということにあるようです。
日本では障害の程度がどれくらいか、それによって日常生活がどれくらい制限されるかという観点で需給の有無や金額が決められます。医学的には「機能障害」がどの程度かということで決まります。
一方、外国の多くでは障害の概念を「労働不能」の程度と、それによってどれだけ収入が低下したかといった点から障害年金の給付を行うようなのです。
もちろん「労働不能」という基準を用いた時にもそれなりに問題があり、詳細は本書を確認してほしいと思います。
それにしても「確かに!そういう見方もあるよなー」って思いませんか?
賦課方式と積立方式
他の書籍でも賦課方式と積立方式の解説がなされていますが、本書でも賦課方式が適しているという分かりやすい説明がなされています。
実際に世界各国のうち、積立方式を行おうとしたが挫折した国、積立方式を採用したけれども賦課方式に戻した国などの紹介もされており、結局は賦課方式に落ち着くのかなということを認識することが出来ます。
スウェーデンでの年金改革
諸外国の話が続いてしまっていますが、それだけ本書の内容が勉強になるということでお許しください。
スウェーデンでは一度年金改革に失敗し、その経験を活かして再度改革に取り組んだそうです。
その際に、「年金制度を短期的な利害調整や政治的にパフォーマンスに使うべきではない」という共通認識を与野党が持ち、年金改革を政争の具にしなかったそうです。
これは見習ってほしいなと純粋に感じてしまいました。年金に限らずの話ですけれどね。
おわりに
今回は「日本の年金」を紹介させていただきました。
ここでは紹介しておりませんが、みんなが大好きなマクロ経済スライドの話やGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の話なども詳しく、分かりやすく書いてありますのでテキストを読んでもしっくりこないという方は勉強の合間に一読するのもいいと思います。
ただし、比較的記載されていることが難解な箇所もある(私もサラーっと流し読み)、いかんせん情報が古いという欠点もありますので、もうちょと軽く全容を把握したいという方には以前にオススメした「知らないと損する年金の真実 」などをお勧めします。
年金関係はどうしても得点源にしなければなりません。どうしても苦手という方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ様々なアプローチをしてみてください!