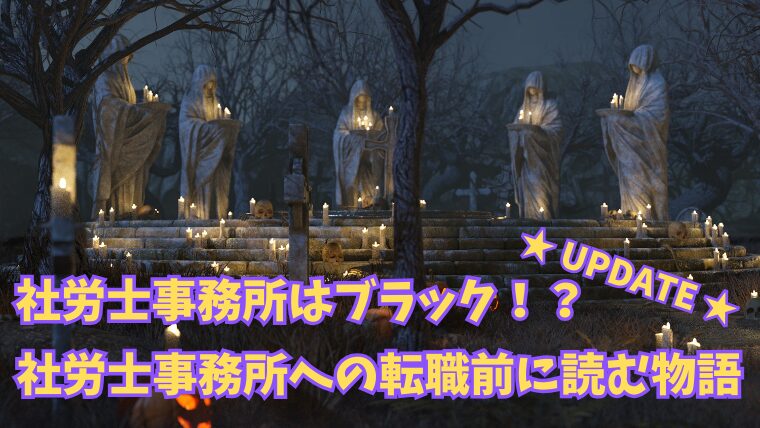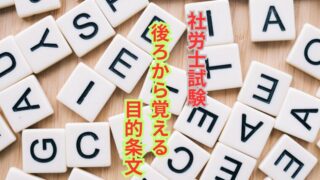社労士試験へのチャレンジをきっかけに、社労士事務所への転職を考えているという方も多いのではないでしょうか?
私もその1人でした。
しかし、今は安易に社労士事務所へ転職しなければよかったなと反省しています。
これから社労士事務所へ転職しようという方の夢を壊すつもりはありません。
が、私のような失敗をすることのないよう、参考までに私の体験を紹介させてください!
序章
こんにちは!オレの名前はワタル。
44歳で実務未経験ながらも社労士事務所への転職という偉業?を成し遂げ、そしてわずか1年で退職したとんでもない男だ。
普通に考えれば「その年齢のくせに1年で退職?」、「我慢が足りないんじゃない?」、「何やらかしたの?」、「周りに迷惑じゃん」と言われてしまいそうだけれど、そんなの気にしていない。気にしていられない。
なぜって、退職しないと身も心もズタボロになりそうだったから・・・。
第1章 試験合格後も変わらない日々
社労士試験の合格率は約5~7%。
つまり20回受ければ(5%×20回=100%)どこかで受かるんじゃない?という謎の理論を励みに、必死に問題を解いていた私は奇跡的に3回目の受験で合格することが出来た。(救済されたけど)
それは嬉しかった。「神様、仏様、厚生労働大臣様」と毎日のお祈りを欠かさず、ひたすら救済されることを夢見ていた成果である。(どこを頑張っているんだ!)
当時は、とある企業の経理部門に所属していたため、社労士試験に合格したことを伝えるとともに人事・労務関係の部署への異動願を出した。社内に社労士資格保持者もいなかったため、次の異動時期には希望が叶うだろうと安易に考えていたが、世の中はそんなに甘くない!
異動希望を含めた1年間の振り返りを行う上長との面接において、ありがたいお言葉をいただいた。
「なんか社労士って、大変な資格取ったんでしょー、何する資格??」
えぇぇぇ、おいおい、総務課長。それくらいは知っておいてくださいよ。いくら顧問の社労士と接点があるのはあなたじゃなくて人事課長だからって、それは無いでしょ。
社労士の知名度はまだまだなのかなと少しガッカリ。
イヤな予感はした。そして的中した。その年の異動は想定外にかなわなかったのである。
いま思えば、これも「社労士業界とは縁が無いよ」というお告げだったのかもしれない。
その後も事務指定講習の受講、社労士会への登録&セミナー受講など人事・労務業務に携わるべく、勉強を続けた結果、合格から約2年半後に晴れて人事部へ異動したのである。
第2章 人事部でも変わらない日々
人事部への異動を機に学んだことをフルに活かしたいと希望に満ち満ち満ち溢れていた。
しかし、残念ながら異動後も学んだことを活かせるような環境には無かった。
結局、このままだとせっかく取得した資格を活かす場が無いなと感じたことが社労士事務所への転職を決意させることになる。
この決意が後の大悲劇を生み出すことになるのだが。
異動先である人事部はいくつかのセクションに分かれていて、オレが所属するのは採用、規程改正、人の異動及び評価を行うセクションだった。
一方で人事部を牛耳っているのは出退勤管理、有給休暇などの各種申請、労働保険・社会保険を担当している管理セクションの奴らだ。
「社労士の試験に合格したらしいじゃん、すごいねー。でも、実務は何も知らないんでしょ」
異動後すぐにマウントを取ってくるこの態度。グイグイくるよねぇ、見習いたいくらいですわ。
ある日、就業規則の改正を担当することになった。これまでに勉強してきた知識も使って、しっかりしたものを作りたいと思っていたのだが、ここでも主導権を発揮するのは管理セクションの奴らだ。
「ここをこう修正して、あそこは○○ができるようにして」など、全ての指示は管理セクションから行われ、それをいかに分かりやすく、キレイに書ききるかが私の業務となった。人事担当?社労士?いやいや、ただの文書作成担当やん。
規程の中で使われる独特の言い回しなども含め勉強になることが多かったが、規程の中身には法律で定められている内容を逸脱しているものも幾つかある!
それはさすがにダメでしょいうことで指摘をすれば、いつも返ってくる言葉は「それだと現場はまわらないんだよ!」の一言。
はい、出ました!最強フレーズ。確かにね、会議室じゃなくて現場が大切ですよ、分かっていますよ、そんなことは。それなら規程を改正する前にその点も解決しておいてよって話でしょうが。
仕方ない、ここは顧問社労士から一発ガツンと言ってもらうしかない。
「●●先生、お世話になっております。××の件なんですけれど、明らかに違反しているので、先生からも言ってもらえませんか?」
「ワタルさん、その件は管理セクションの方に私どもからもお伝えしました。あとは最終的にどうするかは御社の内部の問題ですので・・・。」
えー!?
そりゃ、分かりますよ。言っても聞いてくれないクライアントにはどうしようもないですよね。分かるけれど、せめて、もう少しオレの話に同調してくれてもいいんじゃない?(笑)
そんな業務、仕事の進め方が続く中で、オレは「社労士事務所へ転職して、経験を積むとともに正しい形で寄り添える社労士になりたい!」という思いを強くしていた。
いや、強くしてしまった。
第3章 転職のため!?特定社労士へ変身
せっかく資格を取得しても活かす道が見つけられなかったオレは社労士事務所へ転職しようと漠然と考え始めた。
いや、しかし、40代で実務経験のない冴えない男を雇ってくれる社労士事務所なんてあるのだろうかという至極まっとうな疑問が頭を過ぎる。
やれる範囲で自分を高めるしかない。
今まで避けていたけれど、「アレ」に手を出しますか、使い道があるのかも分からないけれど、知識の向上、チャレンジしているという姿勢はアピールできるだろう。万が一にも合格すればステータスUPにもつながるし、経歴も少しは膨らむ。
そんなわけで「特定社労士」の受験を決意。
安易な理由で始めた特定社労士への道、結果的には受講してすごく勉強になったし、何より楽しい!社労士の勉強は学校にも通っていたにもかかわらず3年間、誰とも友達にならなかったオレはグループで学ぶことが何より楽しかった。出会った仲間も本当に素晴らしい人ばかり。
グループ内の半分くらいの人は開業社労士。「みんないい人だし、誰か雇ってくれないかな」と思いつつも、さすがにそんなこと口には出せず、夢みたいな展開にはならなかった・・・。
特定社労士受験の詳しい話はまた別の機会に。
結果として、特定社労士は合格基準点ピッタリで合格することが出来た。つまり合格者の中では最低点だったわけだが、そこは気にしない。ちなみに簿記2級も合格点ピッタリ、社労士試験自体は救済適用と全てがギリギリの自分に乾杯!
これで満を持して転職活動に拍車を駆けることが出来る。準備は整った。
転職市場へ殴り込みじゃ!!!
第4章 ツラすぎる。40代の転職活動
転職活動4回目ともなると履歴書・職務経歴書の作成などはチョイチョイと綺麗な言葉を並べることが出来るようになってしまう。
問題は面接だなと考えていたのだが、さすが人事・労務ほぼ未経験オジサンのことを暖かく迎えてくれる事務所はなかなか見つからなかった。自信を持って作成した書類がまず通らない。
いや、チョチョイと作成なんて書いたけれど、陰では必死こいて作ったんですよ、履歴書と職務経歴書。お願いだから読んでくれー、チラっと見るだけでもいいから!
でもね、通らない。全く通らない。
そうだよね、40代・未経験・頭髪も怪しくなってきた・辛いもの食べると病的に汗かく・趣味はゲームと海外ドラマ・甥っ子姪っ子可愛すぎる!なんてオジサンに興味示してくれる会社ないよね。
結局、20社くらいに応募して書類が通ったのは3社しかなかった。社労士事務所の求人は思いのほかたくさんあったけれど、さすがにこちらにも譲れない条件がある。収入と勤務地は選びたい。(まぁ、最初に選ぶ理由はそれくらいしか無い)
3社のうち1社は本当にキレイなオフィスで代表者もスマートな感じの方だった。ここでぜひ働きたいと強く思ったのだが、残念ながらお断りされてしまった。
2社目は面接も淡々としていて、1社目ほどの魅力を感じなかった。そんな気持ちが面接中に出てしまったのか!?あえなく撃沈である。あの時は面接をつまらなそうに受けてしまい、本当にゴメンなさい。
そうなると、3社目は必然的に気合いを入れていくことになる。せっかくの面接の機会を2回もダメにしているのだ。これまでの面接の反省も踏まえ、やる気マンマン、これまでの経歴も控え目かつ誇りを持って、ちょっと話を盛りつつ自慢。
話は脱線するけど、オレの友達に面接大好き、大得意な奴がいる。面接まで行くとほとんど落ちたことが無いらしい。彼が教えてくれた面接の極意をせっかくなので披露しちゃおう。
「面接ほど自分のことを好き勝手に自慢できる場は無い」
そーゆー気持ちで面接に臨んでいるのか!うまく出来たかは分からないが、3社目の面接ではこれまで以上に自慢した。自分でも恥ずかしくなるくらいだ。
面接終了後、帰り道にメールが。
「明日、事務所に来られますか?」
うぉぉぉぉぉー、これはとうとう乗り切ったのではないか!
面接官であった事務所代表者も話しやすかったし、未経験でも大丈夫、しっかりと成長してもらえるように業務を配分しますといった話までしてもらったし、これは期待大。オレも面接を受けながら、ここならやっていける!!と思っていたんすよ。相思相愛じゃないですか。いやー、生きているといいこともあるもんだ。
翌日、ありがたく内定をいただきました。
ありがとうございます。本当に嬉しかったです!
うん、まあ、今思えば悲劇の始まりだったんだけどね。。。
なんで内定くれちゃったんだよ、くれなきゃよかったのにー。
第5章 不安だらけ。もっとワクワクさせてよ。
内定をもらってから入社までは約1か月半の日数があった。
その間にも働き始める社労士事務所とは何度か接点があったのだが、実はこの時に多少の違和感を感じていた。
1つは課題図書が与えられたこと。
課題図書が与えられること自体は未経験オジサンを雇ってくれるのだし、当然かなと思ったけど合計3冊、しかも自腹っすか。1万円以上しますけど。3冊で1万円だから、それなりに分厚い専門書も入っている。
もう1つはワタルさんの成長ルートなる資料をもらったこと。
これも普通に考えると「オレのことを真剣に考えてくれている!」と喜びたくなる話なのだが、問題は中身ではない。資料の作りだ。
世の中にパワーポイントが認知されてきた時代に作られていたような、ステキな資料。
ボックスからはみ出る矢印、とにかく色を使いたい気持ちが溢れ出ていて、図形同士の高さやバランスも微妙にバラバラ、どこで改行しているのよという文字の配列。
とにかく古き良きパワーポイント。確かに昔はこれでも「パワーポイント使えるんだ!」と言ってもらえた時代もあったよね。うんうん、分かるよ。でも、逆にいまこれを貰ってしまうと不安しかないよ、オレは。
ここで気づいておけばよかったよ。
いや、気づいていたんだよ、でも目をつぶっちゃったよ。社労士として働きたかったから。
一抹の不安を抱えながら、とうとう勤務初日を迎えることになる。
第6章 社労士事務所は黒色という噂
初日 ~ようこそ我が国へ~
オレが就職した社労士事務所は規模は小さく小さな貸しビルの一室。
従業員は所長1名、先輩社労士2名、事務職員5名だ。そこにオレが加わり総勢9名体制となった。
転職を何度か経験しているが、これまでの職場で最も小規模だったのは従業員50名ほどの組織であったため今回の社労士事務所はその記録を更新した。
小規模だからこその良さもあるだろうなんて安易に考えていた。しかし、人が集まればそれはどんな規模であろうと、対立・嫌悪が生まれてしまうようだ。ここも例外ではない。
初日からひどくギスギスした雰囲気が伝わってくる・・・。
勤務初日、簡単に自己紹介を行い先輩社労士からレクチャーを受けていると、所長がやってきた。そこで場の雰囲気が一変する。全員、即座に起立する。
えぇー、コレ毎回、所長が来るたびに起立するの?大会社の社長ならまだしも、ほぼ毎日顔合わせるわけでしょ。!?しかし、所長は「座ってください」と言った。それはつまり、「一度は立ってください」という言葉の裏返しだよな。
その後、所長からのありがたいお話が始まった。途中の区切りのよいところでは大きな声で「ハイ!」という反応を示すことになっているようだ。まるで小学生のホームルーム。話の最中に意見を求められることもある。そこで職員から述べられているのは所長への賛同と尊敬の念を伝える言葉。まるで宗教のようだ。
これがオレの社労士事務所勤務初日、午前中の出来事。
やっちまった。完全にやらかした。むしろ騙されたと言いたい。
転職に関連するネット記事などを見ていると「アットホームな職場です」という言葉には要注意!!というアドバイスが掲載されている。これは紛れもない事実だ。確かに掲載されていた。そして全くアットホームではなかった。
ここでは社労士事務所という名の下、所長による独裁国家が構築されている。
それがオレの初日の感想。ちなみに、勤務初日からガッツリ残業したのも、転職5社目にして初めての経験だった。
2日目以降 ~響き渡る怒号・罵声~
社労士事務所への転職を考えている中で避けては通れない話題、一度は目にしてしまうのが「社労士事務所は黒色だからやめた方がいい」という話。
それは矛盾でしょ。だって、黒色企業を認めませんよという法律を学んできた人が開設した事務所が黒いわけがない!
と、オレも思っていた。
でも、あくまでオレの場合だけど、噂は本当だった。
入社して数日を過ごす中で、確実にココは黒色企業だと感じることがいくつもあった。だっておかしいでしょ、職場環境をより良くするために社労士がいるんじゃないの?
入社3日目にして所長がキレて怒鳴り散らしているのを目の当たりにする。
これまでも職場でキレちゃって怒鳴っている人などはいたが、そんな人は対して出世もせず小さい人間だなという判定をしっかりと受けている。しかし、今回はそんな話では済まされない。組織のトップがやっちゃってるんだから。
そんなのパワハラじゃないよと言われちゃうと困るから、所長から先輩社労士に向けられた怒声の一部を紹介します!
「聞けよ!誰が責任取るんだよ、おまえか?おまえじゃねぇだろ、俺だろ、所長だろ、なんでこんなことになってんだよ、あぁん!?!?」
これを大声で、思いっきりブチ切れた感じで言ってもらえると、イメージが湧くと思う(笑)
これはパワハラでしょ。そもそも職場で「おまえ」って言葉遣いをする大人を初めて見たわ。しかもこれ、先輩社員が付き合いの長い顧客と話をする中で、本来ならお金をいただいて引き受けるべき仕事を勝手に受けちゃったから怒っているという場面。
その仕事もそこまで手間がかかるものでもない。ひな形とかあるから、それをアレンジしてあげればいいもの。付き合いも長いし、それくらいならこちらでやりますよというサービス精神もあったと思う。そんな背景を聞こうともせず、自分の知らないところで話を勝手に進めたことと、儲けるチャンスを失ったことにブッチブチにキレている。
気持ちは分からんでもないけど、所長と先輩社員ももう長い関係。これまで事務所を支えてきている先輩社員に何もそこまでとオレは感じていたから、ドン引きですよ。しかも周りの職員さん曰く、こんなことは日常茶飯事。
過去のメールとかも見せてもらったら、メールでもキレまくってます。「ふざけるな」「甘えるな」「結果を出せ」「俺(所長)がいないと何もできないのか」などなど汚い言葉が盛り沢山。
文章に残ってしまう、記録に残ってしまうなんて考えたことないのかな。
入社してから数日でこんな状況に出会うことができるなんて、貴重な体験。
ねぇ、面接のときの「いい人」はどこいった?
これを「面接詐欺」と名付けたいと思う。
第7章 黒から暗黒へ!
入社してからわずか数日でとんでもない事務所だという確信を得た。
毎日毎日行きたくないなーと思いながら出勤するのは本当にツライ。
社労士事務所としてお客様の相談に乗り、「法律で決まっていることですからそこはしっかりやりましょう」とアドバイスしている一方、自分の職場では一切それが守られていない。
「矛盾」という単語はうまいこと言っているよなぁ、今のオレのためにある単語だよだなぁという思いを嚙みしめる日々。
入社後、数か月から半年も経つとこの社労士事務所を自慢するネタに事欠かない状況になってきた。
もはや黒色では済まされない、暗黒時代。そのいくつかを自慢しよう。
辞めさせない、逃がさない
こんな事務所だから周りには常に「辞めたい」と思っている人が何人もいる。とはいっても、そもそも9人しかいないから、ほぼ全員だ。
その中でも、もう限界という人は所長へ退職したい旨を、規程どおり1か月前には伝えるのだが一筋縄ではいかない。そこでもお得意の罵声。
周りへの迷惑を考えているのか、自分だけよければいいのか、お客様に対して失礼だなどなど、ありとあらゆることを並べ立て、「退職したいという話が出るのは、事務所内部に問題があるからだ。おまえらで話し合って解決して、引き止めろ」という業務命令を出してくる始末。
周りへの迷惑? そっくりそのままお返しします。
自分だけよければいい? はい、そうです、この事務所にいる限り。
事務所内部の問題? そのとおり。でも問題なのは「おまえ」だよ!!
結局、全員での話し合いも行われるものの「こんな事務所だけど、どうか辞めないでくれ」などと言えるわけもなく、引き止め失敗というのがお決まりのパターン。
その後どうなるかというと、話し合いの結果も踏まえて改めて退職の意思を伝えに行った際に延々と所長の説得を受け、根負けし、3か月から半年後に辞めるということで決着。
よく刑事ドラマで見る、長時間の取り調べが苦痛すぎてやってもいない罪を認めてしまうっていうのとそっくりです。
年次有給休暇って何ですか?
オレが勤務した1年間で有給休暇を取得した人は体調不良の場合を除けば、8人中4人くらいが各1日ずつを取得した程度である。
オレも結局、自分のための休暇は半日休暇を2回ほど取得して1年間の勤務を終えた。この2回も転職のための面接だったわけだけど(笑)
所内では呪文のように「権利を主張する前に労働者のとしての義務を果たせ」という所長の言葉が蔓延しており、有給休暇を活用してプライベートを満喫するという雰囲気は全くない。
そもそも、休みを申請すること自体が面倒だと感じてしまうのだ。
休みの申請を所長へ行うというルールになっているから、そこで所長との接点が出来てしまう。所長との話すのが苦痛すぎるから、休みの申請するくらいなら働くかという感覚。
ここまでくると異常、いや洗脳か。それくらいに職員はマヒしていた。
ちなみに労基法の「年5日の有給取得義務」はどうしたのか?
こちらにつきましては、体調不良時の消化、半日取得がメインとなってございました。半日取得と言っても午前中に取得して深夜まで働く、午後休での取得の場合は事務所を出るのが午後4時など、ほぼフル勤務でございましたとさ。
所長様は好待遇♡
バレていないと思っているのかと疑ってしまうくらい社員との格差を実現させていた。
社労士事務所の求人を見てもらうと大抵は年収300~500万というのが多いと思う。オレの事務所もそれくらいの水準であったが、所長様は別格。
推定だが1500万円くらいは得ているだろう。
高級車に乗り、高いスーツを着て、地方出張へ行きまくり、夜は飲み会三昧。
事務所の仕事には大して興味を示さない一方、ミスがあれば怒鳴りたい放題。
こうした状況で働いていると「おまえら職員は所長がより良い生活をするために働くロボット」程度にしか扱われていないのがよく分かる。
ちなみに俺の約20年の社会人生活でボーナスが全く支払われなかったのは、この社労士事務所にいた1年間だけだ。業績不振により「賞与ナシ」。所長の給与を減らして配分したらええやんと誰もが思っていたことは言うまでもない。
打ち合わせ・ミーティング大好き
とにかく打ち合わせが多い・長い。
毎日最低でも1時間、顧客からの電話が鳴らなくなった夕方、夜なら長い時には3~4時間やっちゃうよ。
業務に関連するミーティングというよりは所長様の精神論と自慢話。
こういう気持ちが足りない、所長がいかに苦労したか、所長がいかに成功を成し遂げたのかなどなど。そもそも何を成功と考えているのか、聞いている方は???だけど。
自分が語っている姿に酔いしれ、それを職員が真剣に聞いている(フリをしている)場が好きみたい。この時間を業務に充てれば、もっと色々なことが出来るだろうに・・。
またこのミーティングは公開説教も実施される。
誰かが起こしたミスを叱責し、悪かった点を吠え、見せしめにすることで反省させるという、古いというか、陰湿というか、古典的な方法でとにかく時間が無駄に過ぎていくのである。
まだまだ細かいことを挙げればキリがない。
最後に断っておきたいが、オレの周りでも社労士事務所にて快適に働いている人がたくさんいる。特定社労士の研修であった仲間はみんな楽しそうに働き、日ごろの業務の悩みなどを共有していた。
オレも経験を積み、そうした会話に参加したかった。だからこそ社労士事務所に転職したのにこのザマだ。巷に噂されているとおり、厳しい環境にある事務所もあるよということを心の底からお伝えしておきたい。
第8章 番外編 社労士事務所に勤務して良かった点
オレにとっては、これまでに経験のない職場環境で社会保険労務士として1年間勤務したわけだが、いくつか良かった点もある。
各種事務手続きを学ぶことができた
これが1番の収穫だろう。
オレは社労士事務所へ転職する直前に初めて人事部を経験はしたものの、規程整備の下請けや人の配置などを主に行っており、労災・雇用保険などに関連する事務は未経験のままだった。
試験の時にはどのような書類をいつまでに提出するといったことは学んだものの、実務で行うにあたってはそうした知識もさほど役には立たず(忘れていたというのも大きな要因ではあるが)、実践してこそ身につくことも多く、大変勉強になった。
今後、開業または社労士事務所への転職を考えている方もこうした事務手続きが未経験だと不安だろうし、最初はかなり苦労する。たぶん。
しかし、慣れてくれば色々と考えながら作成していくのも楽しくなってくる。
オレはハローワークや労災担当の部署などに電話をしまくり「初めてなので教えてください」とお願いして、申請事務を行っていた。社労士だからと気取らずに最初はどんどん教えを乞うという姿勢でいいと思います!!!
実際の労務問題に触れることができた
事務作業はもちろんですが、色々な企業が様々な問題を抱え、対応しているということを肌で感じることが出来たのも非常に勉強になった。
使用者側も労働者側も私の想像以上に大胆な行動が多いのだなというのが正直な感想。
私が勤務していた事務所は顧問社労士として、使用者側の立場にいたわけだが顧問先から「頭にきてクビだ!明日から来なくていい!と言ってしまったが何か問題はあるだろうか」、「従業員が音信不通になってしまったが退職扱いとしてよいか」、「退職代行から書類が届いたがどうしたらよいか」といった相談が頻繁に来ていた。
例として記載した相談からも分かるとおり特に多いのが「解雇・退職」に関する問題とそれに付随する金銭問題である。こうした労使間トラブルというのは想像以上に頻繁にある。少なくともオレの事務所では非常に多かった。
今思うと、他の社労士事務所はどうなのかとは思う。
こうした問題が世間一般でも本当に多いのか、それとも「類は友を呼ぶ」効果が働き、黒色組織は黒色事務所へ相談するという流れが出来ていたのではないかとも想像される。
第9章 再び転職活動開始 社労士引退を決意
社労士事務所勤務も半年を経過した頃から、この事務所で働き続けるのは止めようという思いが急激に強くなり、再び転職活動を開始することにした。
社労士事務所勤務で学べることはまだまだたくさんあるのは分かっていたが、それ以上に職場環境に耐えられず、学ぶ気力さえも吸い取られてしまう。成長したい、学びたい、そして顧問先の方の役に立ちたいという気持ちすら湧いてこなくなってしまった。
いかに所長との接点を持たず、穏便に1日を過ごすかが毎日のメインテーマであり、そのことだけを考えて毎日過ごしていた。
そんな毎日つまらないよね。
ここにいても得られるものは何もない、しかし、社労士としての仕事自体はまだまだ経験したいという気持ちがあったオレは別の社労士事務所への応募を厳選して行った。
本当ならもっとたくさんの社労士事務所へアプローチし、より良い環境を求めて活動したかったが、いかんせんその時間が無い。仮に書類がとおったとしても面接に行くことが出来るか否かもはっきりとしない。
そうした制約もあり、オレは慎重に事を進めざるを得なかった。
残念ながら1社目に応募した社労士事務所は面接で落ちてしまった。
そして2社目の社労士事務所に行ったときに、話もはずみ、これは手応えアリ!と強く感じた。その気の緩みからつい余計なことを話してしまった。
「オレがいま勤務している事務所の所長はすぐキレて、怒鳴るんです。だから皆、辞めたがっていますし、もう事務所内部もボロボロですよ。あははは~」と。
それに対する面接先代表者の言葉を聞いて、「もう社労士事務所で勤務するのは止めた方がいいのかもしれない」とオレは感じた。その代表者の発言は
「それは所長さんが正しいですよ。私も所長さんと同じ代表者という立場にいるから分かるんですけどね。ワタルさんの勤めている事務所の所長さんが何でそんなにキレてしまうのか分かります?所長さんに比べて、周りの職員のレベルが低すぎるからですよ。そういう時には怒鳴りたくもなります。私もゼロではありませんよ、そうした言動。」
あーぁ、ここも同じなんだ。
そこからはお互いに一気にトーンダウン。面接通過の連絡が来ることもなかった。断る手間が省けたので、こちらもありがたい結果だったが。
しかし、オレはこの面接を機に「社労士事務所はもういいや」と思うようになった。
選びに選んで応募した事務所でも、今と変わらぬ生活になってしまう、社労士事務所は黒色ですという噂もあながち間違っていないのかもしれない。
そう考えた瞬間、全身の力も抜けてしまい、オレは「社労士という業務からの引退」を決意した。
第10章 退職まで
社労士事務所への転職願望がすっかりと消え失せてしまい、そこからは範囲を広げて転職活動を行った結果、無事にある企業から内定をいただくことができた。
40代半ばのオッサンを雇ってくれるなんて、本当にありがたい話である。
ここでも社労士としての資格を保持していることが役に立ったのかもしれない。
さて、問題は退職をどう伝えるかだ。これが最後の難関である。
内定をいただいたということは、辞めるべき日付も決まっている。他の人のように先延ばしにされるわけにはいかないのである。
まぁ、普通はそんなこと自体認められていないんだけどね。
しかし、結果はあっけない幕切れであった。
次が決まっていることを告げると、そのまま了承されたのだ。
たまたま所長の機嫌がよかっただけなのかもしれない。周りの人へはあらかじめ話しておき、概ね「脱出おめでとう!」と言ってもらうこともできた。何人かは「周りへの迷惑を考えない奴」という反応で、その日から退職までほぼ無視され続けたが。
しかし、そんなことどうでもいい。何物にも代えがたい解放感に浸っていた。
退職を決めてから数日が経つと所長から「君の転職が他の人へも悪い影響を与えている、どうしてくれるんだ!」という電話が私個人の携帯電話に掛かってきた。
最後までコレかよ。
よっぽど「あなたのせいですよ」と言ってしまおうかとも考えたが、それをすればまた明日以降もみんなを巻き込んだ大々的な説教大会が開催されてしまうのは明白。ここはぐっとこらえて「大変申し訳ございません。」を連発しておいた。
全く気持ちのこもっていない謝罪などいくらでもしてやるわ!
こうしてオレの1年間にわたる社労士としての勤務は終わりを迎えた。
社労士としての業務はツライこともあるけれど、本当に楽しい。度重なる法律改正などへの対応など、勉強を続けていくのも非常に刺激的だ。
社労士事務所への転職を考えている方は、ぜひ慎重に、長く続けられる事務所を見極めて充実した社労士ライフを送られることを願っております。
最終章 社労士事務所へ就職・転職する際のポイント
最後に、オレのこれまでの経験を踏まえて、オレが考える「社労士事務所へ就職・転職する際のポイント」を紹介させていただきたい。
なるべく大きい事務所を
小規模な事務所は士業といえども一般的な中小企業です。
そしてボスは中小企業のオヤジです。
組織も何もあったものではありません。オヤジのいうことが全てです。
そうした環境でも平気な人はいいと思いますが、組織として機能しているところでこれまで働いてきたという方が転職などを考える際には、同じようにある程度の規模があり、しっかりと組織として機能している事務所を選ぶことをお勧めします。
所長の過去の経歴を調べよう
これも事務所の雰囲気を知るためには大きな指針となるでしょう。
社労士事務所での勤務を得て独立した人、中小企業にいた人、大企業にいた人、様々なバックグラウンドを持つ人が社労士事務所を開業しています。
何がいい・悪いというのは好みも分かれますので一概には言えませんが、転職を考えている先のホームページを見れば、大抵は所長の経歴が掲載されているはずです。
例えば、営業をしていたという人は人当たりは良いでしょうが、実際はガンガンいこうぜ!という雰囲気を作り上げているかもしれません。
社労士事務所での経験しかない人は、一般的な会社での当たり前のルールを知らないかもしれません。
所長の過去の経歴を調べ、自分の想像力を膨らませて、本当に自分に合っている会社なのか否かを冷静に判断しましょう。
従業員に「所長様の家族」は、いない方がよい
所長の家族が従業員として勤めているパターンがあります。
これも職場の雰囲気づくりを考えるとお互いにあまりよろしくないと個人的には思います。
代々、その家族の方が所長を歴任することになっているといった場合は含みません。
後を継ぐ方の場合は資格を取得し、相当の責任と覚悟を持って継がれるわけですから、そこには並々ならぬ苦労もあるでしょう。
一方で、事務員として所長の配偶者、兄弟姉妹、お子さんが働いている場合は要注意です。
私の勤めていた事務所も所長家族がいたのですが、好きな時に来て、大変な仕事はすることもなく、それなりの給料を貰っているようでした。
怒鳴り散らしている所長を見ても、それをとがめることもなく、怒鳴られた従業員を励ますわけでもなく、全く気にしていない様子。
ましてや、職員の雑談内容など細かい所まで報告しているのです。
そもそもビジネスの中にプライベートを持ち込まれたような気がして、このような職員構成はあまり好きではありません。
HPが充実しているか
組織としてしっかりと機能しているかを見極めるには規模も大きな要素だと思いますが、様々な転職サイトで求人を行っている社労士事務所を見た限り、HPが充実しているかということと、企業としての充実度は比例していると感じています。
HPが貧相な社労士事務所へ面接に行くと、事務所がマンションの一室であったり、狭い事務所であったりという可能性が高かったです。
狭い事務所が一概に悪いとは言えないわけですが、そうした事務所では整理整頓もあまりうまくいっていない印象です。
実際に働いてみると結構気になることもあるんですよね。これまで務めてきた企業とどうしても比べてしまいます。
例えば、個人用ロッカーが無い、トイレが男女共用、備品がほぼ無いなど、本当に細かくて個人的な感想なのですが、私には合いませんでした。
入社する前に把握するのが難しいですけれどね。
ビジョン・コンセプトのみが充実していたら要注意
HPが充実しているかという内容とも被るのですが、事務所のビジョンやコンセプトについての記載が他と比べて異様に充実している事務所も要注意だと思います。
ましてやその事務所が比較的小さい規模の場合、理想だけは高く持っている中小企業のオヤジの思いが記されているものと推察されます。
そして、そこに掲げられている内容はほぼ実現されていないでしょう。このビジョンいいなー、このコンセプトには共感できるというものは多々ありますが、鵜呑みにしないよう気をつけてください。
固定残業の有無
社労士事務所は固定残業代を支給されているところが多いと思います。
私は社労士事務所は1社しか経験していませんので、全ての事務所が該当するとは思いませんが、私の事務所は固定残業代の対象となっている時間は確実に働いておりました。
入社前は安易に「固定残業代が支給されるなら、どんどん仕事を終わらせてサッサと帰ろう。それだけ得するから」と思っていました。
現実はそう甘くはありません。
早く帰れそうな人がいたら、その分業務量が増やされるのです。効率化も何もあったものじゃありません。
結局、固定残業ギリギリまでは働けという制度なのかと思ってしまいました。
ちなみに固定残業分として設定されている時間を超え、残業代が支給されることになるとそれはそれで怒られました。
固定残業代が支給される場合は、実際の労働時間もしっかりと確認するようにしましょう。
面接時などで提供される資料が洗練されているか
これまで一般的な企業に勤めていたものの、社労士事務所への転職を考える場合、その事務所の資料作成能力にも着目するのも良いと思います。
これまでお勤めされてきた中でワードやパワーポイントを用いて資料作成する機会があったかと思います。そうした経験を踏まえて、転職を考えている事務所から提示された資料を見た時に、作りが貧相である、雑であると感じた場合は要注意です。
先に記したように私が入社した事務所でも面接の際に簡単な資料で事務所の紹介をしてくれたのですが、まぁ、これが雑なパワーポイントでした。
その時は「あまり得意ではないのかな」くらいにしか感じませんでしたが、実際に入社してみると事務所が活用しているエクセル、ワード、パワーポイントなども同程度であり、効率的という単語からはかけ離れている作業が非常に多かったです。
自分が「雑な作りだな」と感じた事務所は疑ってかかるくらいの方が賢明だと思います。
年間休日数にも着目
求人概要を見ると、年間休日数についての記載もあると思います。
通常、会社に勤務している場合は土日・祝日が休み、加えて夏季休暇、年末年始休暇というパターンが多いのではないでしょうか。
私が社労士事務所勤務前に勤めていた会社も全てがこのパターンでした。
そうすると、1年が52週。
土日休みが52週×2日=104日。
現在、土日以外の祝日は16日。
夏季休暇が仮に3日、年末年始は29日~3日が休みとすると、元旦を除く5日間が休み。
これらを合計すると、104+16+3+5=128日となります。
一方で社労士事務所の求人を見てみますと、ハッキリと「年間休日日数●●●日」と記載されている場合もあります。
その場合はこの日数が厳格に守られるというケースもあります。
それに伴い、日数が何日間と記載されているかによって、場合によっては祝日・土日に勤務するというパターンが発生する可能性もあります。
125日あたりを目安に休みのパターンもしっかりと確認しておくことをオススメします。
置いてある書籍も要チェック!
これは何社もの社労士事務所へ面接に行ったことで気づいた点です。
置いてある書籍が古いところは要注意!!
社労士の業務は常に情報が更改され、新しい知識を吸収していくことが必須です。
もちろんインターネットであらゆる情報を確認することが出来ますが、やはり深い情報を正確に把握していくためには専門書による知識の蓄積も必須です。
しかしながら、私が勤務した事務所、面接に行って「ここは微妙かも・・」と感じてしまった事務所は高い確率で「古い書籍」の宝庫です。
なかなかそこまでチェックする機会は無いかもしれませんが、可能であれば事務所の見学などを申し出て、書籍だなもササっとチラ見してください!!
個人的には以下の書籍の有無、そして最新版があるかは大きなポイントだと感じています。
あせらない
転職活動をしているということは、少なからず現在の職場に不満があるということです。そうしたケースが多いでしょう。
そのため、より良い環境を求めているわけですが、そうしたマインドの中で転職活動を行っていますと、特に私のような中高年は面接に進んだだけでも「行きたいと思ってしまう」→「その会社がよく見えてくる」という現象に陥りがちです。
資格を活かせるなら多少の不満は我慢できるなどと軽々しく思わず、誇りを持ってあせらずに転職活動を進めてください。
妥協しない
先ほどの記載とも被ってしまいますが、なかなか社労士事務所への転職が決まらない中で、面接に進んだ企業などがあるとどうしてもよく見えてきます。
環境や金銭面でどうかなぁと感じていても、せっかく取った資格を活かしたいし、最初は我慢も必要かなと考えてしまう可能性があります。
しかし、1年も経てば軽々しく妥協するべきではなかったと思ってしまう日が必ず来ることでしょう。結局、また転職活動するハメになってしまいます。
就職・転職先が決まらないことを恐れず、焦らず、全てに納得した上で自分に合った社労士事務所を見つけられるよう努力しましょう。いや、努力すべきです!!
終わりに
「社労士事務所で働くことは幸せなのか?」
という質問をもし私がされた場合、簡単に答えることは出来ません。
かなり悩んでしまいます。
私が勤務した事務所のことを考えればイエスとは言えない一方、お客様の話を聞き、共に成長していくための道を探っていくことは本当に魅力のある業務です。
せっかくチャレンジした社労士試験です。皆さんがよりよい社労士ライフを送ることができるようお祈りしています!!
おわり