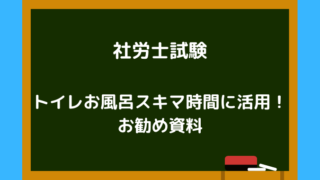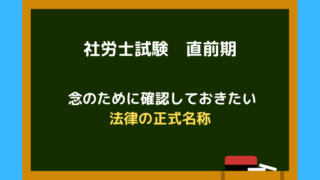社労士試験 8月の過ごし方 これは守って!5つの「ない」
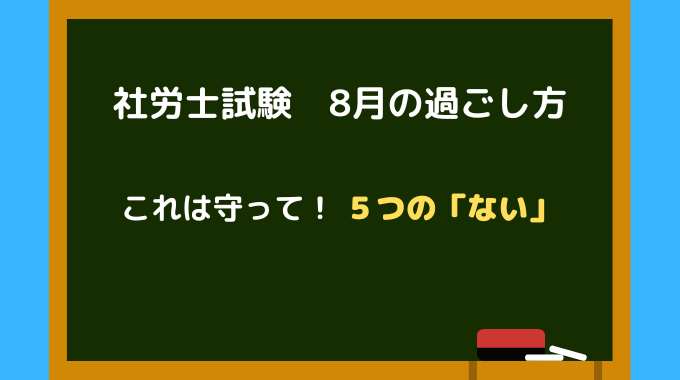
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
いよいよ8月!本試験に向けて最後のひと踏ん張り!そんな勢いに乗っている中、これだけは守ってほしい5つの「ない」をお伝えします!
はじめに
いよいよ本試験まで1か月を切りました。
とうとう来たかという思いで緊張している方もいるかと思いますが、まだまだ時間はあります。
自分が立てた計画に従って、ひたすら愚直に勉強しましょう。
そんな中、今回は私の3回の受験経験から、8月にふとやりたくなってしまうけれど、そこは我慢して守っていただきたいという5つの「ない」を紹介します。
① 深入りしない
1つ目は「深入りしない」です。
直前期はひたすら過去問を解くという方も多いかと思います。
もう何度も解いているのに、ふとした瞬間に「あれ!?こんなことテキストに書いてあったかな??」という疑問を抱いてしまった経験ありませんか?
各種テキストにはそれぞれ記載されている内容に若干の差はあるものの、試験に出る可能性のあること全ての内容が記載されているというテキストは存在しません。
出題頻度の高いもの、基礎的な内容、法改正等の新しい情報などを中心にプロの方が取捨選択して、大切だと思われる内容が掲載されているわけです。
そのため、当然のように過去問や模試にはテキストに記載されていない内容も出題されるわけですが、これまで気にならなかった点がたまたま自分のレーダーに引っかかってしまうことがあります。
加えて「他の人が使っているテキストには記載されているのでは?」「あまり見ない内容だから、そろそろ出題されるかも。深堀しておこう!」と想像は膨らむばかりです。
本試験が近いため、余計に敏感になっているということもあると思います。
しかし、そうしたマイナー情報を調べるのには時間もかかりますし、その努力に見合った成果が出るとは限りません。
8月になって気になる点が出てきてしまった時は、深入りすることなく丸覚えしてしまうか、思い切って捨ててしまい、基礎的項目の徹底に注力しましょう。
全ての項目を暗記している人なんていませんよ!!
② 広げない
2つ目は「広げない」です。
直前期になりますとこれまで考えもしなかったことが頭に思い浮かんできます。
「横断テキストを丸暗記しよう」
「市販のオリジナル問題集を買ってくれば、出会ったことの無い問題に出会うこともあり、本番対策になる。その上、新しい知識をゲットすれば一石二鳥だ!」
などなど、直前期にやろうと決めていたことの範囲を広げてしまっていませんか?
気持ちはよーーーく分かりますが、ここは我慢です!
今取り組んでいる内容が完璧になっているわけでもありませんし、新しいものを増やしたとしてもすぐに頭に定着されるわけでもなく、結局は回数をこなさなければ自分の実力にはなりません!
何か足りない、もう少しやっておこうという気持ちがどうしても出てきてしまう場合は、過去に取り組んだことはあるけれどもそれ以降はあまり触れていないもの、例えば学校で行われた実力試験やミニテストなどにしておきましょう。
今の時期に取り組む範囲を広げてしまうのはNGです!
③ まどわされない
3つ目は「まどわされない」です。
直前期になりますと、これまで以上に活発にあらゆる情報が飛び交い、溢れ返ってきます。
- 「××校の〇〇先生が今年は△△が出ると言っていた」
- 「法改正の中でも特に◇◇が怪しいらしい」
- 「▲▲の判例は比較的新しい中でも重要判例だから間違いなく出る」
などなど、インターネット上ではお祭り騒ぎです。もっと身近なところでも
- 「●●の冊子についているチェックリストがかなり使えるらしい」
- 「(同じ資格学校内で)◎◎先生の作った資料が超いいらしいよ!」
なんて話を聞くことがあるかもしれません。
しかし、そんな声に惑わされないでください。対処方法も変わりません。まずは目の前にあることに、計画どおり全力で取り組むべきです。
それでも余裕があるという方は取り組む価値があるかもしれませんが、そもそも8月に余裕のある人などいないでしょう。
新たな情報を入手したとしても、自分に取り入れるべきか否かを判断し、取り入れた場合にはその中でも知っていること、知らないことを選別し、さらに知らないことの中でもどこまで取り入れていくかなどの作業は必要になります。
それも結構な手間になりますので、余計な情報に翻弄されることなく、我が道を突き進みましょう!
④ 睡眠を削らない
4つ目は「睡眠を削らない」です。
睡眠を削ってはいけません!まずは体調管理が最重要事項です。
僅かな時間すら惜しいという気持ちは分かりますが、試験当日に向けて朝型に切り換えるなど、規則正しい生活へシフトさせていくことも大切な準備の1つです。
一方で勉強中のプチ仮眠は私も必要だと思いますので、積極的に取り入れていきましょう。眠たいまま勉強しても全く頭に入りません。
しかし、あくまで仮眠ですから必ず起きる仕掛けを施してからお休みください!
脳が最も活発に働くのは起床してから4時間後と言われています。
午後に行われる択一式に照準を合わせることは不可能ですので、選択式に狙いを定めるのがベストですよね。
選択式は10:30スタートですから、その4時間前ですと6:30起床が最適ということになります。こちらを基準にして、まずは実際に6:30に起床し、4時間後である10:30にどれくらい頭が冴えているかを実感しましょう。
もしかしたら、この4時間というのも人によっては多少の誤差があるかもしれません。
本番に向けて試行錯誤し、少しでもベストな状態で臨むために、小さなことでも努力を惜しまず試すべきです。
いずれにしても徹夜が続くといった生活は避け、睡眠も大切にしてください!
⑤ あきらめない
5つ目は「あきらめない」です。
私は「今年もダメだったら、来年も頑張ればいいや」と自分に言い聞かせ、「もうすぐ試験だ、どうしよう・どうしよう」という気持ちを落ち着かせていました。
そのように考えること自体は悪いことだとは思いませんが、だからといって今年の試験を諦める理由にしてはいけません。
もしかしたら直前に勉強した内容がそのまま出るかもしれません、各科目で得意としている内容がいくつも出るかもしれません。
本試験は終わってみるまで何が起きるか分かりません!
私は合格した年の模試でD判定を取りました。3年目の受験生であるにもかかわらずD判定というのはさすがにショックでした。オワッタという感じです。
しかし、当日の試験ではあまり好きではない年金科目の択一で9点、8点をゲットすることができました。
選択式では2点を取ってしまった科目に救済措置が入りました。
ですから、諦めることはありません。何が起きるか分からないのです。
満点を取る必要もありません。
誰かと点数を競い合うわけでもありません。
私は社労士試験は救済措置により生き残り、その後に受けた簿記2級、特定社労士の試験ともに合格基準となる点で何とか突破しました。順位で言えば最低点での合格です。
だからといって何も問題はありません。
とにかく1点でも多くもぎ取るため、「今年の自分はやり切った!」と思えるまで勉強しましょう。
おわりに
今回は私の経験をもとに超直前期に守ってもらいたい5つの「ない」を紹介しました。
ネット情報に翻弄されないのは大事ですが、モチベーションが下がった、やる気がでないといった時には諸先輩方の合格体験記なども活用して、勉強を続けてくださいね!(ただし、読み漁ってしまわないよう注意です)
がんばりましょう!!
私も英語がんばります!!