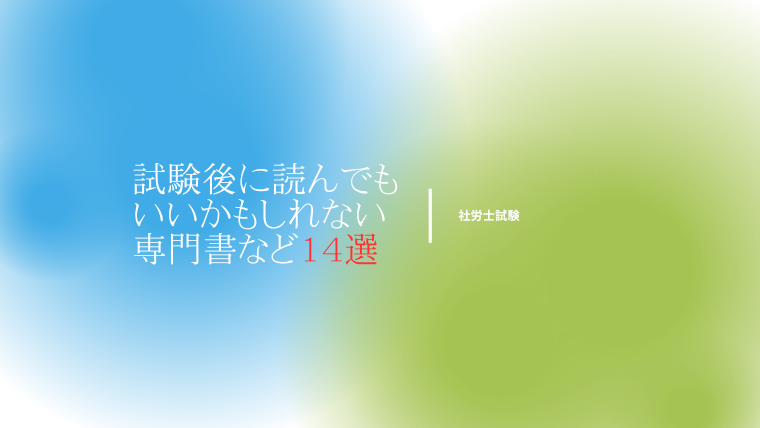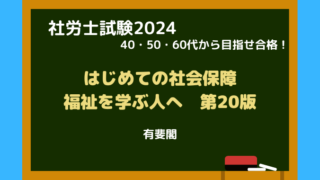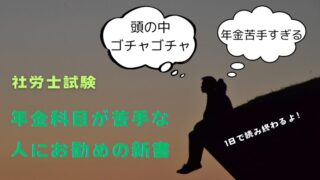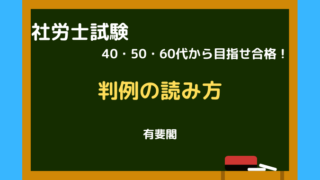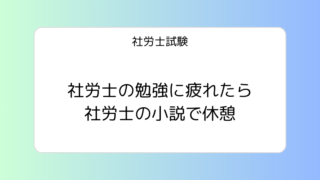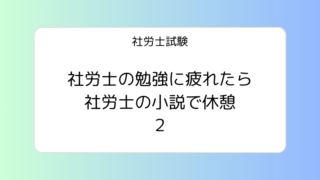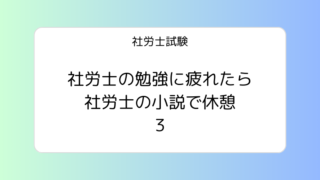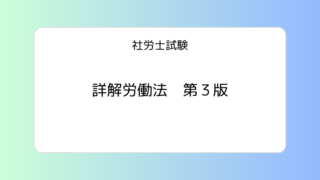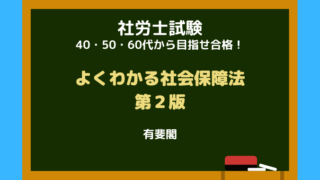こんにちは!
社労士試験が終わって一休み。
早速来年に向けて勉強を始めようと思う人、今後社労士として活躍することを想像している人など色々な思いがありますよね!
そんな時間がある今だからこそ、読んでみてもよいのでは?という書籍を紹介したいと思います。
はじめに
8月の試験、大変お疲れさまでした。
試験が終わったあと、特に自己採点で悔しい思いをされている方は早速翌年の試験へ向けてスタートを切られている方も多いと思います。(実体験済み)
既に課題が見つかっている方、苦手科目が明らかになっている方などは勉強の方針も経っているかと思いますので、ぜひ来年の試験へ向けてスタートダッシュをかましちゃってください!!
一方で、一生懸命に勉強したものの何か漠然と勉強していた、勉強している内容が何か漠然としていて全体像がつかめていない、よく分からないけれどとにかく暗記していたといった感覚を持っている方もいるのではないでしょうか?
そんな時に一度読んでみては??と思う書籍を私が読んだことのある書籍の中から紹介します!
サクっと読める書籍8選
まずは比較的簡単に読むことのできる、薄めの本を紹介します。
お値段もそこまでしませんし、頭の整理には最適ではないでしょうか。
①プレップ労働法
まずは労働法に関するこちらの書籍を紹介します。
全ページ数が約350ページと比較的簡単に読み進められますよ!
その中で「労働法の全体像」「労働契約」「労働者の保護」「労使関係」という4つのテーマを中心に労働法全体を広く、深くなりすぎない程度に学ぶことが出来ます。
労働法の全体像がモヤモヤしているなぁ・・・という方にはオススメの1冊。
②はじめての社会保障 福祉を学ぶ人へ
社会保障関係の概要を把握したいという方はこちらの1冊を。
医療保険や介護保険など社労士試験に関係してくる各種制度はもちろんのこと、試験範囲には入らないものの一般教養として知っておきたい生活保護や社会保障の歴史などについても学ぶことのできる1冊。
1つ前の版にはなってしまいますが、本書について詳しく知りたいという方はこちらもご覧ください。
③知らないと損する年金の真実
最近のテストでは確実に得点源となってきている「年金」が苦手だという方はこの1冊。
世間で騒がれているような年金に対する疑問やイメージについて、非常に分かりやすく解説してくれています。
新書で分量も多くないので、ぜひ一読されることをオススメします!
詳しくはコチラでも紹介しています。
④「条文の読み方」⑤「判例の読み方」
社労士試験は法律の試験です。そして判例に関する問題も出題されます。
そんなわけでこちらを紹介。
条文をどう読むのか、どのようなルールで書かれているのか。
条文で使われている語句、接続詞にどのような意味があるのか。
判例とは何か。
判例の読み方や民事・刑事の違いは何か。
などなど、何気なく学んでいる法律や判例のルールを知ることが出来ます。
こちらも以下の記事でより詳しく紹介しています。
これらの本も非常に薄いので、気軽に手に取ってみてください。
薄いのに内容は充実。
法律の勉強をする一助となること間違いなし!!
⑥社労士のヒナコ シリーズ
勉強に関する本を読むのは疲れた。
でも、何もしないというのは許されない気がする。
そんなときは社労士を題材にした小説などいかがですか?
新米社労士の活躍を描いた作品で、シリーズ物になっていますので、ぜひ1冊目から読んでくださいね!
これを読めば試験に役立つということはあまりありませんが、出てくる用語は勉強している時に出てくるものも多数ありますよ。
ちなみに推理小説に近い面もありますので、そこはご了承ください。
私の個人的な感想はこちらにまとめております。
好みはもちろんあると思いますが、私は非常にハマってしまい、一気に読み進めました!
⑦民事法入門
こちら社労士試験と直接の関係はないのですが、民法を学ぶための基礎本です。
なぜこちらの本を紹介したかと申しますと、社労士試験の勉強をしている中で普通に出てくる用語の基礎が民法にあるからです。
時効、契約、権利の濫用、親族、未成年者などなど。
労基法などを学んでいると「時効は〇年」とか、労働契約といった用語が出てきますが、実際に時効について詳しく聞かれると???ってなりませんか。
もちろんそれ自体が社労士試験で聞かれることはありませんが、一方で昔から「社労士試験には民法を加えるべき」といった意見があるといったことを聞いたこともあります。
そうした声があがるということは、それだけ関連してくるということですよね!
基礎的な知識だけでもいいと思うので、時間のあるときにコチラの本を一読されてみてはいかがでしょうか。
⑧各種 事務手続き本
社労士試験の勉強をしていると事務手続に関する話もたくさん出てきますよね!
でも、そうした経験の無い方にとっては勉強を重ねても実感の沸いてこないものばかりだなと感じるのではないでしょうか?
実際に私もそうでした。
なので、実務に関する本をパラパラと時間のあるうちにめくってみるというのも非常に有益だと思います。
書店には総務・人事関係の業務を行う際、非常に参考になる書籍が数多く販売されています。
未経験で社労士事務所に勤務した経験のある私はこれらの本を買い漁り、業務の参考にしていました。
もっと正直に話してしまえば、これらの本を参考に予習し、そしてお客様へのアドバイスも行っておりました(笑)
未経験だったので、許してくださいませ・・・。
紹介している2冊は未経験の私がワラにもすがる思いで購入しまくった本の中でも活用する機会の多かったオススメ本です。
通読するような本ではないかもしれませんが、勉強していることのイメージを膨らませるにはとても参考になりますよ!
ガッツリ読める書籍6選
ここからは値段も張るけれど、内容も充実。
社労士試験の前に読む必要があるかと問われれば「必要ナシ」という回答になってしまうのですが、読めば読むほど味が出てきて、記憶定着にも役立つであろう専門書を紹介していきます。
①令和3年版 労働基準法 上巻・下巻
いきなり内容もお値段も充実している本の紹介です。
こちら労働基準法の解説だけで、上下巻あわせて約15,000円の出費となります(笑)
しかしながら、私はそれだけの価値のあるありがたい書籍だなと思っておりまして。
まず第一にこちらの書籍は「厚生労働省労働基準局」が編者となっております。
お上が作成した公式マニュアルですよ!
ですから、こちらの書籍に書いてあることはまず間違いないでしょう。
書籍の内容は労基法の第1条から1つずつ詳しい解説、見解などが述べられています。
「この条文が作られたのにはこうした背景がある」
「この条文が作られたときにはこうした議論もあった」
など詳しく書かれているので、堅苦しいながらも読んでいると「なるほどなぁ」と思うことが非常に多いわけであります。
労基法って面白いなぁと感じている方はぜひ飛び込んでみてください!
②八訂新版 労働者災害補償保険法
こちらも負けずに色々と重たい本です(笑)
先ほど紹介した労働基準法のように上下巻とはなっておらず1冊にまとまっているのですが、1冊で約14,000円というバケモノ書籍です。
しかし、こちらも編者が「厚生労働省労働基準局労災管理課」となっており、公式マニュアルでございます。
内容は労基法にも劣らぬ固さですが、それ以上に学ぶことも多い書籍ですので「労災法って何なんだよー」と感じている方は手に取ってみてもよいかもしれません!
なお3冊を並べると「私は労働関係の法律が好きなんだなぁ」と実感することができます(笑)
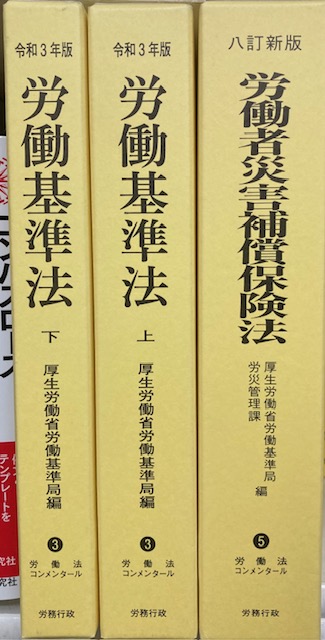
③詳解労働法 第3版
ここから学者の方が書かれた労働法に関する書籍を2冊紹介します。
まずはコチラ。
ものすごい分厚さで内容も充実。
しかも約2年に1回、新しい版が発売されるので購入するのも大変なんですよ(笑)
しかし最新の情報を追ってくれている専門書であり、読んでいても勉強になることが非常に多いです。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
また、こちらの書籍には副読本があります。
書籍の内容に関して寄せられたQ&Aが掲載されていて、「なるほどなぁ」と思うところや「そういう観点で質問するのか!」と新たな視点を学ぶこともできるのでセットで読まれることをオススメします!
④労働法
「労働法」というタイトルの本はいくつかありますので、書店などで眺めていますと「どれがいいのかなぁ」と思ってしまいますね。
そんなときは迷わずこちら。
こちらの「労働法」は社労士業界では非常に多くの人が読んでいる、超超有名本です。
私が知り合った社労士先生も「読んだ」「読まされた」「事務所に何冊かある」と言っておりまして、私も第12版、そして新たに発売された第13版を通読しました。
社労士試験に合格した後、一度は読む機会のある本ですので、先取りして眺めておくのもオススメですよ!
⑤よくわかる社会保障法
社会保険科目が苦手だなぁ、勉強していてもなんか見えてこないと感じている方も多いのではないでしょうか。
そんなときは読みやすい、分かりやすい、でも詳しいというこちらをオススメ。
ありがたいことにこちらの書籍は大学のゼミナールで学ぶという場面が想定されており、全て対話形式で解説されています。
そのため非常に読みやすい!
専門書の中ではそこまでボリュームもありませんので、比較的気軽に学ぶことが可能です。
ただ、発刊が2019年とちょっと古くなってきておりますので、内容のアップデートはご自身でお願いしますね!
詳しい紹介はコチラをご覧ください。
⑥社会保障法 第3版
こちらの書籍は社会保障法に関する本の中でも、かなりヘビーな部類です。
実際に中身をのぞいてもらえれば分かるのですが、大きく総論と各論に分かれています。
各論の中には社労士試験で学習する年金、医療保険、労働保険などについての記載があるのですが、私が面白い、勉強になると感じたのは総論です。
そもそも社会保障とは何ぞや?といったことや、歴史的な背景など各論を勉強していくにあたって知っておくとよりタメになる記載が多いなと感じています。
とはいえ、試験にはほぼ関係ない内容でもあるので、興味のある方はぜひ勉強が本格化しないうちに読んでみてくださいね!
おわりに
社労士試験に役立つかはさておき、勉強の助けになるであろう書籍を紹介しました。
まだまだ他にも専門書や参考になる書籍はたくさんありますが、私が読んだ中でお勧めのものをピックアップしてみました。
勉強に行き詰ってしまっている、実際に今後は社労士として活躍していきたいといった思いがある時に思い切って読んでみると様々な発見があると思います。
中には値の張るものもありますが、これを読んだときの爽快感をぜひ味わってみてください!
もちろん、日頃の勉強が優先事項第1位ですので、ご無理をなさらぬよう。
また新他に読んだ書籍の中でオススメがあったら随時紹介したいと思います。